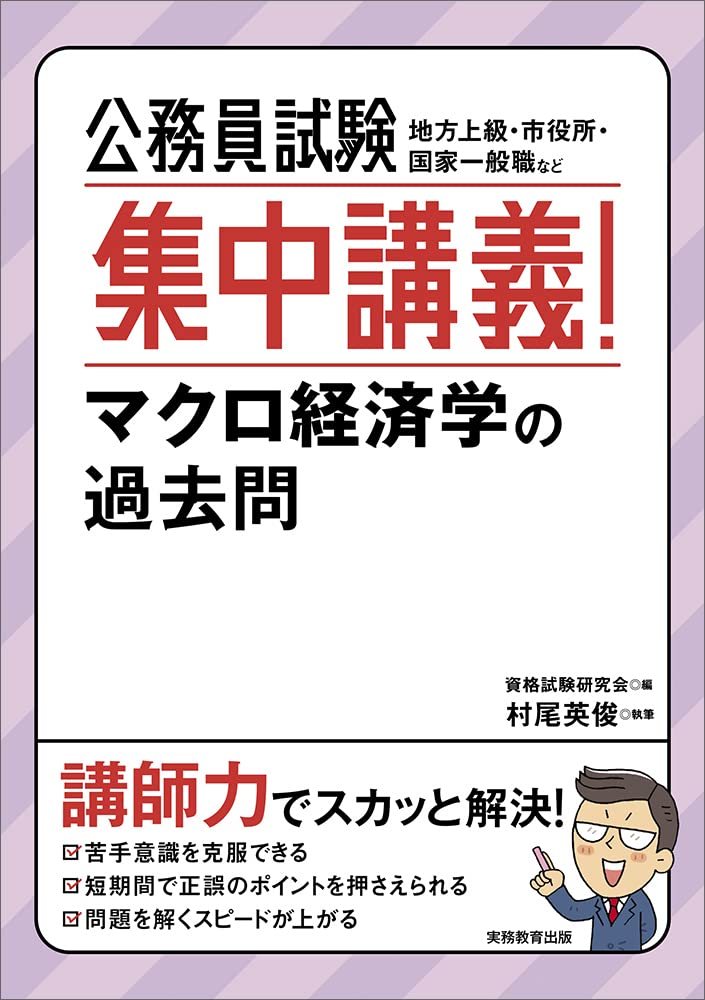若者を戦争に駆り立てた軍国主義の根源」と徹底的に批判され続けてきた教育勅語に光を当てる「神話が教えるホントの教育勅語」を連載でお届けします。
もし、教育勅語に対する断罪が「冤罪」であったとすれば、それは、教育勅語が発布からほどなく、起草者の井上毅 (いのうえこわし) と元田永孚 (もとだながざね)が意図した趣旨とは大きく異なる解釈をされ、政治的に利用されていったからではないかと想像できます。
そこで、そのことを明らかにした上で、当時出された教育勅語を、井上毅や元田永孚の意図に近い形で善意に解釈をすることによって、その言われなき批判に一石を投じることができれば…と思います。
前回の「教育勅語はかく批判された」に対して、今回から一文ごとに善意の教育勅語解説を試みます。今回は、内容によって分けられるとしたら第一段落に当たる第1文と第2文です(下太字部分)。
教育勅語(読み下し文)
朕(ちん)思うに わが皇祖皇宗 国を肇(はじ)むること宏遠に 徳を樹(た)つること深厚なり わが臣民 よく忠によく孝に 億兆こころを一(いつ)にして 世世(よよ)その美を濟(な)せるは これわが国体の精華にして 教育の淵源(えんげん)また実にここに存(そん)す
汝(なんじ) 臣民 父母に孝に 兄弟(けいてい)に友(ゆう)に 夫婦相和(あいわ)し 朋友(ほうゆう)相信((あいしん)じ 恭儉(きょうけん)己れを持(じ)し 博愛衆に及ぼし 学を修め業(ぎょう)を習い、もって智能を啓発し徳器(とっき)を成就し 進んで公益を広め 世務((せいむ)を開き 常に国憲を重(おもん)じ国法に遵(したがい)い 一旦緩急あれば義勇公(こう)に奉(ほう)じ もって天壤無窮(てんじょうむきゅう)の皇運を扶翼(ふよく)すべし かくのごときは、独(ひと)り朕が忠良の臣民たるのみならず、またもって汝祖先の遺風を顯彰するに足(た)らん
この道は実にわが皇祖皇宗の遺訓にして 子孫臣民の共に遵守すべきところ これを古今(ここん)に通じて誤らず これを中外に施して悖(もと)らず 朕 汝臣民と共に 拳々服膺((けんけんふくよう)して皆その徳を一(いつ)にせんことを乞い願う
―――――――――
「朕思うに~」から始まるこの段落については、これまで「神話的国体観や皇国史観に基づいて、臣民に忠孝の倫理観を植えつけながら、宗主としての天皇への服従を強いた」などと批判されてきました。はたして、この見方は正しいかったのでしょうか?
神話的国体観:その根拠を古事記・日本書記におく天皇制国家観
皇国史観:天皇による統治が神代から続いていると権威づけることで、天皇による統治を正当化する歴史観
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
<教育勅語 第1文>
朕(ちん)惟(おも)フニ 我(わ)カ皇祖皇宗國(くに)ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠ニ 徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ
朕(ちん)思うに わが皇祖皇宗 国を肇(はじ)むること宏遠に 徳を樹(た)つること深厚なり
(文部省訳)
朕が思うに、我が御祖先の方々が国をお肇めになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられる。
*旧文部省の現代語訳では、読点(とうてん)で結んで、次の第2文と連続させていますが、ここでは説明の関係で句点をつけました。
朕(ちん):天皇の自称。ここでは明治天皇自身のこと。
皇祖(こうそ)皇宗(こうそう):皇室の祖先
肇(はじ)ムル:創り開く
宏遠(こうえん):広くて遠大なこと
徳:身についた品性。社会的に価値ある性質。善や正義に従う人格的能力。
深厚(しんこう):情け、気持ちなどが心の底から発したものであること。
徳ヲ樹(た)ツルコト:徳をもって国を治めること。
この一文が、戦後、教育勅語は「神話的国体観」または「皇国史観」に基づいていると否定された部分です。果たしてその批判は当たっているのか、そもそも「神話的国体観」と批判される中で、どれほどの人が日本の神話を知っているのか、ここでは、記紀神話に遡りながら、教育勅語の第1文について考えたいと思います。
◆ 記紀神話①
天地開闢(かいびゃく)
まず、日本の神話において、天地開闢(かいびゃく)(天地のはじめ)のストーリーとして、「古事記」では、最初にアメノミナカヌシ(天之御中主神)が登場します。天之御中主神は、天地の始まりと共に成した宇宙の根源(宇宙そのもの)とされている至高の神であり、その御神名は、天(高天原)の中央に座する主宰神という意味です。
その後、タカミムスヒノカミ(高御産巣日神)、それからカミムスヒノカミ(神産巣日神)が現れ(この三柱の神を「造化三神(ぞうかのさんしん)」と呼ぶ)、さらに、ウマシアシカビヒコヂノカミ(宇摩志阿斯訶備比古遅神)、アメノトコタチノカミ(天之常立神)が現れます。天地開闢時のこれら五柱の神々を、「別天津神」(ことあまつかみ)(特別な神という意味)と呼びます。
五柱の神々が出てきた後、神世七代(かみのよななよ/てんじんしちだい)と言われる七代の神々が現れます。その最初の神が国之常立神(くにのとこたちのかみ)で、最後の七番目の神が、イザナギノカミ(伊邪那岐神)(またはイザナギノミコト(伊弉諾尊))と、イザナミノカミ(伊邪那美神)(またはイザナミノミコト(伊弉冉尊))です(以下「イザナギ」と「イザナミ」と表記)。
イザナギは男神、イザナミは女神で、初めて人間の姿をした神さまと言われています。この時代はまだ天と地がはっきりと分かれておらず、別天津神たちは、イザナギとイザナミに、その頃まだ水の上に油が浮かんでいるようなふわふわとしたものに過ぎなかった大地を完成させるよう命じられます。
そこで、イザナギとイザナミは、天と地の境目になる天の浮橋に立って、天沼矛(ぬぼこ)と呼ばれる鉾を持って、雲の隙間から、混沌とした下界の大地をかき混ぜ始め、その鉾を引き上げると、沼矛の先からぽたぽたと滴り落ちて、積もって固まったものが、オノゴロ島(淤能碁呂島)と呼ばれる島で、神話上、この島が日本列島の起源となります。
国産み・神産み
オノゴロ島に天降り、住居(神殿)を持ったイザナギとイザナミは、淡路島、四国を生み、次に、隠岐、九州、本州、壱岐、津島(対馬)、佐渡、さらに本州の八つを産みました(この八つの島を総称してを大八島(おおやしまの)国(くに)と言う)。その後、二神は、国土だけでなく、石や壁など家宅の神々や、風の神、山の神、海の神、川の神といった自然にまつわる神々を次々に産んでいきます。
ところが、イザナギとイザナミの最後の交わりで、イザナミが火の神カグツチ(火之迦(ひのか)具土(ぐつ)神(ち))を産んだ時に大やけどしてしまい、それが元で死んでしまいました。これを嘆いたイザナギは、カグツチを剣で切り殺します。その時に付着した血から、雷神とも剣の神と称されるタケミカヅチノカミ(建御雷之男神または武甕槌神)が生まれました。(なお、タケミカヅチは、現在、茨城県の鹿島神宮の主神でもあり、国譲り神話にも登場する相撲の元祖としても有名)。
イザナギは、亡き妻イザナミを慕って、黄泉(よみ)の国(死者の国)に会いに行くのですが、そこには腐敗して醜い姿に変わり果てたイザナミに慄(おのの)き、結局逃げ帰ってきます。そして、日向(現在の宮崎県)の地へ赴き、黄泉の国での穢れを取り去ろうと水の中に入って禊(みそぎ)をするのですが、その時、左目を洗ったときに太陽神・アマテラスオオミカミ(天照大神)、右目を洗った時に、月の神または暦の神でもあるツクヨミノミコト(月読尊)、鼻を洗った時に、後に八(や)岐(またの)大蛇(おろち)を退治するスサノオノミコト(須左之男命/素戔嗚尊)が生まれます。
この三柱の神は、これまで産まれた様々な神々(八百万(やおよろず)の神)の最後にあたり、特に「三貴子」と呼ばれます。そして、イザナギの指示で、天照大神は、八百万の神々がまします天上界の高天原(たかまのはら)を、月読尊は夜の世界を、そして須左之男命は海をそれぞれ治めることになります。この高天原の主宰神とされる天照大神が、記紀(古事記・日本書記)では、天皇の祖神(皇祖神)とされる神さまで、八百万の神々の中では最高神の地位を占めておられる女神です。現在では、伊勢神宮の祭神として祀られています。
*高天原は通常、「たかまがはら」と読まれますが、本稿では日本書記の仮名表記である「たかまのはら」を使用します。
日本人の世界観
さて、「天地開闢」から「神産み・国産み」までの神話の中に、日本独特の世界観を見出すことができます。世界各国の神話の多くは、天地創造の話しから始まります。キリスト教においては、絶対神ヤハエが、天と地を創造し、日と月と星、海、魚、植物、獣などを創った後で、最後に神の姿に似せてアダム(男)とイブ(女)を創ったとされています。
これに対して、日本の場合は、人間の形をした男女神であるイザナギとイザナミのまぐあい(交わり)によって大地が生まれ、また、山・海・風・雷といった自然の中に存する八百万の神々が産まれています。
また、記紀の世界では、神々が住む天上界(高天原)だけでなく、人間の住む地上の「葦原(あしはら)の中つ国」(日本のこと)、死者の霊が生まれ帰る「根の国(根の堅州(かたす)国)」が描かれています。さらに、天上界から地上の世界に降臨される神々の話し(中には人間と結婚される神さまもいて、祖先神となる)や、地上に住む神さまが根の国にお隠れになる話しなど様々です。そこで、神と人は一体で分離していません。
ですから、日本列島はイザナギとイザナミが創った「神々の国」であり、人間は神の子孫と考えられているのです。もっとも、政治家が「日本は神国(しんこく)である」と発言した場合の「神国」は、政治的イデオロギー(観念)そのものの言葉で危険視されますが、記紀神話の世界でいう神の国とは、全く別次元の世界です。
国造り神話
天照大神の弟神とされるスサノオノミコト(須左之男命/素戔嗚尊)(以下「スサノオ」と表記)と、その子孫にあたる大国主神については、記紀の中では「国造り・国譲り」の壮大なお話しの中に登場します。
母イザナミに会いたいといつも泣いていたスサノオは、天上の高天原にいる姉の天照大神を訪ね、しばらく滞在していました。当初、平穏に過ごしていたスサノオでしたが、元々荒っぽい神であったとされ、たんぼの畦道は壊すなど乱暴な行いを続け、ついには高天原から追い出されてしまいました(スサノオが粗暴な行為をしたという話は誤解釈の説もある)。
追放されたスサノオは、地上の世界である「葦原の中つ国」の出雲の斐伊川のほとりに天降られました。その川のほとりで泣いている奇稲田姫(くしなだひめ・櫛名田比売)に出会います。聞けば、そこに住むヤマタノオロチ(八岐大蛇)に食べられてしまうと言うではありませんか。そこでスサノオは、奇稲田姫を櫛(くし)に変えて自分の髪にさし、やってきた八俣の大蛇を濃い酒で酔わせ、剣でずたずたに斬り殺します。その時、ヤマタノオロチの体から出てきたのが、後の三種の神器の一つである草薙剣(くさなぎのつるぎ)です。
八俣の大蛇を退治した後、スサノオは、奇稲田姫と結婚し、出雲の国を治められ、やがて「根の国(冥界)」に下って行かれました。その後、出雲神話の中心人物となるのは、スサノオの息子とも、数代あとの子孫ともされる大国主命(おおくにぬしのみこと)で、太古、各地において地上の国造り・人造りを進めました。
大国主神(大国主命)は大黒さまとも言われて、打ち出の小槌を持ち、にこやかなえびす顔で、人々に分け施す優しい神様の印象が強いのですが、その反面、大国主神は、「八千(やち)矛(ほこ)の神」とも呼ばれ、広く国を治める為に、矛をもって服(まつ)ろわぬ曲津(まがつ)神(かみ)を戦いによって退けながら国を治めてきました。
また、大国主神には、少名彦神(すくなひこなのかみ)という高天原におられる天津神の子孫、カミムスヒノカミ(神皇産霊神)の御子が側につかれ、二人で、葦原(あしはら)中(なか)つ国(地上の国、日本のこと)の開発をなされました。
大国主神と少名彦神は、医療や土木治水、農耕に至るまで人々の生活のためにあらゆることを施されたことが記紀には紹介されています。医療は、因幡(いなば)の白ウサギの説話に象徴的に示されています。また、「葦原中つ国」に農耕がもたらせたのもこの時とされ、少名彦(すくなひこなの)神(かみ)は、大国主神とともに農耕神と称されています。
このように、大国主神は、地上の「葦原中つ国」日本を長い間、治めていました。その勢力圏は、列島の日本海沿岸を中心に、九州から近畿地方、東北をのぞく東日本にも及んでいたといわれています。実際、奈良県の三輪山の大神(おおみわ)神社の祭神は、大国主神の第1子の事代(ことしろ)主(ぬし)神(かみ)とされています。
国譲り
一方、高天原(天上の神々の国)では、地上の「葦原中国(あしはらのなかつくに)のこうした様子をご覧になられていたタカミムスヒノカミ(高皇産霊神)と天照主大神は、天安河(あまのやすかわ)の河原に八百万(やおよろず)の神々を集めました。
天照主大神は、その場で、「豊(とよ)葦原の千秋長五百秋(ちあきのながいほあき)の瑞穂の国(地上の国)は、わが子、天忍穗耳尊(あまのおしほみみのみこと)が治(しら)すべき国ではないか」と、今でいえば政権交代を希望されました。しかし、「(大国主が治める)この国には、荒ぶる国津神(地元の神)が多いと思われる。どの神を遣わせて荒ぶる神たちを説得させるべきか」と神々に問われ、最終的には、力自慢のタケミカヅチノカミ(建御雷神/武甕槌神)と、足の速いアマノトリフネノカミ(天鳥船神)(「日本書紀」では経津主神(フツヌシノカミ)の二神を差し向けることになりました。
二柱の神は出雲の国の伊耶佐(いざさ)の小浜(現在の稲佐の浜)に降り立つと、タケミカヅチは、剣を抜き逆さまにして柄を下にして突き立て、その剣の切っ先の上にあぐらを組んで座り込み、大国主神に国譲りの直談判をします。そして、大国主神に次のように問いました。
「われわれは、タカミムスヒノカミ(高皇産霊神)と天照大神の命によって遣わされた。そなたが治める葦原中つ国は、天津神の御子の『しらす(治める)』国であると、天照大神がおっしゃっておられるが、そなたの考えは如何なものか。」
すると、大国主神は、「私の一存ではお答えできません。息子の事代主神(ことしろぬしのかみ)がお答え致しましょう。ですがあいにく美保の岬に鳥や魚を取りに遊びに行っております」と答えました。国譲りの重大案件を第一の御子である事代主神に委ねられたのです。
タケミカヅチ(健御名方神)はアメノトリフネを迎えに行かせ、事代主神を呼んで来させます。事情を聞いた事代主神は、「おっしゃるように、天照大神の御子に差し上げましょう」と答えました。事代主神は、若き時より父上の大国主神を補佐し、国造り・人造りに挺身してきました。父同様、服わむ者がおれば、先陣を切って武勇を示して戦ったそうです。
そんな事代主神が「国譲りに応じる」と父の大国主に告げると、そこへ大国主神のもう一人の息子で、力持ちのタケミナカタ(建御名方神/武甕槌神)が大きな岩を抱えて戻ってきました。タケミナカタは「この国が欲しいのなら力比べ(力競べ)だ」と言って大岩を投げ捨て、タケミカヅチの腕をつかみました。
するとタケミカヅチの腕が氷柱(つらら)に変わり、さらに氷柱は剣(つるぎ)の刃(やいば)に変わりました。タケミナカタが驚きひるんでいると、今度はタケミカヅチがタケミナカタの腕をつかみ、軽く投げ飛ばしてしまいました。この二神の力競べが大相撲の始まりと言われています。
力競べに負けたタケミナカタ(健御名方神)は、命に危険を感じて逃げましたが、追いかけてきたタケミカヅチは、信濃の国(現在の長野県)の諏訪湖辺りで、追いつめ組み伏せます。タケミナカタは、葦原中国を天津神の御子に譲ることに応じ、諏訪の地に引き籠もって、外に出ないことを誓いました。タケミナカタは、現在も諏訪の神(諏訪神社の祭神)として祀られます。
タケミカヅチは出雲に帰り、大国主神にこの一件を伝え、この国の統治権を返上するかを改めて問い直しました。大国主神は「仰せのとおり、天照大神のご意向に従って、この葦原中つ国をお譲りします」と返答し、恭順の意を示しました。
ただし、大国主神は一つだけ条件を提示されます。それは、国を譲る代償として、高天原の光輝く宮殿のような神殿を建てて、大国主神自身が住み、祀られることでした。「それが許されるのであれば、私は片隅の国(出雲の国)に隠れて留まることにいたしましょう」と交渉されたのです。
タケミカヅチ(建(たけ)御雷神(みかづちのかみ))は高天原に帰り、「葦原中国の神々は皆、従いました」と大国主神を説得したことを天照大神に報告されると、地上ではほどなく、稲佐の浜において「国譲り」の儀式を挙行されました。その後、大国主神がお隠れになられた後、天照大神の命により出雲の国に、壮麗な御殿が建てられました。この巨大な社が現在の出雲大社で、今も大国主神のみ魂がお祀りされています。
一方、事代主神は、美保の御岬(みさき)に帰られると船に乗って海に出られ、船を踏んで傾け、天の逆手(アマノサカテ)という特殊な柏手を1回打ち、青(あお)柴垣(ふしがき)(青い灌木で造った垣根)に変えられると、そこに篭もり、妻神と共に海中にお隠れになったと伝えられています。
◆ シラスとウシハク
さて、ここまでの記紀(古事記と日本書記)の記述から、教育勅語の「徳ヲ樹(タ)ツルコト深厚ナリ」の意味を解き明かされています。皇祖皇宗が立(樹)てた徳とは、神代の時代から施されていた「シラス(知らす)」政治です。タケミカヅチ(建御雷神)が、大国主神に国譲りを迫った時のセリフを改めて着目してみます。
―――――――――
「われわれは、タカミムスヒノカミ (高皇産霊神)、天照大神の命によって遣わされた。そなたが治めている葦原中つ国(日本のこと)は、天津神の御子の治める国であると、天照様はおっしゃっておられるが、そなたの考えは如何なものか。」
――――――――
これは、一般的になされる現代語訳です。しかし、実際の古事記では次のように書かれています。
―――――――――
「天照大神、高木(たかぎ)神の命(みこと)もちて問いに使はせり。汝(いまし)の宇志波祁(うしはけ)流(る)「葦原の中つ国」は、我(あ)が御子(みこ)の知らす国ぞ、と、言依(ことよ)さし賜(たま)ひき。故(かれ)、汝(いまし)の心は奈何(いか)に、とのりたまひき。
――――――――
現代語訳にある「治(おさ)める」を、読み下し文では、宇志波祁(うしはけ)流(る)「領ける(ウシハケル)」と「知らす(シラス)」と使い分けています。このところを意識して、上記の現代文を言い換えて要約すると次のようになります。
「汝(大国主神)がウシハケル(領く)この国は、本来、天照大神の御子がシラス(知らす)ところの国である…」
では、ウシハケル(ウシハク)とシラスとはどう違うのでしょうか?
「ウシハク」に漢字を当てはめれば、「領(うしは)く」であり、国語辞書では、領地として治める、領有している、支配すると説明されます。歴史的に欧米や中国でみられたように、一人の実力者が戦いによって多くの土地を占領支配し、そこに住む民衆はその支配者の領民、いわば「所有物」のような存在となります。ですから、彼らの観点でいう国家とは、土地と人民を征服することによって成立するとみなされます。
結局、「ウシハク」とは、武力によって国を統治することと解すことができるでしょう。近代に入っても、国家は君民の約束(契約)といった形で成立し、憲法の本質も君主が人々の人権を勝手に制約しないように、君主の行動を縛ることにあります。
これに対して、シラス(シロシメス)とは、「知る」を語源としています。また、「知(し)らす」は「知る」の尊敬語で、「知る」という動詞に尊敬の意を表す「す」のついた語で、(天の下を)統治されるという意味になります。従って、「知らす」は「統(し)らす」とも表記されます。
なぜ、「知る」という言葉が「統治」を意味するようになったのかというと、それは、日本において、天皇(君主)は、神の意思と民の心をお知りになることを根本にして国家(国民)をお治めになられていたからです。
日本は天皇の徳によって国家が始まりました。即ち、日本国の天皇の大御業(おおみわざ)(=なさってこられたこと)の源は、皇祖の心を知り、これを民に伝えると同時に、民の心を知るということです。日本の歴代の天皇は、民のことを、宝として大切にするという意味で、「おおみたから」と呼び民に接してこられてきたという伝統があります。天皇は民を慈しみ、民は天皇を敬愛して、天皇と民が家族的な感情で結ばれる状態を理想としてきました。
天皇が皇位の印として受け継がれた三つのみ宝である「三種の神器」の一つに「鏡」があります。鏡はまさに神の心と人々の心(国民の喜びや悲しみ、願い)を照らし、天皇はにごりのない心で、常に鏡に映ったものを見る、すなわち「知る」のです。
この「シラス」の政治の意味がよくわかるエピソードに、仁徳天皇の「民のかまど」の逸話があります。
「民のかまど」のエピソード
仁徳天皇の四年、天皇が難波高津宮から遠くをご覧になられて
「民のかまどより煙がたちのぼらないのは、貧しくて炊くものがないのではないか。都がこうだから、地方はなおひどいことであろう」と仰せられ「向こう三年、税を免ず」と詔(みことのり)されました。それからというものは、天皇は衣を新調されず、宮垣が崩れ、茅葦屋根が破れても修理も遊ばされず、星の光が破れた隙間から見えるという有様にも堪え忍び給いました。
三年がたって、天皇が高台に出られて、炊煙が盛んに立つのをご覧になり、かたわらの皇后に申されました。
「朕はすでに富んだ。嬉ばしいことだ」
「変なことを仰言いますね。宮垣が崩れ、屋根が破れているのに、どうして富んだ、といえるのですか」
「よく聞けよ。政事は民を本としなければならない。その民が富んでいるのだから、朕も富んだことになるのだ」
天皇は、ニッコリされて、こう申されました。そのころ、諸国より
「宮殿は破れているのに、民は富み、道にものを置き忘れても拾っていく者もありません。もしこの時に、税を献じ、宮殿を修理させていただかないと、かえって天罰を蒙ります」
との申し出が頻頻とあるようになりました。
それでも、天皇は引き続きさらに三年間、税を献ずることをお聞き届けになりませんでした。六年の歳月がすぎ、やっと税を課し、宮殿の修理をお許しになりました。その時の民の有様を「日本書紀」は次のように生き生きと伝えている。
「民、うながされずして材を運び簣(こ)を負い、日夜をいとわず力を尽くして争いを作る。いまだ幾ばくを経ずして宮殿ことごとく成りぬ。故に今に聖帝(ひじりのみかど)と称し奉る。みかど崩御ののちは、和泉国の百舌鳥野のみささぎに葬し奉る」
◆ 井上毅の功績
このエピソードが示すように、天皇は、神の心、皇祖の心、民の心を知ろうとされ、それに自らを合わせ、慈愛に満ちた国造りをなされてこられました。日本では、まさに、天皇の「徳」により、国家が始まったのです。これが、記紀神話の伝承からわかる教育勅語の第1文の「徳を樹つること深厚なり」の「徳」の意味です。
また、この「シラス」の理念こそが、日本の国柄(国体)の根本であり、教育勅語を作成するにあたり、もっとも意識されたことは言うまでもありません。なぜなら、教育勅語の起草者の井上毅(こわし)は、「しらす」について、最も理解を寄せていた人物の一人であったからです。
井上毅の「梧陰存稿」に次のような文章があります(現代語訳)
―――――――――
中国やヨーロッパでは、一人の英雄が出現して、多くの土地を占領し、政府をつくり支配するというように、一人の人間による征服の結果が国家であると解釈される。しかし、日本の場合、皇位継承は、新天皇が皇祖(天照大神)」の御心を鏡に映して、民を治める(しらす)という意義より成立するものである。であるから、日本における国家の始まりは、君民の約束のといった形(西洋でいう社会契約論のような約束事)ではなく、君徳による。これは、「日本における国家学の最初に説くべき定論である。
―――――――――
井上毅は、教育勅語の草案を書いただけでなく、大日本帝国憲法の起草者の一人でもあります。憲法を書くにあたり、井上の立場は、日本の歴史や伝統、慣習を重視することにありました。そこで、記紀や国学書などの国典研究をするなかで、本居宣長の「古事記伝」や「玉くしげ」などから「シラス」と「ウシハク」に着眼するようになったと言われています。実際、帝国憲法第1条は、「大日本帝国憲法ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」ですが、井上毅の草案では、「大日本帝国憲法ハ万世一系ノ天皇ノ治(しら)ス所ナリ」でした。
この「しらす」の精神は、井上が手掛けた「大日本帝国憲法」に続く「教育勅語」にも生かされたことになります。井上毅が「記紀」の中に秘められていた「シラス(治(しら)ス)」に着目し、天皇の私心のない統治姿勢を示す言葉であることを世に明らかにした功績は極めて大きいと考えられます。
「徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ」の真の意味
このように、教育勅語の第一文
朕惟(おも)フニ 我(わ)カ皇祖皇宗國(くに)ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠ニ 徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ
の「徳を樹(た)つること深厚なり」で、歴代の天皇が立てられた「徳」とは、仁、義、礼、孝、忠、信といった儒学が教える徳目を天皇が実践してこられた意味というよりは、天皇が争うことなく慈愛に満ちた民衆のための国づくりである「しらす」による為政(祭祀)を、日本という国が始まった時から、明治天皇まで連綿と続けてこられていることを言っています。「徳を樹(た)つること深厚なり」の「徳」は、天皇の徳(=君徳)のことなのです。
この「しらす」の精神こそ、国体の精神です。明治憲法下の「国体」などというと、神話に基づいて、天皇が国家の主権を一手に掌握した絶対主義専制体制で、教育勅語はこれを支えたと、これまで散々批判されてきました。
しかし、制定者の井上毅の考えには、天皇中心の絶対主義的専制国家、すなわち「ウシハケル」国家などという発想はいささかもなかったでしょう。逆に、天皇が国民の思いを広く「知る」ためには、「しらす」政治でなければならないというのが、井上毅の考えであったと言えます。
日本の神話に基づいて、戦前、三大神勅(「天壌無窮の神勅」「宝鏡奉殿の神勅」「由庭稲穂の神勅」)と呼ばれた皇国史観の指導原理が確かに浸透していました。しかし、記紀神話を通して、古き良き時代の日本の「シラス」政治が明らかになったと同様、次に、国譲り神話の後の記紀の世界をみることによって、「三大神勅」の真の「意義」を明らかにしたいと思います。記紀神話のストーリーに戻ります。
◆ 記紀神話②
天孫降臨
大国主神様から葦原中つ国(地上)の統治権を譲り受けた天照大神は、孫のニニギノミコト(瓊瓊杵尊様)に統治を委ねることにしました。記紀神話は、天孫降臨のストーリーとして進んでいきます。
天照大神は、孫のニニギノミコトを高天原(天界)から葦原中国(地上)に送り出す際、神勅(命令)を出しました。この時の神勅の一つが、日本書記では、前回の投稿で紹介した「天壌無窮の神勅」と呼ばれる神勅(第一の神勅)で、後世に尊重されているお話しです。
第一の神勅:天壌無窮の神勅
豊葦原((とよあしはら)の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂(みずほ)の國(国)は、是(こ)れ吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)也(なり)。宜(よろ)しく爾(いまし)皇孫(すめみま)、就(ゆ)きて治(しら)せ。行矣(さきくませ)、寶祚(あまつひつぎ)(宝祚)の隆(さか)えまさむこと、当(まさ)に天壤(あめつち)と窮(きわま)り無かるべし。
千五百秋(ちいほあき):限りなく長い年月、永遠、千歳、千秋
瑞穂国(みずほのくに):日本列島の別称
豊葦原(とよあしはら)の千五百秋の瑞穗国:葦の生える豊かな稲作の国
爾(いまし):今まさに、ちょうどいま
行矣(さきくませ):「いってらっしゃい」の意
寶祚(あまつひつぎ)(宝祚、天津日嗣):皇位のこと、皇位が引き継がれること、天つ(あまつ)神(かみ)の子孫
天壤(あめつち):天と地、天地
天壌無窮(てんじょうむきゅう):天地とともに永遠に極まりなく続くさま
(現代語訳)
豊(とよ)葦原(あしはら)の永遠なる瑞穂(みずほ)の国(日本)は、私の生みの子(子孫)が、天皇(すめらみこと)(大君(おおきみ))となるべき地である。なんじ皇孫(すめみま)、ニニギノミコトよ、これから天(あ)降(も)りて、しっかりと地上の国を治(おさ(しらし))めなさい。恙(つつが)なくお行きなさい。天つ神の子孫が栄えること(皇位が引き継がれること)は、天地とともに窮(きわ)まることなく永遠であろう。
「瑞穂の国」は日本列島の別称で、「豊(とよ)葦原(あしはら)の瑞穂の国」とは、豊かな葦原では秋になれば稲穂がたくさん稔るみずみずしい国という意味です。
「吾(あ)が子孫(うみのこ)」とは、天照大神の子孫のことで、ニニギノミコト(邇邇藝命)をはじめ神武天皇そして今上天皇(現在の天皇)に至る御歴代の天皇のことをさします。
「爾(いまし)皇孫(すめみま)、就(ゆ)きて治(しら)せ。行矣(さきくませ)」の部分は、天照大神の生みの子よ、地の国(地上の国)を統べ治めよ、つつがなくあれ、という御命令です。
「天壌無窮の神勅」と言われるこのみ言葉は、神代の昔から連綿と続く皇室と日本国の限りない弥栄(いやさか)えを言祝(ことほ)ぐ名言とされています。
一方、御歴代の天皇は、天照大神の「生みの子」で、天照大神の御神霊と一体です。今上天皇(現在の天皇)も、ニニギノミコトや神武天皇と不二一体で、現人神(あらひとがみ)(地上で肉身をもった神さま)であると説かれました。
また、最後の「宝祚(あまひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、当(まさ)に天壤(あめつち)と窮(きわま)り無かるべし」の部分も、「宝祚」を「皇位」と辞書通りに解釈すれば、「皇室の繁栄は永遠である」と確かに読むことができます。
結果的にこの神勅は、「日本国は現人神であらせられる天皇が永遠に統治する国である」と日本の国体が端的に表現されているとして、終戦まで日本の国是となりました。
しかし、記紀の話しに沿って理解しようとすれば、「天壌無窮の神勅」は、日本のあり様が宣言された政治的メッセージではなく、高天原の天つ国から、地上の豊葦原の中つ国(地上の国)へ降りたとうとされている孫のニニギノミコトに対する天照大神の祝福・激励のみ言葉であることがわかります。
「豊葦原((とよあしはら)の瑞穂(みずほ)の国」を大国主神から譲り受けられたわけですから、最初に、高天原の系統の神々によるご統治が始まることを言及されることは自然の流れでしょう。そして、統治のあり方は、領(うし)はく(ウシハク=支配する)のではなく、治(しら)す(=知らす、シラス)です。天照大神は、「就(ゆ)きて治(しら)せ」と、神の心と民の心を照らしながら、政(まつりごと)を行うことを、「子孫(うみのこ)」に求めておられます。
「天壌無窮の神勅」(第一の神勅)は、シラスによる政治が継続されれば、皇位は引き継がれ、日本国(国民)とともに永遠に栄えることができる、との希望が込められている神勅であると解されます。
第二の神勅:宝鏡奉斎(ほうきょうほうさい)の神勅(宝鏡奉殿(ほうきょうほうでん)の神勅)
さて、天照大神は、葦原の中つ国(日本のこと)を統治されるために、御孫のニニギノミコト(瓊瓊杵尊、邇邇芸命)を地上に降ろす際に、八坂瓊曲(やさかにのまが)玉(たま)(勾玉)と八咫(やたの)鏡(かがみ)(鏡)と草薙(くさなぎの)剣(つるぎ)(剣)の三種の寶物(たから)を与えました。
後にいう三種の神器(じんぎ)は、皇位継承のシンボルとして皇室に代々伝えられるもので、皇位継承の証明書のようなものです。この三種の神器のうち、鏡(八咫鏡)を授けられる際、日本書記によれば、天照大神によるご神勅(命令)が出されました。(第二の神勅)。
吾が児(みこ)、此(こ)の宝(たからの)鏡(かがみ)を視(まさむ)こと、当(まさ)に吾(あれ)を視るがごとくすべし。ともに床(みゆか)を同じくし、殿(みあらか)を共(ひとつ)にして、斎(いはひの)鏡(かがみ)と為すべし
(現代語訳)
我が子よ、この宝鏡を見るとき、まさに私を見るのと同じようにしなさい。床を共にし、同じ殿にいて、神聖なる鏡としなさい。
「当(まさ)に吾(あれ)を視るがごとくすべし」の現代語訳である「私を見るのと同じようにしなさい」とは、「この鏡を私、つまり天照大神として取り扱いなさい」と命じられたと解されています。鏡は、天照大神の御真影そのものの象徴であり、天照大神そのもののお姿であるというわけですね。
後半の訳文、「床を共にし、同じ殿にいて、神聖なる鏡としなさい」は、「鏡とともに生活し、住まいを同じにして、鏡を神霊として祀りなさい」、つまり、み鏡を天皇が住まわれる宮中に安置し、祭祀を行いなさいという趣旨であることが想定できます。そこから、この神勅は、私(天照大神)を祀り続けなさいというご命令であることがわかります。
さらに、このご神勅は、「シラス=知らす=治す(しらす)」の根本を教えてくれています。「鏡と共に生活する」とは、「常に天照大神の意思と民の心を汲んで、政(まつりごと)を執ること」とも解釈されます。鏡は太陽神・天照大神の心と、人々の心を照らしています。天皇は純粋な心で常に鏡に映ったものを見ることで、神と民の心を「知る」のです。鏡が、古来、祭祀において、種々の祭具の中で、特に大きな役割を担っているのもこうした背景がありました。
八咫(やたの)鏡(かがみ)のストーリー
三種の神器の一つである八咫(やたの)鏡(かがみ)は、天孫降臨の際、瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)に授けられて以来、天照大神のお言葉通り、宮中に祀られていました。しかし、第10代、崇(す)神(じん)天皇の御代に、強い威力をもった神(ご神霊)と御殿を共にすることに畏れを抱かれた天皇は、鏡を宮中から出して、天照大神を皇居外のふさわしい場所にお祀りされることを決意されます。そして、皇女(天皇の娘)、豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)は大和の笠縫邑(かさぬいのむら)に神籬(ひもろぎ)を立てて天照大神をお祀りされました。
また、次の第11代垂仁(すいにん)天皇の御代において、宝(たからの)鏡(かがみ)は皇女倭姫命(やまとひめのみこと)に託されました。倭(やまと)姫(ひめ)は、新たに永遠に神事を続ける(天照大神を祀る)ことができる場所を求めて、大和の笠縫邑(かさぬいのむら)を出発し、伊賀、近江、美濃と巡り、伊勢の国に入られました。「日本書紀」によると、そのとき天照大神は「伊勢の国は、遠く常世から波が幾重にも打ち寄せる美しい国である。都から離れた傍国ではなるが、ここにいようと思う」とのご神託があり、倭姫命は、お言葉通り、五十鈴川の川上に宮を建てられました。これが二千年前にさかのぼる伊勢神宮の起源で、宝鏡(八咫鏡)は今も伊勢神宮に奉斎されています。
なお、現在、宮中には、伊勢神宮にある御神体(八咫鏡のこと)を象って作った代わりの鏡(ご分霊のことでレプリカと考えてよい)が伝えられ、現在も皇居にある宮中三殿の賢所にお祀りされています。天皇陛下は、この国の象徴として、宮中三殿にて年間20回以上の祭祀を執り行い、国民の繁栄と世界の平和を祈っていらっしゃいます。
このように、この天照大神を尊崇する神勅は、後に「宝鏡奉(ほうきょうほう)斎(さい)の神勅(宝鏡(ほうきょう)奉殿(ほうでん)の神勅)」と呼ばれるようになりました。日本各地の神社における神鏡(鏡を神霊として祀ること)の起源をここに求めることができます。同時に、私たちにも神祇(じんぎ)崇敬(すうけい)(神々を敬うこと)と崇(すう)祖(そ)(先祖を崇め奉ること)を教えてくれています。
第三の神勅:「斎庭(ゆにわ)の稲穂(いなほ)の神勅」
日本書記では、「宝鏡奉斎((ほうきょうほうさい)の神勅」の直後に、「斎庭(ゆにわ)の稲穂(いなほ)の神勅」(第3の神勅)と後に呼ばれる天孫降臨にかかる話しがさらに続きます。
吾が高天原に所御(きこしめ)す斎庭(ゆにわ)の穂(いなのほ)を以て、また吾が児(みこ)に御(まか)せまつるべし
高天原(天上の国)で育てられている神聖な田の稲穂を我が児(みこ)(=おさなご)に授けましょう。
天照大神は、ニニギノミコト(瓊瓊杵尊)に、(三種の神器とともに)人々が飢えないようにと稲穂を持たせました。天上界の田で育った清らかな稲穂を撒いて地上で稲作し、この国を天上界のような稔り豊かで安定した国にしなさいと、天照大神から託されたのです。これは民を飢えさせないで、民が安心して食べていくことができるように、この国を栄えさせなさいという思召しと解されます。
日本は昔から「豊(とよ)葦原(あしはら)瑞穂(のみずほ)国(くに)」といわれ、豊かな収穫の続く、みずみずしい稲のできるすばらしい国となったのでした。高天原でも稲を育てているのが日本の神話の独特なところです。天上で行われていることは、地上でも行われているのです。まさに写し鏡ですね。
「三大神勅」と記紀神話
以上、ここまでは天孫降臨にかかわる神話で、天照大神が地上(葦原(あしはらの)中国(なかつくに))に降りようとされるニニギノミコトに対して贈られた神勅(ご命令)を紹介しました。地上の葦原中国を治めることを命じた「天壌(てんじょう)無窮(むきゅう)の神勅」を第一の神勅、三種の神器の中の鏡をお祀りすることを求められた「宝鏡奉(ほうきょうほう)斎(さい)の神勅」が第二の神勅、稲穂を授けられた「斎庭(ゆにわ)の稲穂(いなほ)の神勅」を第三の神勅と呼ばれています。この3つの神勅は、後に三大神勅として、「神道の根本義」とまで言われるようになりました。
ただし、日本書記には、第一、第二、第三といった番号付けはありませんし、「宝鏡奉(ほうきょうほう)斎(さい)の神勅」(第二の神勅)、「斎庭(ゆにわ)の稲穂(いなほ)の神勅」(第三の神勅)は、一つの話しの中にまとめられています。ですから、「三大神勅」というのは、神道理論として、後世になって出てきた日本書記の解釈(理論付け)の一つで、神話の伝承を飛躍的に解釈し、政治的に利用された面もあると言えます。
実際、古事記には、三大神勅と命名されるような厳格な記載ではなく、天照大神が地上へ天降られるニニギノミコトに対して、まさに出発前に親が子どもを気遣うようなトーンで書かれているような気がします。例えば、日本書記の「第二の神勅」に相当する部分は古事記では、日本書記よりも短く、次のような記述になっています。
亦常世思兼神、手力男神、天石門別神を副へ賜ひて、詔りたまひけらく、「此れの鏡は、専ら我が御魂をして、吾が前を拝くが如(ごとく)伊(い)都(つ)岐(き)奉れ。次に思兼神は、前の事を取り持ちて、政(まつりごと)為よ」。
(現代語訳)
また、常世の国の思兼神(オモイカネ神)、手力男神(タヂカラオ神)、天石門別神(アメノイワトワケ神)を加えて、天照大神がおっしゃいました。「この鏡を、私(天照大神)の魂として私を拝むように祀りなさい。次に思兼神は、祭祀を取り持って、政治を行いなさい
なお、後半の「思兼神は、前の事を取り持ちて…」とは、天照大神を祀ることを取り持つ、すなわち、祭祀をなされるニニギノミコトをお支えし、政治を行いなさいと、天照大神はご命令されています。
ここに、日本は伝統的に、天皇の役割は祭祀で、政(まつりごと)の実務は、別の人が行っていたことが伺えます。ですから、天皇は神話の時代から独裁的に治められる存在ではなかったのです。実際、大国主神にもスクナヒコナ神という補佐役がいました。このように、私たちは、神話伝承からも、日本の統治スタイルをも拝察できるのです。
かくして、天照大神からお言葉(日本書記では神勅)と「三種の神器」、それに稲穂を賜ったニニギノミコト(迩迩芸命、瓊瓊杵尊)は、八百万(やおよろず)神を従えて、天上の高天原から、地上の葦原の中つ国へ向けて旅立ち、九州日向の高千穂の峰に天降られました。
地上の大地に降り立った天つ神の皇子(おうじ)、ニニギノミコト(瓊瓊杵尊)は、立派な宮殿を建てて、そこに住み、天孫が葦原中つ国を治める時代がいよいよ始まったのです。
◆ 記紀神話③
神武天皇誕生
天孫ニニギノミコト(瓊瓊杵尊/邇邇芸命)が地上に降りてからある時、海岸で、コノハナノサクヤヒメ(木花開耶姫/木花之咲夜姫)という名の女性に出会いました。咲夜姫は、日本の山を管理する大山津見(おおやまづみ)神(大山祇神)の娘です。
ニニギノミコトが咲夜姫に求婚すると父の大山津見神も喜び、ニニギノミコトと咲夜姫は結ばれました。これが、出雲神話に続いて、天界の神と地上界の者が結ばれた話しです。2人の間には、火照命(ホテリノミコト)(別名海幸彦)、火須勢理命(ホスセリノミコト)、火遠理命(ホヲリノミコト)またの名を彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)(別名山幸彦)の3人の御子が生れました。
このうち、山幸彦は、日本の海の管理者である綿津見神の娘(海神の娘)である豊玉姫と結婚し、男の子の鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)を持ちました。
鵜葺草葺不合命は、豊玉姫の妹で自分を育ててくれた玉依姫と結婚し、二人の間に五瀬命(いつせのみこと)、稲氷命(稲飯命)、御毛沼命(三毛入野命)、若御毛沼命(わかみけぬののみこと)という4人の子どもが生まれました。この4番目の若御毛沼命こそ、後の神武天皇となる人です。
このように、日本の初代天皇とされる神武天皇は、記紀伝承によれば、九州の日向(ひなか)の地で生まれました。初代天皇にご即位するまでは、名は、神倭伊波礼毘古命(神日本磐余彦天皇)(カムヤマトイワレヒコ)、ご幼名を狭野命といいました。記紀神話では天照大神の孫に当たる瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)の曾孫(そうそん)(ひまご)、天照大神から五代目の御孫にあたります。
以上、神武天皇の誕生までの日本の神話の一部を外観してきましたが、ここで、教育勅語の
第1文を改めて考えてみましょう。
◆ 神話から考える教育勅語
教育勅語 第1文
朕惟(おも)フニ 我(わ)カ皇祖皇宗國(くに)ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠ニ 徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ
朕(ちん)思うに わが皇祖皇宗 国を肇(はじ)むること宏遠に 徳を樹(た)つること深厚なり
本投稿の総タイトルである「教育勅語の冤罪をほどく」ための最初の試みは、教育勅語第1文の「皇祖皇宗」の解釈について明確にすることです。
皇祖皇宗の解釈
皇祖皇宗とは、皇室の祖先のことですが、皇宗は、神武天皇の後の第2代綏(すい)靖(ぜん)天皇以下の先代までの天皇を指すことで一致しています。しかし、皇祖は、始祖である天照大神までの神さまに遡るのか、神武(じんむ)天皇のことをいうのか諸説があります。
(神話を現実の歴史と捉える)神話的国体観(皇国史観)の立場に立てば、皇祖は天照大神またはニニギノミコトまで遡ります。実際、教育勅語の事実上の「公式解釈書(公定注釈書)」として扱われた井上哲次郎の「勅語衍(ちょくごえん)義(ぎ)」には、皇祖を天照大神の命を受けて地上に降臨したニニギノミコトまで遡っています。
太古の時に当り、瓊瓊杵命、天祖天照大神の詔を奉じ、降臨せられてより…
太古、ニニギノミコトが、天祖天照大神の詔を奉じて、降臨されてから…
これに対し、教育勅語を書いた井上毅による勅語衍(ちょくごえん)義(ぎ)の修正案では、皇祖を神武天皇としています。
神武天皇皇国を肇め民を治め、我が大日本帝国を定めたまへるの後…
神武天皇が、日本国を創り民を治め、我々の大日本帝国を定められたまへるの後…
井上毅が皇祖を神武天皇とした理由は、彼が教育勅語の草案作成にあたって示した起草七原則にあります。井上毅は、その七原則の2番目に「敬天尊神などの語を避ける。勅語には天とか神とかいう言葉は避けなければならない」としています。
「天」を敬うとか「神」を尊ぶとかいうような表現を避けるというのは、天皇のお言葉である勅語をめぐって、神学論争に発展することを恐れて、神代時代を言及することを避けるためでした。
また、七原則の最後に「ある宗旨が喜んだり、ある宗旨が怒ったりしないもの」とあります。これも皇祖を神武天皇とした要因として考えられます。神代までの遡ってしまえば、明らかに神道色が濃厚となり、当時、廃仏毀釈で打撃を受けた仏教界や、当初禁止されたキリスト教の人々からすれば、教育勅語は受け入れ難いものになったかもしれません。
教育勅語を書いた井上毅本人がそう言っているのですから、皇祖は神武天皇でしょう。したがって、教育勅語の第一文を「神代の神話を歴史と同一し、皇国史観の基本となった」とする批判は根底から覆ります。
もっとも、神武天皇も伝説上の人物との見方も一部にはありますが、少なくとも、天照大神の孫とされるニニギノミコトの天孫降臨の際の「天壌無窮の神勅」をもって、日本は神国であり、天皇は現人神である…という式の考え方を、執筆者の井上毅はしていなかったとみることは明らかです。つまり、教育勅語はその発刊直後から作者の趣旨が曲げられてしまったということが言えるでしょう。
なお、教育勅語のもう一人の執筆者(現在でいう監修者)である元田永孚が皇祖をどう捉えていたかを知りたいところですが、元田は教育勅語が世に出されてほどなく、他界され、その真意を知ることはできません。
いずれにしても、記紀の中には、教育勅語の第一文の理解にとって欠かすことができない内容が無数に散りばめられていたことは確かなことです。それだけ、教育勅語の第一文は奥が深いわけです。
そこで、前述した徳の意味(民衆のための国づくりである「しらす」による徳政)と、皇祖皇宗の皇宗の意味を踏まえて、この第一文を改めて解釈し直すと、次のような現代語訳ができるでしょう。そこには神話的国体観とか皇国史観という政治的な解釈は生じえないと思われます。
朕惟(おも)フニ 我(わ)カ皇祖皇宗國(くに)ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠ニ 徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ
朕(ちん)思うに わが皇祖皇宗 国を肇(はじ)むること宏遠に 徳を樹(た)つること深厚なり
(私訳)
天皇である私が思うに、神武天皇から始まる歴代の天皇が、国を開かれ、発展させてこられたことは、遥か昔に遡り、その間、祖神と民の心を知ろうとされる徳による政治が永きにわたり行われてきた。
(参考:文部省訳)
朕が思うに、我が御祖先の方々が国をお肇めになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられる。
<教育勅語 第2文>
我(わ)カ臣民 克(よ)ク忠ニ克ク孝ニ 億兆心ヲ一(いつ)ニシテ 世世(よよ)厥(そ)ノ美ヲ濟(な)セルハ 此(こ)レ我カ國體(こくたい)ノ精華ニシテ 教育ノ淵源(えんげん)亦(また)實(じつ)ニ此(ここ)ニ存(そん)ス
わが臣民 よく忠によく孝に 億兆こころを一(いつ)にして 世世(よよ)その美を濟(な)せるは これわが国体の精華にして 教育の淵源(えんげん)また実にここに存(そん)ス
(文部省訳)
また、わが臣民はよく忠に励み、よく孝をつくし、国中のすべての者が、皆心を一つにして、代々美風をつくりあげてきた。これはわが国体の真髄であり、教育の基づくところもまたここにある。
臣民(しんみん):君主国(明治憲法下の日本)の国民
克(よ)ク:能力を発揮して成し遂げることで、 「能く」と同じ。
億兆(おくちょう):万民。全ての国民。限りなく大きな数。
國體(国体):国家としての固有の体制(性格)、天皇を中心とした政体
精華(せいか):そのものの真価をなす、立派な点、真髄
淵源(えんげん):物事の拠(よ)って立つ根源
本投稿では、第一文の解説が膨大な量に及んだため、第一文を文字通り、一つの文章とみなして解説しました。辞書的な訳文なら問題ありませんが、教育勅語の含蓄ある意味を理解しようとするなら、この第2文を独立した内容と考えると全体の意味を取り違えてしまうおそれがあります。
実際、第2文は、第1文と対にして考えなといけません。というのも、教育勅語を書いた井上毅は、「我が臣民克(よ)く忠に克(よ)く孝に億兆心を一にして…」と「我が臣民」に始まる一文と、前の「皇祖皇宗、国を肇(はじ)むること…徳を樹(た)つること深厚なり」の一文が「対股(むきあい)文」であると説明しています。
どういうことかと言うと、「徳を樹(た)つること深厚なり」の皇祖皇宗の「徳」と、第2文の臣民の「忠孝」が対になっているということです。歴代の天皇は、記紀にもあった「皇祖の御心の鏡もて天が下の民をしろしめす(神々のみ心を鏡に映し出すように、民の心を知りながら民を治める)」精神を守り、天皇は臣民に対して「しらす」という徳の政治を実践されてきました。その一方で、それに呼応するかのように、民もまた心を一つにして、代々、忠孝に勤めるという美風を育ててきたと、第2文では述べているのです。
「世世(よよ)厥(そ)の美(び)を濟(な)せるは」の部分についても、文部省訳は「代々美風を作り上げてきた」としていましたが、「美をなす」というと、中国の論語に「人の美をなす(人のよい所を助け導き、成し遂げさせる)」という言い方があります。ここから、万民が「互いに美点を見出し合いながら育て上げてきた、互いに高めあってきた」という意味も込められていると推察されます。
したがって、第2文は、言外のことばを補って解釈すると次のように現代訳できると思います。
わが臣民 よく忠によく孝に 億兆こころを一(いつ)にして 世世(よよ)その美を濟(な)せるは…
(歴代の天皇が臣民に徳を与えてこられたように)わが民も、よく忠に励み、よく孝を尽くし、皆が心を一つにして、代々その(忠孝の)美風を作り上げてきた・…
…これわが国体の精華にして 教育の淵源(えんげん)また実にここに存(そん)ス
これ(天皇は臣民に対して徳を、民もまた忠孝に励んできたという「君民同治」の姿勢)が、日本という国体の精華(国柄のすばらしさ)となっているのであって、教育の淵源(基本)もまさしくこの点にある
さらに、ここで使われている「国体」は、万世一系の天皇制国家というような政治的イデオロギーではなく、文化的民俗的な意味の国柄を指すと言えます。この点からも、第1文と第2文は、天皇と臣民両者の徳について書かれていることがわかります。
このように、教育勅語の第1段落(第1文と第2文)は、とりわけ、神話と歴史の深い理解に支えられた明治の賢人、井上毅と元田永孚の英知の結集であり、字面(字づら)の表面的な理解で批判することはできない含蓄のある内容でした。
★☆★☆★☆★☆
では、改めて、第1文と第2文(第一段落と解される)が対になっていることを念頭において、文部省訳を補いながら現代語訳を試みてみました。
朕惟(おも)フニ 我(わ)カ皇祖皇宗國(くに)ヲ肇(はじ)ムルコト宏遠ニ 徳ヲ樹(た)ツルコト深厚ナリ 我(わ)カ臣民 克(よ)ク忠ニ克ク孝ニ 億兆心ヲ一(いつ)ニシテ 世世(よよ)厥(そ)ノ美ヲ濟(な)セルハ 此(こ)レ我カ國體(こくたい)ノ精華ニシテ 教育ノ淵源(えんげん)亦(また)實(じつ)ニ此(ここ)ニ存(そん)ス
朕(ちん)思うに わが皇祖皇宗 国を肇(はじ)むること宏遠に 徳を樹(た)つること深厚なり わが臣民 よく忠によく孝に 億兆こころを一(いつ)にして 世世(よよ)その美を濟(な)せるは これわが国体の精華にして 教育の淵源(えんげん)また実にここに存(そん)ス
(私訳)
天皇である私が思うに、神武天皇から始まる歴代の天皇が、国を開かれ、発展させてこられたことは、遥か昔に遡り、その間、祖神と民の心を知ろうとされる徳による政治が永きにわたり行われてきた。また、(歴代の天皇が臣民に徳を積んでこられたように)わが民も、よく忠に励み、よく孝を尽くし、皆が心を一つにして、代々その(忠孝の)美風を作り上げてきた。これ(天皇は臣民に対して徳を積み、民もまた忠孝に励んできたこと)は、わが国体の精華(国柄のすばらしさ)であり、教育の根本もこの点にある。
(参考:文部省訳)
朕が思うに、我が御祖先の方々が国をお肇めになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられ、また、わが臣民はよく忠に励み、よく孝をつくし、国中のすべての者が、皆心を一つにして、代々美風をつくりあげてきた。これはわが国体の真髄であり、教育の基づくところもまたここにある。
<参照>
神話が教えるホントの教育勅語
教育勅語②:近代史からわかる義勇公の精神
教育勅語③:日本書記が明かす八紘一宇の真実
他の「タブーに挑む」シリーズ
<参考>
「明治期における政治・宗教・教育」(福島清紀)
「教育勅語の成立と展開」(所功 京産大法学44巻4号)
「近現代教育史のなかの教育勅語 ─研究成果の検討と課題─」(貝塚茂樹)
「近代以降日本道徳教育史の研究」(千葉昌弘)
「戦後教育はこうして始まった」(日本政策教育センター)
「明治後期における公教育体制の動揺と再編」(窪田祥宏)
「教育勅語の真実」(致知出版社/伊藤哲夫氏著)
(2022年12月7日)