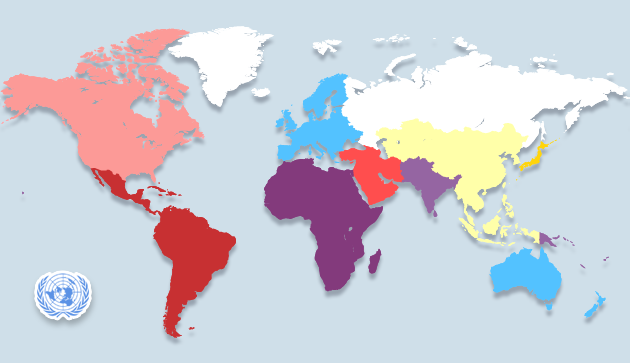三笠宮家「内紛」の結果・・・
三笠宮家は、2024年11月に三笠宮妃百合子さまが101歳で薨去されてから、当主が不在となっていたなか、2025年9月30日、「*皇室経済会議」(議長・石破茂首相)が、宮内庁の特別会議室で開かれ、以下の2つの決定がなされました。
(1) 空席となっていた三笠宮家の当主について、孫の(あきこ)さま(彬子女王)が継がれること
(2) 彬子さまの母で、百合子さまの長男・寛仁親王妃・信子さまが、三笠宮家を離れ、独立して新たな宮家『三笠宮寛仁親王妃家(みかさのみや・ともひとしんのうひ・け)』を創設し、その宮家の当主となられること
これによって三笠宮家は、母娘で分断した形となりました。なお、彬子さまの妹の瑶子(ようこ)女王(41)は、姉が当主となる三笠宮家にそのまま残られます。
◆ 三笠宮家当主を彬子女王が継承
彬子さまは、三笠宮崇仁 (たかひと) 親王の長男で、「ヒゲの殿下」と親しまれた三笠宮寛仁(ともひと)親王の長女です。大正天皇の曾孫で、現在の天皇から見て「祖父の弟の孫である女王」ということになり、一般人なら「はとこ」「またいとこ」という関係性があります。
女性皇族が当主となるのは、当主を亡くした妃(きさき)が継ぐというのが通例です。実際、戦後の皇室では、高円宮妃だけでなく、秩父宮妃、高松宮妃、高円宮妃、三笠宮妃が、夫の宮さまがお亡くなりになったのち、臨時で当主になられています。
しかし、彬子さまのように、未婚(宮家で夫を亡くした妻以外)の女性皇族が、当主を継承するのは、明治憲法下の1889年に旧皇室典範が制定されて以降、今回は初めてです。
江戸時代にまで遡れば、仁孝天皇(在位1817〜1846)の第三皇女で、桂宮淑子(すみこ)内親王以来163年ぶりのことです。淑子内親王は、桂宮家を継いだ別の弟が亡くなり、当主不在となったことから、1863年に (旧) 桂宮家の第12代当主となりました。
宮家の継承とは祭祀を継ぐことを意味します。宮家当主(一般人でいう「世帯主」)は、法的な概念ではありませんが、その家の代表として祭祀を執り行う役割があります。今回の決定により、彬子女王は、独立生計を営む皇族と認定され、三笠宮家の当主として正式に宮家の名称と、その祭祀を「継承」されました。
もっとも、彬子さまはすでに、三笠宮ご夫妻(崇仁親王と百合子妃)と子の寛仁親王の祭祀を執り行っており、今回の決定で、その立場が法律に明文化された形です。さらに母の信子さまが独立したことで、彬子さまが、名実ともに「三笠宮家」を継ぐ存在となられました。
◆ 信子妃が独立し宮家を創設
今回、三笠宮家から独立した信子さまは、独立生計認定を受け、新たな宮家(三笠宮寛仁親王妃家)の当主となりましたが、信子妃のように結婚により民間から皇室に入った女性(皇族妃)が新たに家を創設するのは、明治時代の旧皇室典範施行(明治22年)以来、これも例のない初めてのことです。しかも、「親王妃家」という、まったく前例のない制度がつくられたわけです。
そもそも「三笠宮寛仁親王」という皇族は、現在存在していません。崇仁親王(三笠宮)の長男、「寛仁(ともひと)親王」は、生前、いずれ「三笠宮家」を継ぐことを考え、「寛仁親王家」という宮家を名乗られていました。したがって、「三笠宮寛仁親王妃家」という名称は、「三笠宮家から出た寛仁親王妃の家」という異例の構成となったのです。
ですから、厳密にいえば、信子妃殿下の新宮家、「三笠宮寛仁親王妃家」は、三笠宮家の分家であり、全く新しい宮家ではありません。新しい宮家であれば、天皇陛下から、秋篠宮や高円宮(たかまどのみや)のように「◯◯宮」という「宮号」を賜わりますが、宮内庁は、宮号はないと明らかにしています。
いずれにしても、新たな宮家ができるのは、1990年に秋篠宮家が創設されて以来35年ぶりのことです。これによって、これまで総数として「4宮家」(秋篠宮、常陸宮、三笠宮、高円宮)といっていたのが、これからは「5宮家」になります。
◆ 増額される皇族費
宮家において、誰が当主になるかは原則、家族の話し合いで決まり、その結論が皇室経済会議に諮られます。皇室経済会議が開かれる理由は、会議で独立生計者(当主)と認定され、宮家の当主になると国(国庫)から支払われる皇族費が増額されるためです。皇族費は身位や「当主かどうか」などに応じて、皇室経済法等に基づいて計算式が定められています。
今回の決定によって年間で支給される皇族費は、以下のように、彬子さまと信子さまは増額され、当主になられなかった瑶子さまは、これまでと同じ支給額となりました。
母・信子親王妃:1525万円⇒3050万円
姉・彬子女王:640.5万円⇒1067.5万円
妹・瑶子女王:640.5万円(変わらず)
もし、三笠宮家だけで存続する場合、すなわち、順当に信子妃が当主に就かれ、彬子さま・瑶子さまがその家の成員となった場合、3人に支払われる皇族費は計4331万円でしたが、今回は新当主が2人誕生することで計4758万円となり、427万円の増額となりました。
皇室経済会議の決定に対する国民の声
今回、7年ぶりに開催された皇室経済会議では、意見や質問はなく10分ほどで終了し、全員一致で、信子さまと彬子さまの独立生計を認定しました。
今回の決定をめぐっては、ご一家のこれまでの事情に鑑みれば、「やむを得なかった」という意見もありますが、「物価高で貧困が増えてるのに皇族に支払われる額は倍増し、国民の負担が増えることに、国民の理解は得られない」、「継がれる当主が決まったのはいいが、ご一家がひとつにまとまるのが通例、そもそも新しい宮家が必要なのか」といった声が聞かれました。
なかには、「親王妃家という前例のない宮家を立てるぐらいなら、信子妃は本来、皇籍離脱するのが筋であろう」、「寬仁親王(2012年死去)の生前から夫婦は事実上、離婚状態にあったのだから、皇族妃という立場を放棄すべきである」との厳しい意見も出されていました。
一連の決定について宮内庁側は、「宮家で話し合われた結果」、「内輪の話。承知していないし、承知したとしても説明を差し控える」と言うのみで、一世代飛ばして信子さまの長女彬子さまが継いだ理由や、信子さまが三笠宮家を離れた、具体的な理由については説明していません。
このように、彬子女王の宮家継承と信子妃の新宮家創設は、明治以降の皇室では前例のない「初めて尽くし」となり、結果的に、三笠宮家は分裂(分断)してしまいました。
こうなってしまった背景には、20年以上にも及ぶ、三笠宮家内における夫婦間の葛藤と、母娘の確執がありました・・・。
三笠宮家内の問題から、今回の決定が与える影響まで、続きは、以下の投稿議事を参照下さい。