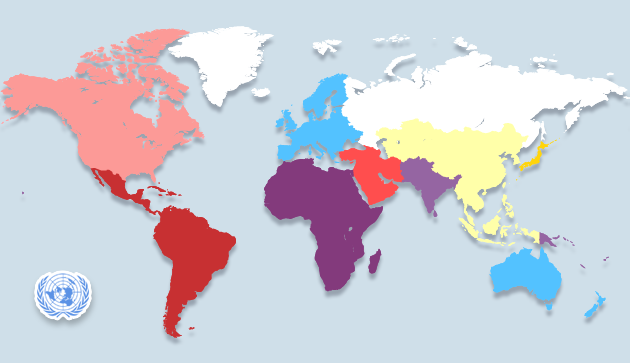鈴木農相、減反への巧妙な言い分と「おこめ券」のわな
コメ価格が高止まりを続けています。高市政権になり、新しい農林水産大臣には、自民党の鈴木憲和衆院議員が就任しました。新大臣の就任会見、その後の発言を聞くと、コメ価格は下がらないまま、日本の農業はますます衰退、高市政権の経済運営にも影響を及ぼすことが懸念されます。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
◆ 鈴木大臣ってどんな人?
鈴木大臣は、2005年に農水省に入省、2012年に退官した後、同年の衆院選で初当選しました。選挙区は コメどころの山形県(本人は東京都出身)で、農協の全面的バックアップを受けて議員となった自民党農水族です。
「農政のトライアングル」という用語があります。これは、農林水産省、自民党の農林族議員(省庁に顔の利く国会議員)、JA農協の3者で形成する癒着に近い権力構造のことで、戦後の農政は、この「農政のトライアングル」によって主導されてきました。
鈴木大臣は、一見すれば、農水官僚、自民党農林族、農協の期待を一身に担った農林水産大臣ということになります。
◆ 鈴木大臣の発言を斬る!
そんな鈴木大臣のコメ政策に関する方針としては、就任会見等で明らかにした、➀「需要に応じた生産」、②「価格はマーケットで決まる」、③おコメ券の配布の3点がキーワードになりそうです。大臣の発言を紐解きながら、その真意を探ります。
➀「需要に応じた生産が基本」
就任会見で、鈴木大臣は、コメ政策に関して次のように発言しました。
需要に応じた生産が基本…需要がないのに生産量を増やせば米価が下がる。生産者の設備投資や人件費を考えても、価格の安定が不可欠。無責任に増産を続けるのは難しい…
「(少ない)需要に応じた生産が基本」で「増産を続けるのは難しい」とは、「生産調整」が行われる、つまり実質的な減反政策に後戻りしたことを意味します。現に「無責任」という言葉を使って、前任の石破総理がコメ対策として掲げた増産路線を批判し、事実上、これを撤回した形です。
これは、「農政のトライアングル」の規定路線に戻ったことを意味します。そうすると、鈴木大臣が目指す「価格の安定が不可欠」の「価格の安定」とは、今回のコメ騒動が起こる前の水準での安定ではなく、急騰した「高値での安定」を示唆しています。コメ価格は、令和のコメ騒動以前の5キロ=2000円台はおろか、小泉前農相が目標とした3000円台に下がることはないかもしれません。
そもそも、経済の原則として、価格は、「需要=供給(生産)」で決まります。鈴木農相は「需要がないのに…」と認識していることから、本来、市場(マーケット)に委ねれば、「需要<供給」でコメ価格は下がりますが、「需要に応じた生産」と言って、生産(供給)を落とすことで、現在の高い米価を維持しようとしているのです。
このように、鈴木農相のいう「需要に応じた生産」とは、特定の望ましい価格を実現するために、それに対応する需要量まで、コメを減産すると言っているようなもので、今の高い米価を下げる意思のないことを表明しています。しかも、大臣は、その理由を「価格の安定が不可欠」だからだと言ってごまかしています。
減反政策を継続
近年の主食用米の年間生産量(主食用米の収穫量)は、概ね600万トン台後半から700万トン台前半で推移しています。
2023年産:662万トン
2024年産:679万トン
2025年産:748万トン(予想収穫量)
2026年度:711万トン(生産見通し)
2025年産の主食用米の収穫量は、2024年産を約69万トン上回る748万トンと見込まれていました。これは、「令和のコメ騒動」でコメ価格の高騰により、農家の生産意欲が高まったことや、作付面積の拡大などがあげられています。
しかし、2026年産向けの生産目安は、需給緩和を見越して、711万トンと提示され、2025年産よりも減産となる見通しです。
農水省は、減反政策は既に廃止されたと言いながら、コメの生産目安の設定や助成金を通じた生産調整で、実質的に減反政策を継続させています。しかも今回は、「需要に見合う生産」という原則をたてに推し進めようとしています。
さらに、備蓄米の水準を回復するという名目で、放出した備蓄米59万トンを買い戻し、市場から「隔離」するそうなので、供給量はさらに減少します。結果、コメの値段は下がらないどころか、いっそう上がることも懸念されます。
需要の見積もりは正しいのか?
加えて、鈴木大臣が「需要に応じた生産」と言うときの「需要」は、果たして正しい数値なのかという疑問も生じます。「国の需給計画上の数字」が必ずしも正しい需要を表すとは限りません。実際、「令和のコメ騒動」のさなか、「23~24年の数字は誤りだった」として、国は謝罪しています。この需要の見積もりミスが令和のコメ騒動の一員となりました。
また、鈴木大臣は、会見で「現状では不足感は解消されたと認識している」と断言しましたが、この認識が正しいのでしょうか?
ある識者によれば、集荷業者らは、2025年もコメ不足が解消しないと見て、田植えよりずっと早い3月頃から、集荷競争を繰り広げ、農家との間では秋の新米の契約をかなりの高値で進みだしていたそうです。これが、現在もコメ価格が高い理由の一つです。
また、大臣の会見では、「需給見通しを精度の高いものに」と言っていましたが、かつて、当時食糧庁のある幹部の方は、「国がコメ需給をぴたりと合わそうなどとは、神をも恐れぬ所業である」と言われたことがあるそうです。
そう、需要を正確に把握し、生産に反映させることができるのは、「神」しかいません。ただし、ここでいう神とは、近代経済学の祖、アダム・スミスで有名な「神の見えざる手」、つまり「市場」です。
需要とは、「市場が価格を通じて生産者に知らせる」もので、生産者は市場で形成された価格シグナルを通じて必要な量を知り、生産活動を行います。真の需要は、市場の価格動向等を通じて把握する以外に方法はありません。
いみじくも、鈴木農相は、「価格はマーケットで決まるものだ」と発言しており、このことを理解されているのかと思いましたが、「マーケット(市場)」の使い方を歪曲しているようです。
② 「価格はマーケットで決まるものだ」
適正な価格についての質問に対し鈴木農水大臣は、次のように答えました。
何円台がいいとは言わない、(米価について)私のスタンスとして、高いとか安いとかは申し上げない。価格はマーケットで決まるものだ。
これは、5月から備蓄米放出による価格引き下げを進めてきた政府の方針を改め、今後は価格のコントロールに関与しない姿勢を示したことになります(政府の価格介入を否定)。
また、あるテレビ番組に出演した鈴木農水相は、コメの値段を「せめて(5キロ)4000円台に」という消費者の声に対し、次のようにも回答しています。
…残念ながら価格というのは、私たちにコントロールする権限が全くないし、私たちが管理をしてるものでは…、残念ながらコメは…流通の世界は自由でありますから…
コメの流通市場は自由なので、農水省は米価を管理する権限は全くない(=農水省は米価をコントロールしてはいけない)と述べているのです。
しかし、「価格に関与しない」と言いながら、「需要に応じた生産」と言って、生産抑制(今年産から5%減少)を指示していること自体、米価の高止まりを望む価格への介入です。
マーケットの機能を阻害
そもそも、鈴木大臣が「価格はマーケットで決まるものだ」という時のマーケット(市場)とは、本来、不特定多数の買い手と売り手が集える、公開・公正で、調整機能が十分に発揮されており、さらに行政もそれを側面から支援している市場です。
しかし、適正価格を形成、市場のメカニズムの働きを意図的に阻害し、価格形成に関与しようとして、適切なコメ市場の形成を阻止してきたのが、ほかならぬ、鈴木大臣ご出身の農林水産省とJA農協です。
農政の歴史を振り返ると、「農政のトライアングル」(農水省、JA農協、自民党)は、1960年代から、農家を守るという名目で、減反政策によって、米価を上げてきました。
具体的には、生産者に毎年3500億円ほどの減反補助金を出して、コメ生産を減少させ(農業用地を減らさせる)、コメの値段を市場で決まる価格よりも高くしてきたのです。
「令和のコメ騒動」前の5キロ=2000円台だった米価も、マーケット(の需給関係)の中で決められたのではなく、強力な市場介入の結果で、価格を市場(マーケットの力)に委ねていたら、コメの値段は5キロ=2000円台をさらに下回っていたはずです。
それが「令和のコメ騒動」が発生し、農水省や農協からすれば、米価が上がり出したのはよかったのですが、農水省が需給を読み間違えたことから、騒動前の2倍以上の水準に、上がり過ぎてしまい大問題となってしまいました。これが今回の「騒動」の実態です。
しかし、農水省は、これまで米価をマーケット(市場)に委ねてこなかったどころか、その働きを阻害してきたにもかかわらず、「価格はマーケットが決めるものだから、米価には関与しない」という鈴木大臣の発言は、農水大臣としては「不誠実」であり、もはや「偽善」の域に達しています。
日本にはないコメの自由市場
加えて、コメの流通プロセスにおいて、日本には自由な売買の場である卸売市場のように公的な「取引所」は存在していません。
代わりに、日本では集荷業者(売り手)と卸売業者(買い手)が、直接「話し合い」によって価格を決定する相対(あいたい)取引が取引量の大半を占めています。このため、一般にニュースで報じられる「米価」は、卸売段階の取引価格(相対取引価格)を指す場合が多く、これが日本でのコメの基準価格となっています。
もっとも、政府(農水省)は、かつて、相対取引における、公設の場として、「全国米穀(コメ)取引・価格形成センター」を創設し、コメ取引に市場原理を導入しようとしました。しかし、相対価格を有利に決めたいJA農協が業者の上場(取引所で売買すること)を制限するようになって、結局センターは廃止されてしました。
また、コメの適正価格の形成になくてはならない先物市場も、JA農協の反対運動により「実質的」に認められていません。需給で公正に価格が決定される市場が実現できれば、JA農協は、自分たちにとって適正な相対価格を決めることはできなくなるからです。日本には、各銘柄米の値段を自由な売買で決める市場がJA農協の反対とこれを認めた農水省によって存在していないのです。
このことは裏を返せば、現在の相対価格は、需給で公正に価格が決定される水準ではないということでもあります。実際、相対価格は、JA農協が決定する概算金に大きな影響を受けます。
概算金とは、コメ価格形成に重要かつ独特な価格体系で、JA農協がその年の秋の収穫後に、農家に一時金として、支払われる仮払金をいいます。相対価格は、この概算金に、保管・運送・検査コストなどの流通経費や手数料などを上乗せしたものとなることから、JA農協が決定する概算金が、相対価格の水準をほぼ決定すると言っても過言ではありません。
ちなみに、JA農協が農家に払う概算金は、玄米60キログラム当たり通常の年では約1万2000円水準であるのに対して、2025年度産のコメの概算金は、主力銘柄で1等米60kgあたり2万6000円~3万3000円程度が中心で、前年産比では6~8割高と大幅に引き上げられています。
さらに、JA農協は、この高い米価(概算金)以上の価格を農家に払えない他の流通業者を、コメの集荷事業から排除しながら、市場の独占力を今も保持しています。
したがって、農水省が米価をコントロールできない理由に、鈴木大臣があげた「流通の世界は自由であるから」という主張は事実に反しますし、農水省は、できないどころか、コメの値段をコントロールしています。
日本では、市場メカニズムが機能して適正価格を形成できるマーケットは存在しないので、鈴木農相の「価格はマーケット(市場)で決まるものだ」は、「価格は、JA農協主導の相対取引で決まるものだ」と言っていることに等しいわけです。
コメの流通市場についての詳細については「コメの価格が決まる仕組み」を参照下さい。
元から、コメ価格を下げる気はない
結局、鈴木大臣の「需要に応じた生産が基本」、「価格はマーケットで決まるものだ」という発言は、今後も生産調整を続け、コメの高価格政策を続ける(高い米価を維持していく)と言っているのです。米価5キロ=4000円以上を、既成事実として、消費者に受け入れさせたいという鈴木大臣の真意が透けて見えます。
ただし、それでは、消費が困るというので、高い米価を受け入れてもらう代わりに、農水大臣がコメ高対策として打ち出しているのが、「おこめ券」の配布です。
③「おこめ券」の配布
鈴木農水大臣は、コメの高値が続くなか、「政府に今すぐできることは実際に消費者の皆さんの負担感を和らげる」ことして、おこめ券の配布を、物価高対策として、表明しました。
おこめ券とは?
政府は、自治体向けの「重点支援地方交付金」に2兆円を計上し、うち4000億円を食料品高騰に対応する特別枠として、おこめ券などの活用を促します。支援額は1人当たり3000円程度になる予定です。
農水省は、「おこめ券」の配布を各自治体に推奨していますが、実際に配布するかどうか、また、配布するにしても、誰を対象にするかは各自治体の判断に委ねられています。後者の場合、 たとえば、子育て世帯や低所得者世帯など、特定の対象者に限定して配布する場合もあります。
自治体から配布される「おこめ券」は、金券と同じで、特定のコメとの引換券ではありません。コメ500円/kgとされ、高いおコメを買えば、差額を負担する必要があります。
また、おこめ券以外に電子クーポンやプレミアム商品券、地域ポイントの配布、パン、麺、パスタなどの食料品の現物給付なども選べます(そうなると、おこめ券は石破茂内閣時代に検討された現金給付政策と何ら違いがないとの指摘もなされている)。
では、おこめ券は、本当に消費者の負担が和らぎ、物価対策になるのでしょうか?
おこめ券の効果
鈴木大臣は、おコメ券の配布を「国民の負担を和らげるため」の救済策と述べています。実際、おこめ券が配布され、今、たとえば、コメ500円/kgのおこめ券4枚を持つ消費者にとって、5キログラム当たり4200円のコメが、2200円で買えたことになります。
たしかに、おこめ券でコメを安くで買えて「助かった」と喜ばれるかもしれませんが、そもそも、これまで多額の減反補助金を通して、私たちは高いコメを長年、買わされて(負担を強いられて)きたという事実を忘れてはなりません。今回のおこめ券にかかる費用も財源は税金です。減反もおこめ券も負担するのは国民なのです。
また、おこめ券を使って、5キロ4200円のコメを買う人が増えるということは、需要の増加に伴い価格がさらに上昇し、消費者の負担も増えることにもつながりかねません。
しかも、おこめ券は、原則として1回限りの時限的な措置で、継続される政策ではありませんので、経済効果は限定的で、気休め程度です。したがって、物価高騰対策としてのおこめ券の配布は、一時しのぎになるだけで適切とは言えません。
うがった見方をすれば、国民に安くコメを買えると思わせて、下がらないコメの価格に対する不満を避けるための対策にみえてしまいます。
鈴木大臣と農水省の深慮
逆に、農水省の立場からいえば、おこめ券の配布によって、消費者に安くコメを供給することで、高い米価による需要の減少を抑制できる効果が期待できます。また、現在、高騰した新米は売れずに行き場を失い、JAや中間業者の倉庫は山積みになっていると言われていますが、おこめ券はそれらをさばくための対策になります。
そうすると、物価高対策としてのおこめ券は、米価を下げるのではなく、現在の高いコメの価格を維持しようとする鈴木大臣の目論見ではなかったのかとの疑いももたれます。
おこめ券の配布は、政府がコメを買い上げて配給するのとほぼ同じ構造であり、結果として、米価は高い水準のまま、コメ消費を無理に押し上げ、米価をさらに引き上げることにもなりかねません。
さらに、鈴木農相は、おこめ券に期限をつけると発表しましたが、これは、期限切れ後には市民が割高な米を購入せざるを得なくなるということを意味しています。
一方、おこめ券は、経費率が10%以上と高いことが指摘されています。具体的には、1枚500円のおこめ券では、440円分の コメしか買えず、差額の60円は印刷代、郵送、銀行振込みなどの費用として消えていきます。
大阪府交野市は、この経費率の高さなどを問題視し、おこめ券を「配布しない」と宣言しました。市長は、経費率0%の給食無償化、経費率1%の上下水道基本料金免除に使うとしています。
これに対して、鈴木農相は「おこめ券を使うか、使わないかは自治体の自由だ」とする一方で、「おこめ券の配布を含む食料品価格高騰対策は、市区町村に対応いただきたい『必須項目』として基本的には位置づけをされている」として、市区町村に対し事実上強制して実施してもらう考えを示しています。
今回の重点支援交付金のような交付金は本来、自治体が使い道を自由に決められるもので、国から自治体に交付金の利用を強制する権限はありませんが、全1741市区町村に対して対応を求めています。自身肝いりの「おこめ券」配布に、鈴木大臣の並々ならぬ意気込みが感じられます。
おこめ券の配布は、国民の負担を和らげるためになされると鈴木大臣は言いつつも、国民の負担(税金)で発行され、農家の収入を減らさずに、高い米価を維持するための政策手段となっています。
しかも、その恩恵を一番受けるのは、発行元である全農などの農業団体というカラクリがあります。
実際、「おこめ券」は、JA全農(全国農業協同組合連合会)と全米販(全国米穀販売事業共済協同組合)の2団体(それぞれ集荷業者と卸売業者の全国団体)が発行し、億単位の利益が転がり込むとされ、おこめ券の配布は、これを発行する農業団体への利益誘導との批判が噴出しています。
このように、付け焼き刃的なおこめ券の配布は、コメの高止まりを放置し、結果的に国民負担を増やすだけで、コメ問題の本質的な解決にはなりません。
◆ コメ問題の本質的な解決のために
令和のコメ騒動を含めた、すべてのコメ問題の元凶が、減反政策です。減反政策を止めなければ何も変わらず、コメ騒動は、政府が増産を後押ししなければ収まらないでしょう。
消費者にとっては減反廃止(増産)で、コメの値段が下がり、安い米が届くようになります。また、収穫量が増え、国内消費で余った分は、輸出に回せば、農家の所得を押しあげることができます。
もちろん、短期間に簡単に輸出を大幅に増やせるわけはないので、増産したら農家は潰れてしまうという指摘もあります。そのための対策として、米価下落の影響を受けた主業農家に対しては、財政出動による政府から直接支払いを交付する所得補填政策が最も効果的で確実とされています。
財源はどうする?という問いについては、専門家によれば、主業農家への直接支払いは1500億円と見積もられていますが、これまでの減反政策で、国民は納税者として、減反補助金3500億円を負担しているとされていることから、問題はないどころか、財政を好転させることもできます。
なお、コメ輸出の拡大については、以前の政権からずっと言われ続けた政策ですが、鈴木大臣も、所信表明演説で、コメ需要の拡大へ海外マーケットの開拓に意欲を表明しました。「私たちが認識を改めたほうがいいのは、今まで日本のコメは高くて海外に売ることができなかったという理屈だ」と述べ、日本産米の高付加価値を武器に輸出を拡大できる可能性を強調しました。
しかし、この発言も、高いコメを前提にしているところが問題です。減反政策をやめて、コメの価格が下がれば、もともと付加価値の高い日本の米を、安く海外に販売できるので、輸出を当然増えていきます。
石破政権では、この減反政策を名実ともやめて、増産に転じるという歴史的な決定を下しましたが、高市政権になって鈴木農相がすぐに撤回、減反(生産抑制)に回帰してしまったことはすでに指摘した通りです。
◆ このまま減反政策を続けたら…
では、政府がこのまま増産に舵を切らず、長年の減反政策を実質的に続けたいったらどなるでしょうか?
コメ農家が5年以内に全滅する!?
「コメの生産現場は、高齢化し、担い手を失い、困窮しきっている」という農家の疲弊が指摘されて久しいですが、こうなった原因は、今の農政にあります。
農家の平均年齢は70歳とされ、地域によっては「あと5年で米を作る人がいなくなる」と言われており、日本のコメ農家は、5年以内に激減し、多くの農村コミュニティが壊滅しかねません。長年の生産調整で、生産を減らせと言われれば、意欲のある若い担い手も育つわけはありません。
コメの自給率が下がる
このまま、高い米価が維持されれば、消費者のコメ離れすすむか、安い外国産の需要が増え(輸入米が増え)、現在95%近いコメの自給率さえ下げてしまいます。
実際、コメ不足が解消しないなら、輸入米でまかなえばよいという安易な主張がなされ、トランプ関税との絡みで、アメリカ産米の輸入が増えました。これは、稲作農家はさらに追い詰められて、やめる農家が続出することが懸念されます。
食料安全保障に悪影響
コメの自給率の低下は、食料安全保障に深刻な影響を与えます。現在の備蓄はおよそ100万トンとされ、これでは国民が食べられるのは、わずか1.5カ月分しかありません。
令和の米騒動では、日本はアメリカからの輸入米に頼りました。そもそも日本は多くの農産物を海外からの輸入に依存しています。主食である米まで輸入頼みになれば、もし供給が途絶えたとき、国民はたちまち飢えることになります。
安全保障環境が悪化しているなか、いまこそ、少なくともコメの備蓄を増やさないといけない時代背景があるにもかかわらず、目先の利益と既得権の維持に捉われて、減反政策を再び採用しようとしているのが鈴木農政です。
また、何より、農相から農業政策の大きなビジョンが示されていないことも問題です。おこめ券の配布に苦心するよりも、私たちが安心して食生活が営めるための農政の方向性をしっかりと示してもらいたいと思います。
自給率と食糧安保については以下の投稿記事も参照下さい。
◆ 高市政権の経済運営への影響
ここ数年、物価対策が最重要課題だとして、対策が求められていますが、昨今の物価高の象徴が食料品のなかのコメ価格で、消費者を最も苦しめています。
これに対して、鈴木農相はコメの高価格・減反路線を復帰させましたが、米価が下がらなければ、高市政権の物価高対策は、仮に食料品の消費税をゼロにしても、米価が高値を維持する限り、失敗する恐れがあると指摘されています。
そこで、物価高対策として、繰り返しますが、減反を止め、増産に切り替えることが望まれます。その結果、農家の所得が落ち込めば、農家への所得補償(直接払い)という形で、財政出動させるべきです。
高市首相は「積極財政」を掲げ、「日本が今行うべきことは、行き過ぎた緊縮財政により国力を衰退させることではなく、積極財政により国力を強くすることだ」と訴えました。
積極財政で、おカネを回すべきは、ここまで疲弊した農業に対してであり、コメの増産で国力を蓄えなければなりません。
もう何年も、農林水産省は、国民のために仕事をせずに、JA農協をはじめとする農政トライアングル(自民党内の族議員と、自民党の支持母体JA農協)の既得権のために仕事をしていると言われても否定できません。結果的にここまで日本の農業を疲弊させたのは、農水省の農政が間違っていたからです。
高市政権の経済運営の成功は、農政にかかっています。鈴木農政が、高市経済のアキレス腱にならないことを願うばかりです。
(追加)
2025年12月9日、農林水産省がコメ政策について「需要に応じた生産」を法律に盛り込む方針を固めたと報じられました。
これが意味することは、実質的に減反政策への復帰を法律に明記することによって、石破政権でやろうとしたような「コメの増産はさせない」、政権が代わっても減反の原則を転換させないということです。
さらに、「需要に応じた生産」を推進して米価が暴落しないよう調整していくことになるので、現在の高いコメ価格が、この水準で固定化されるということを意味します。
(関連投稿)
以下のサイトで、さまざまな農業問題について扱っています。ご関心があれば参照下さい。
(参照)
コメ、増産路線を修正 価格は市場任せに回帰 鈴木農相が方針
(2025年10月24日、食品新聞)
「米価と洋服は同じ」鈴木農水大臣の発言を食料安全保障の専門家が痛烈批判…「米の備蓄は国防費と同じ」
(2025/11/07 『女性自身』編集部)
高市政権の「農政復古」
(2025年11月12日、国基研ろんだん)
コメ高騰問題 古市憲寿氏「噓というかぎまんというか、ずるい発言」鈴木農相の「価格はマーケットで」発言を一刀両断
(2025/11/09 サンスポ)
お花畑の農業論にモノ申す
(2025年10月31日 Wedge Online)
〈検証〉鈴木憲和新農水大臣のコメ政策“転換”、「需要に応じた生産」「おこめ券」は妥当なのか
(渡辺好明・新潟食料農業大学名誉学長)
「令和の米騒動」が収まらない。国産米が消える日
(2025.10.27、文芸新書)
「おこめ券」でJAはボロ儲け? 国民から「いらない!」とブーイングでも鈴木農相が執着するワケ
(2025/11/30、日刊ゲンダイ)
やっぱり進次郎のほうがマシ…「コメの値下げは無理」と言い張る農水大臣に、高市首相が命じるべき「5つの策」
(2025/11/23 PRESIDENT Online)
進次郎農水大臣のほうがよっぽどマシ…高市政権に潜り込んだ「コメの値段を下げたくない農林族」の正体
(2025/10/25 PRESIDENT Online)
今、改めて、旧モンサント社の功罪を問う
昨日、『日本の農業 その現実と未来』をテーマに、日本の農業についてまとめたものを公表しました。令和のコメ騒動に揺れる日本ですが、コメの供給に頭が一杯で、安全性の議論がなおざりになっているようです。そこで改めて、遺伝子組み換え(GM)種子メーカーの世界最大手、モンサント(現バイエルン)に焦点を当て、
と題して、遺伝子組み換え市場について深堀りすると同時に、旧モンサント社の功罪と、現在の世界のGM市場についてまとめました(上赤字タイトルをクリックしてお読みください)。
なお、今回の投稿は、拙著「日本人が知らなかったアメリカの謎」の中の「モンサント ―遺伝子組み換え種子で、世界を支配!?その目的は何?―」を加筆校正したものです。
日本の農業を考える 「令和のコメ騒動」の背景と今後
「令和の米騒動」に日本中がコメ価格に翻弄されるなか、日本の農業について真剣に考えてみました。そこで、「日本の農業、その現実と未来」と題して、「農政」、「食料安保」、「食の安全」の3テーマ毎に、日本の農業の現状、問題点などを総合的かつ体系的にまとめてみました。
<農政>
<食料安保>
<食の安全>