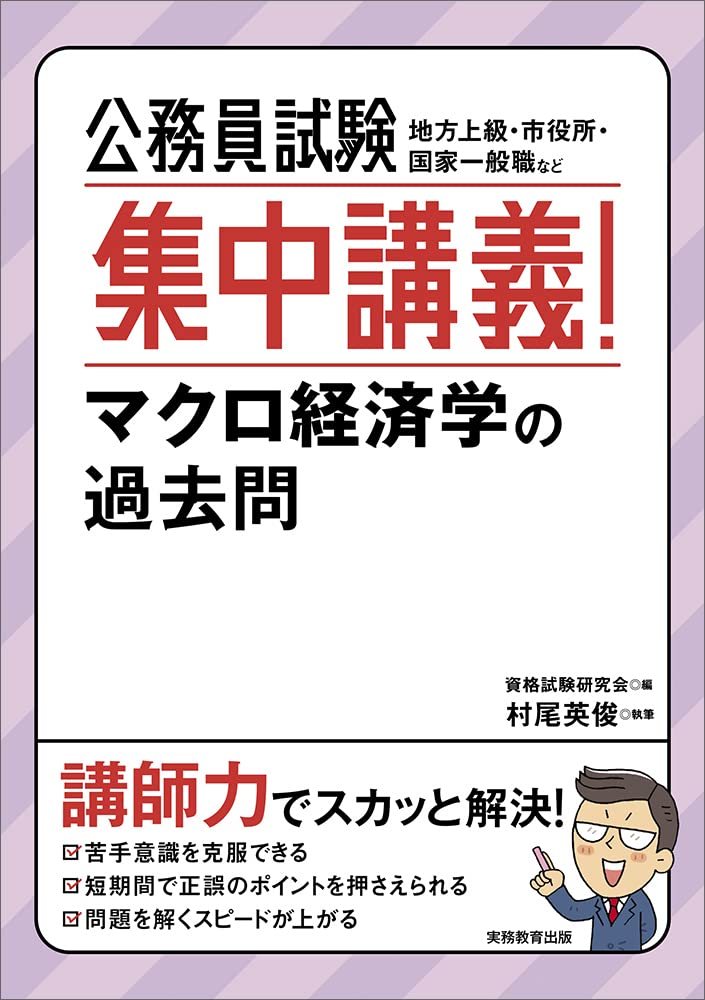前回の投稿では、マニ教の教義を中心にまとめましたが、今回はマニ教の創設から、その発展と衰退の歴史をみてみましょう。
★☆★☆★☆★☆
<預言者マニの出自と立教>
マニ(マーニー)(摩尼)
(216年4月~277年2月)
予言者マニは、アラム語で「偉大な」という意味の尊称マー(Mar)を冠して、大マニ(マニケーウス)と呼ぶ場合があります(摩尼はマニの音訳)。
マニは、アルサケス朝パルティア時代末期の西暦216年4月14日、南バビロニアのユーフラテス川沿いの小村マールディーヌで生まれました。ユダヤ教徒の両親は、パルティアの王族に連なる家系出身であったとされています(王族の家系に関してはマニ教信徒のあいだで生み出された後世の潤色という見方もある)。
マニの生まれ育ったバビロニアでは、多様な民族・言語・慣習・文化が共存し、数多の文化や宗教を学ぶ機会があり、このヘレニズム的環境がマニ教の創設に大きく影響しているとみられています。
ユダヤ教徒の家庭に生まれましたが、ユダヤ教と言っても、父パティークは、ユダヤ教系キリスト教のグノーシス主義(霊知思想)洗礼教団「エルカサイ派」に途中から属していました。近年、マニ自身も、ユダヤ教に由来するエルカサイ教団出身であることが明らかになりました。マニ教は、これまでゾロアスター教やミトラ教など東方の宗教に起源があるとされてきましたが、このグノーシス主義のエルカサイ教団の影響が大きいてみられています。
エルカサイ教団(エルカサイ派)とは、ユダヤ教・キリスト教・グノーシス主義のシンクレティズム(折衷主義)的宗教組織で、紀元1世紀頃にエルカサイによって創始されました。その教義では、「火」ではなく「水」こそが、すべてを清めるものとして、文字通りに「洗礼」を重視したので、洗礼派(キリスト教的洗礼派集団)とも呼ばれました。
また、原始キリスト教の新興派にも分類されるエルカサイ派は、肉食の禁止(食物を「清浄」と「不浄」に二分割)など厳格な戒律主義を実践しました。加えて、女人禁制であったことから、マニの父パティ―クは妻を捨て、教団内で修行に没頭したと伝えられています。当初、母親から育てられたマニでしたが、4歳の時、父とともにエルカサイ教団内で生活したそうです。ですから、マニ自身も、ユダヤ教的・グノーシス主義的教養が身につく環境で成長したことは言うまでもありません。
マニは12歳のとき、聖天使パラクレートス(アル・タウム)からの「啓示」に初めて接したといわれます。この時、自らの使命が明らかにされ、新しい信仰への自覚を持つに至ったそうです。さらに、マニが24歳の時、再び綺羅の霊(きらのれい)(=聖霊)の啓示と召命を受けたと言われています。
綺羅の霊との二回の出会いを通じて、マニは、この聖霊の導きで、以下のような宇宙開闢以来の全歴史をありありと観るという神秘体験をしたとされています。
―――――
太古において、神族と魔族の戦いがあり、この時、原人オフルミズド(アフラ=マズダー)は、決定的な敗北を喫し、無数の微細な光のかけらになって飛散した。光のかけらの救済に現れた救済神は、「光明の父」、すなわち永遠の時間の神ズルワーンの化身であるミフルヤズド(ミトラ神)であった。その後、ズルワーンは、眷属の神々(七大天使)を指揮し、実際はセト、エノク、ノア、ザラタス、釈迦仏、イエスなど使徒たちを通して、復興と救済に当たっている。
―――――
こうして、2回目の綺羅の霊の啓示と召命を受け、マニは、インドに旅をして仏教なども知ったのち、242年3月、マニ教をバビロニアで宣明しました。エルカサイ教団とは、その教義に異議を唱えたことから破門された形となりました。
<マニの布教と殉教>
さて、マニの生涯は、ほとんど福音伝道の放浪の旅に費やされました。その伝道の初期、バビロニアに戻ったマニは、ササン朝の第二代シャープール1世の弟を改宗させ、その仲介で、シャープール1世(在位:241~272)に拝謁し、ペルシア帝国内でのマニ教布教の許可を王から得るとともに、クテシフォンの王宮に迎えられ、重用されました。マニの医学的知識が評価され、王の遠征にしばしば同行したとされています。
マニは、マニ教の教義をみずから著した最初の教典「シャープーラカーン」を王に献上しています。そこには、王とマニとの間の宗教上の相互理解についての記述も含まれていました。シャープール1世自身もマニ教に理解を示したと言われていますが、王自身はゾロアスター教徒であったので、マニ教は保護されたとしても公認されたわけではありませんでした。
それでも、マニ教は、シャープール1世の庇護を得て、教勢を拡大させることができました。世界に教えを広めることを自らの使命と考えたマニは、ササン朝ペルシア全域に広く布教しただけでなく、シリア、ローマ、エジプト(のアレクサンドリアはじめ北アフリカ各地)、インドなどの地域へ、弟子(高等司祭)たちと分担して(弟子たちを伝道団として送り)、マニ教の勢力を拡大させました。この布教は大成功を収め、信者の数は急増し、教会を組織し、弟子の教育に努め、聖典の翻訳もさらに進められました。
こうしたマニ教の成功に危機感を強めたのが、ササン朝内のゾロアスター教祭司団でした。当時、ゾロアスター教の祭司長は、キルデール(カルティール)で、王朝の宗教政策に大きな影響力を持っていました。(キルディールらはゾロアスター教の国教化を進められていたとされる)。
キルデールは、マニの排除を画策しましたが、シャープール1世の生存中は成功しませんでしたが、272年にシャープールが死去し、次のホルミズド1世(272年-273年)とバハラーム1世(在位:273~276)の時代になると、イランにおけるマニの立場を急速に悪化させることに成功しました。
マニは、シャープール1世の死後、伝道に専念しようと王宮を辞しましたが、マニ教を宮廷から排除したバフラーム(ワフラーム)1世は、マニの行動にさまざまな弾圧を加えました。マニは、迫害の中止を訴えたが、王は訴えを取り上げないどころか、マニを捕らえて投獄してしまいました。
こうして、キルデールの讒言(ざんげん)で、拘留されマニは、26日後の276年2月に死去しました(獄死したとも、処刑されたとも言われ、その最期は不明)マニの殉教については、これまで、重い鎖をつけられたとか、死刑になって体を二つに切り離された様々な残酷な受難をマニは被ったとも伝えられてきました。
しかし、近年では、かなり自由に信者と面会していたとする文書も出土しており、マニは穏やかな状況で獄死したとの見方も出て、臨終の際、弟子(伝教師)のアンモー、アブザキヤ、ウッジに、2人の信徒と、2人の通訳が立ち会ったとされています。マニは、全教会に向けた「封印の手紙」を、アンモーに口述し、後継者にシースを指名した後、般涅槃に入ったそうです。その際、迎えに来た天使たちに付き添われて太陽の戦車に乗り、ハープの音と聖歌の合唱の中、天使たちに付き添われて天に昇って行ったと伝えられています。
<マニ死後のマニ教団>
マニは生前に自ら聖典を書き、弟子も多かったので、マニの死後、バビロニアを中心にマニ教団が成立していったと言われていますが、マニは生前、殉教を予見し、自分の死後に備えて、マニ教の教団組織を作り上げていたとされています。
マニの死後、「法王(ディーン・サーラール)(教長)」の座には、シース(スィースィン)が就任し、教団本部をササン朝の首都クテシフォンからバビロンに移しましたが、ゾロアスター教を国教とするササン朝からの弾圧はとどまりませんでした。
286(293)年には、ゾロアスター教の司祭長キルディール(カルティール)に呼び出され、初代教長スィースィンと「3人の長老」が処刑されてしまいました。その後、法王(教長)の座は、マニの直弟子であったインナイオス、ハッティーと受け継がれたとされています。
4世紀に入り、9代皇帝シャープール2世(在位:309~379年)と、第10代皇帝アルダシール2世(在位:379~383年)に時代には、ササン朝の中心部での布教が禁止され、またマニ教徒に対する国内移動が制限されるなど、マニ教は異端として排除され厳しく弾圧されました。
そこで、彼らの布教活動は、メソポタミア南部やアラビア半島だけでなく、西は北アフリカ・イベリア半島から、東はインド、さらに西域、中国と、西アジアからユーラシア大陸の東西に拡大し、広く信仰されました。
ゾロアスター教はイラン人以外の民族には広がりませんでしたが、寛容な諸教混交の立場を表明したマニ教はキリスト教や仏教の要素も取り入れた世界宗教的な教義を持っていたので、他の民族にも受容しやすかったことが要因として指摘されています。
<マニ教の世界展開>
- マニ教とキリスト教
マニ教がローマ帝国に伝えられた頃、キリスト教も、同じように、ローマ領内で布教活動を行っていたので、両者は各地で対決することとなりました。また当初、この両宗教を同じような危険な宗教と捉えたローマ帝国からたびたび弾圧されました。
例えば、領内のマニ教拡大に不安を覚えたローマ皇帝ディオクレティアヌスは、297年に、マニ教徒がペルシアのスパイであるとして、エジプトに「反マニ教宣言書」を送り、焚書や信徒、教師の死刑、財産没収、強制労働を命じました。
それでも、こうしたディオクレティアヌス帝の迫害も乗り越えて、4世紀から5世紀にかけて最盛期を迎えたマニ教は、シリア、パレスティナ、エジプト(アレクサンドリア)から、北アフリカのカルタゴにまで、ローマ帝国領の都市知識層に迎えられました。また、西方では、ローマがキリスト教の国教化前にローマ帝国全域にマニ教信者が増加し、原始キリスト教と並ぶ大勢力となりました。
ローマ時代の初期キリスト教最大のラテン教父アウグスティヌス(354~430)も、その主著「告白」で述べているように、カルタゴ在住時代の青年期(カルタゴ遊学の一時期)にマニ教の影響を受け、マニ教の「聴講者」として信徒に加わっていました(アウグスティヌスは、その後、回心してキリスト教徒となり、「神の国」の理念を作り上げた)。
しかし、ローマ帝国でキリスト教が公認され国教となってからは、度重なる公会議や異端論争を経て、マニ教は「グノーシス主義一派」の異端の一つとして扱われると、ローマ・カトリック教会と東方正教会双方から迫害を受け、6世紀から7世紀頃には、ヨーロッパから姿を消したとされています。
もっとも、中世のキリスト教化されたヨーロッパにおいても、マニ教の影響は強く残りました。マニ教の現世否定の善悪二元論的な思考法は、東方アルメニアのパウロ派や、ブルガリアのボゴミール派、南フランスのワルド派や、カタリ派(アルビジョワ派)などに受け継がれました。もっとも、これらの宗派は、「マニ教的異端」ではあっても、教祖としてマニを承認しないので、マニ教の分派には分類されていません。
マニ教のグノーシス主義的二元論
キリスト教会は、神は唯一無二の存在であるとする一方、マニ教的(グノーシス主義的)二元論の立場に立てば、善神と悪神が存在すると考えます。人間の霊魂(善神の天使)、また神により創造された精神は、悪しき肉体という牢獄に閉じ込められている(拘束)と考えられました。現実世界や、そこに存在する物質的なものは全て、悪神(悪魔)の手で作られ、悪神が支配しているので、物質や肉とかかわる行為である結婚,肉食,飲酒、また教会の洗礼や聖体の秘跡,十字架,奇跡なども悪魔に由来するものとしてすべて否定されました。
パウロ派
ビザンティン帝国のアルメニアで3世紀頃に起こった異端で、最初は、キリスト養子論(神がイエスを死から蘇られせることによって、イエスは子として高められたという考え方)を奉じていましたが、パウロ派が、7世紀に帝国の東部に拡大したころには,マニ教的二元論を採用していたとされています。なお、パウロ派の名称は、キリスト養子論を説いたアンティオキア主教のパウロスからきていると見られています。
ボゴミール派
ブルガリアで10世紀に興ったキリスト教の一宗派で、正教会改革運動とマニ教的二元論が結合して形成され、ビザンツ帝国内の各地に広まりました。12世紀後半以降、ビザンツ帝国内から、西方へ伸長し、13世紀初めには黒海から大西洋まで広がりました。その過程で、ボスニアでは国民的宗教となり、フランス,イタリアのカタリ派あるいはアルビ派に大きな影響を及ぼしました。ブルガリアでは 14世紀まで続き,ボスニアの多くの信徒はイスラム化し,バルカン地方の民間信仰のなかに解消されていったとされています。
パウロ派もボゴミール派も、マニ教的二元論の観点から、地上の物質的なものは全て悪魔の手で作られたものであるから、東方正教会や東ローマ帝国などの聖俗の既成権力を否定しました。
カタリ派とワルド派
両派とも、中世において、ローマ教会から異端とされた、南フランスで勢力を持ったキリスト教の一派です。ワルド派は、12世紀の末にリヨンに現れ、ロンバルディア、ドイツ、スペイン、ボヘミアに広がりました。カタリ派(カタリとは清純者の意)は、10世紀半ばに現れ、フランス南部(ラングドック地方)とイタリア北部で活発となったキリスト教色を帯びた民衆運動で、13世紀頃まで栄えました。いずれも、マニ教の二元論的な世界観を持ち、教会の権力や富を否定し、清貧を主張する共通性を持っていました。
アルビジョワ派
このうち、カタリ派は、地域や時代によって、その呼び名が異なり、12〜13世紀ごろ,アルビジョワ派(アルビ派)とも呼ばれました。これは、カタリ派が南仏アルビを中心としたトゥールーズ伯領にかたまっていたからですが、カタリ派の一派とする見方もあります。
いずれにしても、アルビジョワ派は、肉体と俗世の克服のため、純潔の保持,断食・肉食・巡礼などを拒否するなど、過激に教会制度を否定して、カトリック教会と対立しました。このため、13世紀のローマ教皇インノケンティウス3世は、フランス国王フィリップ2世に十字軍派遣を要請、1209年から、3回に及ぶ「アルビジョワ十字軍」が行われ、ルイ9世の時、1229年に制圧されました。これにより、フランス国内の異端は殲滅され、カペー朝による統一が進みました。
- マニ教とイスラム
メソポタミアでは、7世紀にムハンマドを開祖として、イスラム教がアラビア半島で勃興し、またたくあいだにササン朝ペルシアを滅ぼし、東はインドの西端から西はイベリア半島まで、広大なイスラム帝国を築いていきました。
このイスラムもまたマニ教を「異端異教」として弾圧されましたが、当初は、迫害されなかったどころか、8世紀前半(732年)、ウマイヤ朝6代カリフ、ワリード1世(705~715年)は、法王(教長)ミフルが指導していた当時のマニ教を認め、イスラムの保護下に置きました。
このため、多くのマニ教徒が中央アジアなどから、新たに本拠となったクテシフォンへ集まってきました。一方、ササン朝の滅亡で、権力基盤を失ったゾロアスター教は求心力が低下し、マニ教に改宗する者が相次いだと言われています
しかし、750年に成立したアッバース朝は、三代カリフ、アル・マフディーが、マニ教を「異端」と断罪し、大弾圧を始めました。マニの絵画に唾を吐かせ、鳥を食わせ(マニ教は肉食)、マニ教徒だとわかるとその場で斬首したと言われています。
迫害に耐えられなくなったマニ教教会は、10世紀前半には、中央アジアのサマルカンドに本部を移しました。クテシフォンには、5人ほどの信者しか残らなかったと言われ、またこの混乱で、マニ自筆の教典写本なども喪失してしまいました。
イスラム教への影響
このように、マニ教は、イスラムから迫害されたものの、イスラム教にはマニ教との類似点が多く見られます。
マニは、自らを、ユダヤ・キリスト教の継承者で、最後の預言者を意味する「預言者の印璽(いんじ)」としましたが、イスラム教の教祖ムハンマドも「預言者の印璽」を名乗りました。イエスを預言者の一人として、「神の子」を否定するイエス観も、ムハンマドにも継承され、イスラム教のキリスト教理解に大きな影響を与えたとされています。
また、ムスリムの義務である「五行」(信迎告白・礼拝・断食・喜捨・巡礼)は、マニ教の一般信者(聴問者)の5つの義務(「戒律」「祈祷」「布施」「断食」「懺悔」)と類似しています。この中で、「断食」に関して、マニ教では「ベーマ祭」に先立つ1ヶ月間の断食が要求されましたが、これがイスラム教における断食月ラマダーンの先駆となったとみられています。
このように、マニ教の宗教体系の多くは、イスラム教に受け継がれています。そもそも、イスラムの布教が短期間のうちにあれだけ広大な地域で成功できた理由としては、それらがすでにマニ教が教化した地域であったと指摘する向きもあります。
- マニ教の東方展開(中国・ウイグル)
マニ教は、バビロニア・クルディスタン・中央アジアを地盤としつつ、そこから西域へ勢力を伸ばし、チベットから中国へ到達しました。さらに、中国から、ウイグルや、江戸時代に日本にも伝来しました。マニ教の東西伝搬に貢献したのが、サマルカンドなどを拠点に中央アジアのオアシス地帯で早くから交易に従事していた、イラン系民族のソグド商人の商業活動と言われています。
中国とマニ教
マニ教は、6世紀以後、イスラム教から圧迫される形で東へ東へと移動し、7世紀末には、ソグド商人によって、ゾロアスター教とともに、唐代の中国に伝えられました。「摩尼教」または「末尼教」と音写され、教義から「明教」との訳語もあり、マニ教徒は「白衣白冠の徒」とも呼ばれました。
中国では、マニ教は、道教・儒教・仏教などを取り込んで、(弥勒菩薩の降生により,地上に理想世界の実現を唱える)弥勒教を成立させています。
唐においては、則天武后(武則天)の時、694年、マニ教の布教者が拝謁して、正式にマニ教の布教が認められました。768年、首都長安に、官寺として、大雲光明寺(大雲寺)(だいうんじ)という名のマニ教の寺院が建てられ、その後も、8世紀後半から9世紀初頭に長江流域の大都市や洛陽・太原などにも大雲寺が建てられました。これには、マニ教を信奉していたウイグルとの関係を良好に保つ意図があったとも言われています。
則天武后(在位 690~705)
唐の第3代皇帝高宗の皇后で、後に自ら国号を周と改め,中国史上唯一の女帝となった。
マニ教は、唐の時代、景教(キリスト教ネストリウス派)・祆教(ゾロアスター教)と共に、三夷教(さんいきょう)と呼ばれ、代表的な西方起源の諸宗教の一つと見なされました。歴代の皇帝は、仏教を含めた外来の宗教に対して寛容であったことから、都の長安を中心に各宗派の寺院が立ち並んでいました。
しかし、道教を篤く信仰していた武宗(在位840~ 846)は、845年に、とりわけ仏教に対して、「会昌の廃仏(三武一宗の法難)」と呼ばれる大弾圧を加え、4600もの寺院が破壊されました。同時に、マニ教を含めて他の諸外来宗教への迫害も行われ、摩尼教寺院も廃止されました(「会昌の禁圧」)。
中国のマニ教は、辛うじて難を逃れた一人のマニ僧によって、福建の泉州で、一種の「秘密結社」のような形式、または道教と混淆した形で伝えられ存続しました。五代十国時代から宋の時代にかけても、マニ教は仏教・道教の一派として流布し続けていたと言われています。
1120年に北宋の第8代皇帝徽宗(きそう)に対して起こされた農民反乱(方臘の乱)の首謀者とされた方臘(ほうろう)は、マニ教徒だったとも指摘されています。実際、方臘は、一種の宗教秘密結社を作り、弾圧のなかで呪術的要素を強めて、同調者を増やしていきました。取り締まりに手を焼く権力者からは、「喫茶魔事」という菜食して魔に仕える教団と呼ばれたり、「魔教」とまで称されたりしていたそうです。その信奉者たちは、平等思想を共有し、肉食せず、神仏を拝まず、ただ日月を拝して真仏としていたと言われています。
元朝(1271~1368年)のもとでは、当初、宗教に寛容な政策がとられたことから、マニ教(明教)は復興し、泉州(福建省)と温州(浙江省)を中心に教勢を拡げました。
ただし、マニ(摩尼)教としてではなく、仏教や道教、ある場合にはキリスト教の一派のように振る舞っていたようです。例えば、マルコ=ポーロが泉州で遭ったという「キリスト教徒」とはマニ教徒だったとも指摘されています。
一方、もともと5世紀の東晋に興った白蓮教(阿弥陀仏の浄土へ往生を願う信仰)が、マニ教(明教)に加え、弥勒信仰(インドに成立した弥勒菩薩に対する信仰)と習合し、元のモンゴル人支配への不満が高まる中で大きな宗教結社となり、元朝末期の1351年に紅巾の乱を起こしました。その指導者、朱元璋が元を滅ぼし、新たに建国した「明」という国号は、「明教(マニ教)」に由来したとも言われています。
しかし、明(1368~1644年)の時代、王朝が安定期に入ると、マニ教は危険視されて弾圧され、15世紀を最後に中国ではマニ教としては全く姿を消したとされています。それでも、秘密結社を通じて19世紀末まで受け継がれたとされ、例えば、清朝末期の1900年に、義和団の乱(北清事変)を引き起こした排外主義的な拳闘集団である義和団なども、そうした秘密結社の一つでした。
マニ教は、現在ではほとんど信者もなく、消滅したとされてきましたたが、中国では、「草庵摩尼教寺」(元代の1339年建立)というマニ教寺院が福建省に現存するなど、現地信仰と混淆して本来の教えからは逸脱した面はあるものの、マニ教信仰が一部の地域で続いています。
ウイグルとマニ教
8世紀半ば以降に中央アジアで有力となったウイグル(回鶻)では、第3代王の牟羽(ぼうう)可汗(かがん=王のこと)が、758年の「安史の乱」で援軍として唐の洛陽に入った際、マニ教僧侶と遭遇し、彼らを連れ帰り、マニ教に帰依しました。その結果、マニ教は、ウイグル族の国教となり、国家的な保護を受けました(ウイグルは、マニ教を国教化した世界史上唯一の国となった)。
ウイグルのハン(可汗)は、マニ教を保護することでソグド人の商業活動を支配下に置くことを狙ったとの見方もありますが、これを機にウイグル内部にマニ教徒であるソグド人が多数移住し、マニ教は西域で大いに繁栄しましました。
それでも、ウイグル内には保守派(反マニ勢力)の反発も強く、779年に牟羽(ぼうう)可汗がクーデタで殺され、マニ教は一時弾圧され衰えましたが、8世紀の末には、改宗した7代懐信(かいしん)可汗によって再びウイグルの国教となりました。
しかし、ウイグルの国教に戻ったのも束の間、840年に、ウイグルはキルギスの侵攻を受けて崩壊しました。ウイグルの敗退によって、多くのウイグル人がモンゴリアから離れるなど、ウイグル勢力は西域において衰退して行きました(その支配地域は、西域の高昌とその周辺地域に限定)。
こうして、マニ教も、中央アジアにおいて、ウイグルの首都高昌(ホッチョ)や、サマルカンド、トゥルファンなどの砂漠のオアシス都市でのみ、細々と存続しましたが、13世紀頃には、中央アジアからはマニ教の痕跡はなくなりました。当時、イスラム化の勢いが強かったことから、イスラム教に改宗していったと見られています。
なお、中国における「ウイグル」の漢字音訳の「回鶻」を取って、イスラム教を、中国では「回鶻教」つまり「回教」と呼称するようになりました。
このように、マニ教は、キリスト教やゾロアスター教など既存の宗教や、イスラム教など新しく興った宗教から「異端」とされながらも、ユーラシア大陸の世界宗教として、マニの時代から千年以上存続しましたが、現在では歴史の遺産となってしまった感があります。
<関連投稿>
マニ教①:グノーシス的な折衷宗教の教えとは?
マズダク教:共産主義の生みの親!?
<参照>
マニ教とは?ゾロアスター教との関係や宇宙図まで解説(雑学サークル)
マニ教概説・序説(KHOORA SOPHIAAS)
国内にマニ教「宇宙図」 世界初、京大教授ら確認(日経)
マニ教とは(コトバンク)
マニ教(Wikipedia)
(2022年7月19日)