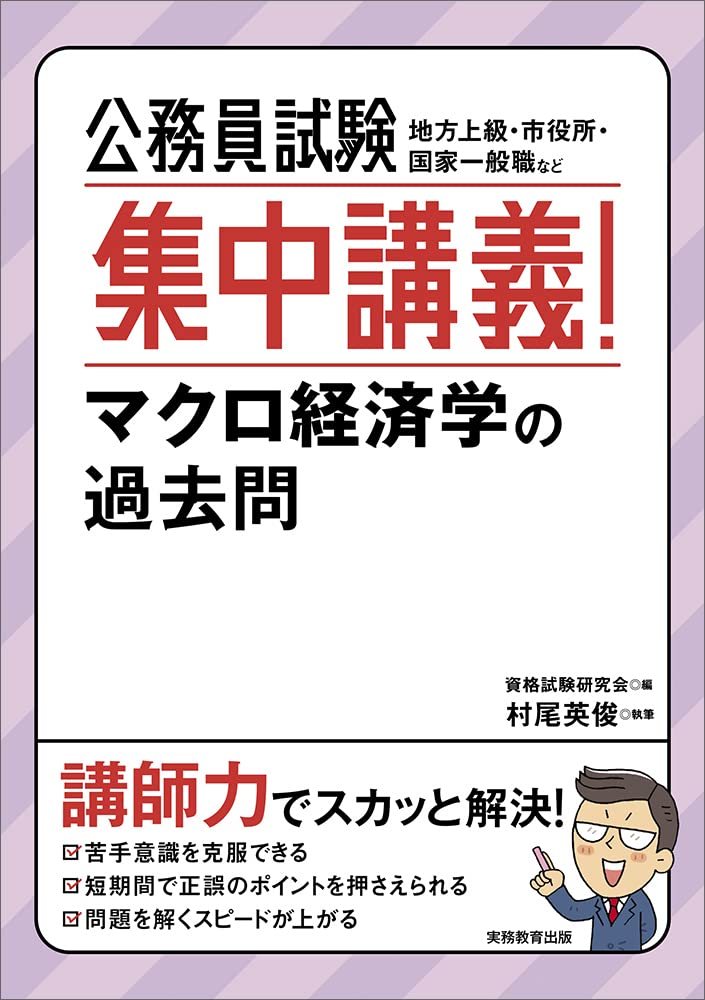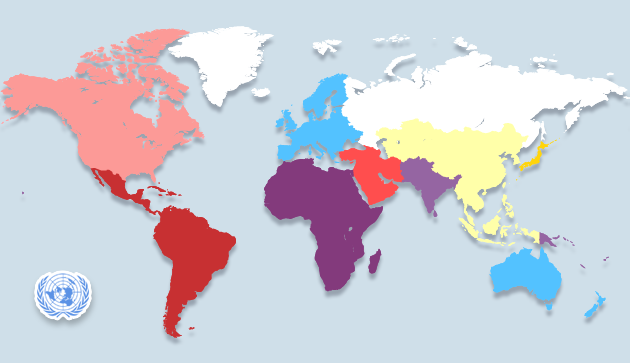メガソーラーが国を滅ぼす⁉
地球温暖化対策として、再生可能エネルギーの活用が謳われています。現在、再エネの中でも太陽光発電が積極的に取り入れられ、全国に所狭しと太陽光パネルが張り巡らされています。太陽光発電は、気候変動対策だけでなく、エネルギー自給率が低い日本にとって、自前で電力を獲得し、自給率を高めるための切り札として期待されています。
しかし、一見優等生にみえる太陽光発電ですが、このまま日本に太陽光発電が導入され続けることが、温暖化対策、自給率対策はおろか、国益を害することにもなりかねないというかもしれないという状況があります。今回は「太陽光発電の闇」の一端をみてみたいと思います。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
<太陽光発電の普及>
◆ 再エネのエース
2023年度の発電電力量のうち、石油・石炭・天然ガス(LNG)などの化石燃料(火力発電)の発電割合が68.6%、原子力発電8.5%に対して、太陽光、水力、風力などの再生可能エネルギー(再エネ)は22.9%です。またその再エネのなかでは太陽光発電の割合が最も多く、9.8%を占めています。
再エネの発電比率の割合(電源構成)は、2010年に約9.5%と全体の1割未満でしたが、福島第一原発の事故を踏まえ、経済産業省は、2012年から本腰を入れ、原発に代わって再エネの普及を進めるために、固定価格買取制度(FIT制度)を導入しました。
FIT(フィード・イン・タリフ)(略称「フィット」)制度は、再生可能エネルギーで発電した電力の全量を、市場よりも高い固定価格で、電力会社に一定期間(10年〜最長20年間)、原則、買い取ることを義務付けた制度です。
これにより、事業としてのインセンティブが高まり、2013年から、再生可能エネルギーの新規参入が飛躍的に増加しました。その結果、再エネ等の比率は、2013年10.9%から2023年には22.9%へと上昇しています。
とりわけ、太陽光発電の伸びが顕著で、2013年の1.2%から2023年には9.8%に急増しました。実際、2024年度末までにFIT制度で運転開始した設備容量の約9000万kWのうち7000万kW が太陽光でした。
なお、2013年当時、再エネの中で最も普及していたのは水力発電の7.3%でしたが、現在は太陽光発電が上回っています(2023年度の水力発電の比率は7.6%でほぼ横ばい)。
また、自民党・菅政権の2021年に、2050年までに、カーボンニュートラル(CO2ゼロ)実現の目標を表明しました。
そのため、再エネの拡大が必要とされ、政府は再エネを主力電源と位置づけ、発電量に占める再エネの比率を、2030年までに、22.9%(2023年度)から、36~38%に、また2040年までに40%〜50%に引き上げることを目指すとしています。
太陽光発電の電源構成も、9.8%(2023年度)から、2040年までに23〜29%に大幅上昇となる予定です。現在は再エネ全体の約40%ですが、2040年には半分を超える比率が想定され、太陽光は文字通り、再エネのエースと位置づけられます。
太陽光発電の電源構成の推移
(2013年→2023年⇒2040年目標)
再エネ:10.9%→22.9%⇒40〜50%
太陽光:1.2%→9.8%⇒23〜29%
◆ FIT制度の影にソフトバンク孫正義
では、どうしてここまで、太陽光発電が普及していったのでしょうか?この背景には、他の再エネと比較して、太陽光設備の建設期間が短くて、設置が容易であることはありますが、固定価格買取制度(FIT)で、太陽光の買取価格が、他の再エネよりかなり割高に設定されたことなどが最大の理由です。
これには、FIT制度を実現させた当時の民主党政権と密接な関係にあったソフトバンク、孫正義会長の存在が見え隠れしています。
2011年3月の東日本大震災後、孫正義・ソフトバンクグループ(SBG)会長兼社長は、「日本を救わなくてはならない」と事業を一時中断してでも「日本再生」に取り組むと公言しました。
具体的には、「脱原発依存」を掲げ、日本全国にメガソーラーの電力供給網を作る構想を打ち出すなど、再生可能エネルギーを使う電力事業への参入を表明しました。
2011年5月、全国の自治体と自然エネルギーの普及促進を加速させることを目的とした「自然エネルギー協議会」の設置を発表、また、8月12日に私財を投じて「自然エネルギー財団」を立ち上げました。さらに、2011年10月には、再エネ事業化のために、「SBエナジー」を設立しています。
孫正義会長が反原発を唱え注目を集めると、当時の民主党政権下の多くの政治家が孫に接近してきました。時の菅直人内閣も、福島第一原発事故を受け、「原発の代わりに再エネでエネルギーをまかなう」という方針を打ち出しました。
菅総理は何度も孫会長に会って意見を聞いており、孫も、民主党や政府の部会で、政府委員や公職にないにもかかわらず、頻繁に呼ばれ意見を表明していました。
孫会長は、「太陽光に支援を集中」「再エネ補助金を優遇せよ」「買い取り保証は超長期で」「原発ゼロ」などを主張していたと言われ、孫の意見が、当時の政権のエネルギー政策にかなり反映されました。
たとえば、国会の参院行政監視委員会(2011年5月23日)に呼ばれた孫会長は、1kWあたり61円でスタートしたドイツの全量買い取り制度の事例を引き合いにだし、「高値での買い取り制度の法整備をぜひ決めていただきたい」と訴えています。
当時すでにドイツでは、太陽光の価格は約20円(18ユーロセント)に下がり、全量買取も廃止されていましたが、日本のFIT制度における太陽光の買取価格は、1kW当たり42円に設定されました。2012年当時の電力卸価格は同6円程度でしたので、この水準が異常に高い固定価格であったかがわかります。
この決定プロセスは、再エネのFIT制度における調達価格などを専門的に算定・審議する経産省の「調達価格等算定委員会(調達委員会)が事前に出した案に、「政治主導」の名目で上乗せされたと言われています。調達委員会も「最初の3年は例外的に利潤を高める」として、欧州(国際価格)の2倍近い割高な水準で決定されたのです。
なお、FIT(固定価格買取)制度そのものは、民主党の菅首相が原発事故対応の「不手際」から退陣を余儀なくされた際、(総理は)全量買い取りの再生可能エネルギー特別措置法案を通すことを条件として、2011年8月下旬に職を辞した結果、2012年7月に誕生したという経緯があります。
いずれにしても、孫は、FIT制度の創設に絡んだ「利害関係者」といえ、合法的に儲かる仕組みを作ったうえで、再エネ事業に参入しました。
ソフトバンク(SGB)は、その後、FIT制度を活用し、太陽光発電事業を中心に再エネ事業を積極的に展開、SBエナジーを通じて「ソフトバンク鳥取米子ソーラーパーク」などの大規模メガソーラーを建設しています。2023年1月時点で、全国に約45の太陽光や風力の発電所を持ち、太陽光667.1メガワット(MW)、風力55.9MWなどを建設・運営する日本有数の再エネ会社に成長を遂げました。
ただし、稼働停止していた原発が、2015年8月、九州電力川内1号機で再稼働するようになると、世の中の原発事故の鮮烈なイメージも薄れていくにしたがい、日本での再エネにかける孫の情熱も冷めていったのかもしれません。2023年2月9日、ソフトバンクグループは、子会社のSBエナジーの株式85%を、トヨタ系豊田通商に譲渡してしまいました。
<外資の参入>
◆ メガソーラー建設ラッシュ
民主党の菅直人元総理とソフトバンクの孫正義会長が実現したとも言える、太陽光発電優遇のFIT(固定買取価格)制度は、再エネとりわけ太陽光発電の普及を後押ししました。太陽光発電のなかでも、各地で建設が相次いだのが、メガソーラー(太陽光発電パネルを敷き詰めた大規模発電所)です。
「メガソーラー事業」とは、メガソーラーで発電された電気を日本の電力会社に買い取ってもらうという「発電ビジネス」のことを言いますが、日本のメガソーラー事業は、再生エネ普及を優先しようと、FIT制度の買い取り価格を過度に高くしたため、確実に利益が見込めます。
民主党政権で制度が発足した2017年7月以降、「日本では国際価格の2〜3倍以上も高い金額で電気を全量買い取ってくれる」ということで、世界中から続々と外資が上陸し、全国のメガソーラー事業に、異業種を含めた事業者が太陽光発電に殺到しました。
再エネ特措法では運転開始の期限を定めないで土地さえ手当てすれば認定したため、海外の投資ファンドが大規模な投資を行い、中には、土地を取得して駆け込みで申請して買取価格を確定し、その権利を転売する業者もたくさん出ました。
民主党政府も、エネルギー不足を補うために、大規模な太陽光発電設備を、建築基準法などの適用対象から外す異例の措置に踏み切るなどして、事業者を支えました。建築基準法などの対象外であれば、事業者は計画の詳細を地方自治体に提出する義務はなく、参入が容易になります。
この結果、住宅・工場・公共施設・未利用地などへ太陽光発電の普及が進み、全国で使えないはずの土地にも続々と太陽光発電拠点に変身していきました。
◆ 中国の一人勝ち
日本に進出してきた外資の中でも、低コストを武器に他国を圧倒していたのが中国企業です。他社との競争に勝つために、発電事業者は、太陽光発電所をつくるコストを低く抑え、安い価格を提示する必要がありますが、中国に敵う国はありませんでした。
太陽光パネルの主要構成単位である太陽電池の出荷量をみると、全世界におけるシェア(2024年)は80%超が中国で、メーカー別の市場シェアも、中国系企業がトップ5を独占しています。
中国メーカーがこれほどの市場を占有している理由は何でしょうか?
そもそも、太陽光発電とは、太陽光がもたらす光エネルギーを、電力(電気エネルギー)に変換する発電方法で、太陽電池を利用して発電します。太陽光を電気エネルギーに変換する太陽電池には種類がいくつかありますが、現在一番多く使われているのが多結晶シリコン系の太陽電池です。
この一般的な素材の多結晶シリコンを使う太陽電池の変換効率(太陽の光エネルギーをどれだけ電気に変換されたかを示す割合)は、現在、15%〜20%の範囲内にあるとされていますが、現在のエネルギー需要を満たすのに十分な実用的で高い効率を実現してしまっています。このため、製品には生産国や製造会社による優劣が有りません(必要とする技術水準が高くなく、簡単に製造できる)。
そうすると、太陽電池は価格だけが競争条件となり、中国は、技術開発には目もくれずに、半導体製造装置メーカーが提供する製造装置を使って大量生産することに専念しました(大量生産→価格低下)。
これにもまして、中国が太陽電池の低価格化を実現できた背景には、中国の太陽光パネルの半分以上は新疆ウイグル自治区で生産されているという事実があります。そこでは、少数民族のウイグル人を低賃金・長時間労働の強制労働をさせているとの疑惑が濃厚です。また、シリコン精製の際に生じるCO2(二酸化炭素)を無制限に排出して電池を作っていると指摘されています。人権や環境を無視した中国製が世界市場を支配しているのです。
太陽電池は、もともと、日本のシャープと日立が先駆者として開発と実用化を主導してきましたが、事業化において、現状、中国の後塵に排せざるをえないという状況です。
◆ 始まりは上海電力
そうした中国企業の日本進出のきっかけをつくったとされるのが、大阪南港北に位置する咲洲(さきしま)の太陽光事業「咲洲メガソーラー」に、中国の上海電力が参入したことでした。
当時の橋下徹・大阪市長がこれに便宜を図ったのではないかと疑惑が持たれています。
咲洲の土地は、橋下市長の前の市長時代は賃貸借の予定がなかったそうですが、橋下氏が市長になった後、貸すことが決まりました。しかも貸す相手は「メガソーラー事業社に限る」と、最初から太陽光発電のために使用することを決定していたのです。出力は2.4MW(メガワット)で、大阪府では最大規模となる、市の一大公共事業でした。
上海電力参入の経緯
2012年12月、大阪市が、メガソーラー事業のため咲洲(さきしま)北西端の土地を民間に貸し出すための競争入札を行った結果、日本の伸和工業株式会社と日光エナジー開発株式会社による「企業連合体」(「連合体咲洲メガソーラー『大阪ひかりの泉』プロジェクト」)が受注しました(賃貸借契約を締結)。(貸付期間は2013(平成25)年1月~令和15年10月末までの約20年間)。
しかし、この入札にも問題が指摘されていました。再エネ事業は儲かるビジネスであるので大阪の事業者なら誰でも手を挙げる案件なのに、1事業体しか入札に参加していなかったのです。しかも、この入札には、通常では公開されることがないとされる「希望賃貸価格(坪55万円)」も発表され、結果、「大阪ひかりの泉プロジェクト」は「55万1円」という最低金額で落札しました。
もしこの案件がもっと周知されていれば、誰もが入札に参加し、こんな安い金額で落札されることはなかったというのが専門家の見立てです(大阪市からすれば、落札金額は高い方がいい)。
その後、伸和工業と日光エナジー開発の連合体組織(コンソーシアム)は、2013年10月、合同会社に組織変更し、合同会社「咲洲メガソーラー大阪ひかりの泉プロジェクト」となり、事業継承が行われました(賃借権譲渡が承認された)。
これが何を意味するかというと、合同会社は、連合体(組合)よりも明確な法人格を持ち、出資者(社員)の変更や事業譲渡などがしやすいため、大規模プロジェクトでの事業再編や第三者への譲渡・転売を、連合体よりもスムーズに行うことができます。
実際、2014年7月、合同会社から日光エナジー開発が脱退し、新たに「上海電力日本株式会社」が加入しました(日光エナジー開発が代表社員から退き、代わりに上海電力が代表社員に加入した)。
なお、日立エナジー開発は、上海電力(日本法人)に対して、インバーターなどの主要な機器を提供・納入する顧客・サプライヤーです。もっとも、日立エナジーが最初から上海電力に対して、メガソーラー事業の賃貸借権を譲渡するつもりであったかどうかは不明です。
いずれにしても、この結果、咲洲メガソーラー発電所を上海電力と日本伸和工業が共同出資で運営することになるのですが、両社の力関係は、上海電力が圧倒的に上です。
上海電力は、中国の巨大国営大手電力会社「国家電力投資集団公司(SPIC)」傘下の日本法人で、豊富な資金力と大規模プロジェクト遂行能力を持っています。発電事業を継承・拡大する中で、上海電力側が経営の主導権を握っていきました。
結局、現在、大阪の南港北にある咲洲メガソーラー太陽光発電所は、上海電力が、実質的に「合同会社咲洲メガソーラー大阪ひかりの泉プロジェクト」を通じて運営しています。
当初、大阪市から土地を借りた事業者は日本企業だったはずなのに、いつの間にか事業主体が、中国企業に変わるという事態が起きました。しかも、上海電力は、大阪市が実施した入札に参加(応札)せず、合同会社の社員変更として行政への「届出」のみで参画し、事業全体を掌握したのです。
このときに橋下市長は、「大阪市の発電事業に、外国企業である上海電力を参入させる」という極めて重要な変更について、市民に一切説明しませんでした。
逆に、上海電力は、日本で初めてのメガソーラー事業となったこの参入について、中国の国家政策「一帯一路政策」の成功例と喧伝しているため、橋下市長が「中国に協力したのでは」と批判されています。
◆ 全国に上海電力!
上海電力は、大阪での「事業成功」を武器に、太陽光のFIT事業認定を9件受けるなど(2023年10月)、日本各地の大規模な「メガソーラー事業」の受注に成功しています。
具体的には、大阪市南港咲洲(2014年稼働)、兵庫県三田市(2016年稼働)を皮切りに、茨城県つくば市(SJソーラーつくば発電所)、栃木県那須烏山市(那須烏山発電所)、福島県西郷村(福島西郷発電所)、青森県東北町、兵庫県三田市や豊岡市、山口県岩国市などで積極的に事業を展開しています。
福島県西郷村のメガソーラーは日本最大級の規模(約7.6万kW)で、総敷地面積は東京ドーム約12個分に相当する大規模事業が計画中です。
なお、「上海電力日本」名義だけでなく、別会社名義で事業を進めるケースや、日本のパートナー企業と共同事業の場合も確認されています。
日本で事業を営む中国企業は、上海電力以外にも、スカイソーラーなども知られています。スカイソーラー・ジャパンは、岩手県軽米町、栃木県鹿沼市、青森県三戸郡南部町など、全国各地でメガソーラーの建設を行い、開発・稼働させ、大阪ガスとは共同事業で合意しています
◆ 中国を利するだけの太陽光発電事業
前述したように、いまや世界の太陽光パネル(太陽電池)は、中国が8割を超えるシェアを持ち、コスト競争力の高い中国製品の台頭により、日本の国内パネルメーカーは生産からの撤退や事業規模の縮小を余儀なくされています。
結果として、かつて世界シェア50%に達した日本メーカーは、中国勢に押され、現在では国内シェア10%未満(2024年は5.1%)にまで落ち込み、日本に設置されている太陽光パネルの約8割が中国製です。これは、国内のメガソーラーを普及させれば、中国メーカーに多くの利益が得られることを意味します。
加えて、確実に利益が見込める「FIT制度(固定価格買取制度)」を利用して、中国企業が日本のメガソーラー事業に積極的に進出している事実を考慮すれば、日本は、政府が再エネ振興策として太陽光発電を普及すればするほど、結果的に、毎月巨額の利益を中国に献上しているということになります。
<日本を壊す再エネ事業>
いまや日本政府は、太陽光を中心とする再エネ最優先を推進することで、日本経済と社会に深刻な影響を与えています。
◆ 太陽光発電の負の遺産
電気代高騰
日本の再エネ政策は、次世代のための投資という見方はできますが、現状、日本経済にプラスに働いでいません。とりわけ物価高に苦しむなか、米価とともに、私たちの家計にのしかかっているのが電気代で、再エネの推進は電気代を高騰させている元凶となっています。
前述したFIT(固定価格買取)制度では、太陽光など再生エネによる電気は、電力会社が発電事業者等から高値で買い取った分は、再エネ課徴金(賦課金)として、家庭や企業の電気代への上乗せという形で跳ね返ってきます。しかも、再エネのなかで導入比率が高い太陽光の買取価格が、他の再エネにくらべても割高になっています。
この再エネ課徴金は年々増額しており、初年度の2012年度には2500億円だった買取総額は、2021年度には3.8兆円と15倍になり、このうち2.7兆円が賦課金として電気代に上乗せされました。
2025年度は、買取総額は4.9兆円、再エネ賦課金(=国民の電気料金に上乗せ額)は3.1兆円になる見込みです(買取総額のうち、事業用太陽光への支払いはその6割に当たる3兆円)。この結果、標準的な家庭(月間使用量400kWh想定)の再エネ賦課金による年間負担額は、19,104円(月額1,592円)程度となると見られています。
景観や生態系への影響
メガソーラー事業においては、山林などを切り開き、時に数万枚超のパネルを使用することもあります。この結果、重要な動植物が生息、生育する場所が消失や縮小することで、環境が変わり影響を与えてしまう可能性があるなど生態系破壊が懸念されています。、
また、森林伐採に伴う災害リスクの増大や、太陽光パネルの設置による景観悪化(良好な景観が変わることや景色が見えなくなる可能性)が指摘されています。太陽光パネルからの反射光がまぶしいという苦情も出ています。
たとえば、北海道の釧路湿原国立公園周辺、福島県西郷村、千葉県鴨川市など地元住民と事業者間でのトラブルも相次いでいます。
太陽光パネルの廃棄問題
太陽光発電の今後の課題として、2012年のFIT(固定価格買取制度)開始当初に導入された発電設備が寿命を迎え、事業が終了した後に発生している設備の放置や不法投棄があげられます。
日本での太陽光発電は、FIT制度が導入されたことで、加速度的に増加しましたが、太陽光パネルの寿命は約25〜30年しかありません。
2040年頃には、太陽光発電設備から太陽光パネル等が一斉に廃棄されることが予想されています。最終処分場の受入能力には限界があるため、大量廃棄による最終処分場のひっ迫が考えられます。
しかも、太陽電池の寿命が尽きると、造るよりも高度で割高な廃棄コストがかかるという、大きな問題が有ります。パネルは、火災の発生や、太陽光パネルに含まれる鉛やカドミウムが、不適切な処分によって流出・拡散といった環境汚染のリスクがあるため非常に危険です。残念ながら、現在の日本には太陽電池の廃棄と言うニッチな技術領域に対応する企業は少ないといわれています。大量の太陽光パネルが、中国企業によって不法投棄された場合の環境破壊が懸念されます。
太陽光発電パネルの大量廃棄問題は、2030年代に顕在化しはじめ(2034~2036年の間に22~34万トンの発電設備が廃棄されるとの推計値も出されている)、廃棄量のピークは2040年頃と予測されていることから、それぞれ「2030年問題」、「2040年問題」と呼ばれています。
◆ FIT制度の軌道修正
こうした割高なFIT制度にともなう様々な問題に対応するために、経産省は、年度ごとに毎年見直される再エネの買取価格を年々下げ、市場の適正価格に近づけようとしています。
特に、再生エネが太陽光に偏っている現状をうけ、重点的に太陽光の買取価格を大幅に引き下げ、たとえば、住宅向け太陽光発電の買取価格は、FIT制度導入時の2012年の42円/1kWhから2025年は16円に、また企業向けの場合も、40円から8.9円〜11.5円に下げられました。
しかし、買取価格が段階的に引き下げられたことに加え、急速な市場拡大による競争激化とそれに伴う供給過剰、維持管理コストや燃料価格の高騰なども当初の計画を上回り出したことから、太陽光関連事業者の倒産・休廃業が急増しています。
帝国データバンクの統計によれば、2024年度には、発電事業者の倒産・休廃業が過去最多の52件(倒産8件、休廃業・解散44件)に達し、このうちの多くが太陽光発電事業者でした。また、2020年度以降の5年間で倒産した発電事業者19件のなかで「太陽光発電」が7件と最も多かったという結果もでています。
この調査結果は、特定の企業名やその国籍(資本構成)といった52件の詳細な内訳は公表さていませんが、資金力のある中国企業の日本法人よりも、日本の中小発電事業者である可能性が高いとみられています。
そうなると、日本の太陽光発電関連事業者の倒産増加は、太陽光パネルの中国依存をさらに進める要因の一つとなりうるという悪循環に陥いることも指摘されています。というのも、事業者の倒産が増えると、国内の太陽光発電関連のサプライチェーン全体が弱体化し、価格の安い中国製パネルへの依存度が構造的に深まることになると見られているからです。
◆「再エネ最優先」は妥当か?
現在、日本では「再エネ最優先」を、実質的に国の基本方針として位置付けています。
前述したように、菅義偉首相は、2020年10月、「2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」というカーボンニュートラル宣言(脱炭素社会の実現)を宣言しました。
そして、このカーボンニュートラルの目標達成に向けて、グリーントランスフォーメーション(GX)(=経済社会システム全体を持続可能な形に転換する取り組み)を推進することが謳われています。
岸田文雄内閣の2023年5月、「GX推進法」と「GX脱炭素電源法」が成立し、GX推進戦略が閣議決定されました。
GX推進戦略とは、日本政府が「脱炭素」と「経済成長」の両立を目指し、化石燃料中心の経済構造をクリーンエネルギー中心へ転換させる国家戦略で、官民150兆円超の大規模投資(今後10年間)などが目玉です。
投資と言っても、その原資はGX経済移行債(国債)を活用すると規定されているので、最終的には国民の負担となって還ってくる可能性があります。これは毎年のGDP(国内総生産)の3%であり、3人世帯ならば累積で360万円にもなると推計されています。
投資先の中心は、再エネ、しかも太陽光発電が主軸となることが想定されることから、政府が再エネ最優先をさらに強化し、積極的に「グリーントランスフォーメーション(GX)」を推進すればするほど、電気代はさらに高騰して、投資資金の多くは中国に流れます。
このまま、FIT制度を含む再エネ政策の枠組みが大きく変化しなければ、日本のエネルギー産業を空洞化させ、日本経済は成長力を失う(ガタガタになる)ことが懸念されます。「再エネ最優先」の国策も、グリーントランスフォーメーション(GX)の推進も、理念としてはよいのですが、その手段としての政策は失敗に終わる可能性があります。
そうしたなか、高市政権は、2025年12月、大規模太陽光発電施設「メガソーラー」について、2027年度から新規事業に対し、市場価格に一定額を上乗せして電力を買い取る支援制度の申請対象外とする方針を決定しました。
この対応によって、これまでのメガソーラーの野放図な拡大に歯止めをかけることができるか、東日本大震災以降の普及促進方針を根本から転換することになるのかが注目されます。
<エネルギー安全保障と再エネ>
◆ エネルギー自給率向上の落とし穴
これまでの日本のエネルギー政策では、「脱炭素」が至上命題となり、経済と安全保障が軽視されてしまった感があります。電力事業は、日本の安全保障上の「最重要なインフラ」で、再エネ推進は、エネルギー自給率を高めるという側面をもっています。
東日本大震災後、日本のエネルギー自給率は2014年に過去最低の6.4%まで落ち込み(震災の年の2011年は11.6%)、その後、回復しましたが、世界的に見ると低い水準です(2024年は12.6%)。
そこで、2021年10月に閣議決定された「第6次エネルギー基本計画」において、エネルギー自給率を当時の13.3%から、「24%前後まで拡大」するという目標も掲げられました。
ただし、「再エネ最優先」のエネルギー政策をとりながらの自給率向上は、太陽光発電がその原動力になっていくことが期待されていることを意味します。そうなると、日本のメガソーラービジネスに、大量の中国資本が参画している事実は、安全保障上の問題として浮き彫りにされます。
もちろん、中国など外資系企業は、日本政府作ったFIT(固定価格買取)制度をフルに利用して、日本で稼いているだけなのですが、上海電力やスカイソーラーら中国系企業は、一民間企業ではなく、中国共産党と密接につながる国営企業であることを忘れてはなりません。
もし、中国が、国益を利するために、日本の電力市場に浸透している国営企業を使って、日本の電力政策にも影響を与えようとしているのであれば、それは安全保障上の問題となります。
◆ 透かしロゴ問題
中国の影響力行使の実態を想起させる、ちょっとした「騒動」が、2024年に起きました。
内閣府にかつて、「再エネタスクフォース(TF)と呼ばれる特別作業班がありました。その目的は、再生可能エネルギー関連規制の総点検と、経産省など関係省庁に再エネ規制の見直しを促す(検討する)ためで、再エネ導入にむけた規制緩和が強力に推進されました。
TFは、親中派で知られる河野太郎・規制改革担当大臣(2020.9〜2021.10)が主導して、2020年11月に設立されたもので、河野大臣の強いリーダーシップから「河野太郎委員会」とも呼ばれ、大臣に近い有識者が委員として参加していました。
「騒動」があったのは、2024年3月、TFの会合で、委員の大林ミカ・自然エネルギー財団事業局長が提出した資料に、中国国営電力会社「国家電網公司」の透かしロゴが入っていたことが発覚したのです。
これにより、日本のエネルギー政策が、中国の影響を受けて決定されているのではないかという懸念が高まりました。河野大臣はチェック体制の不備を認めつつ、タスクフォースの議論内容自体に問題はなかったと弁明しましたが、結局、内閣府の会議体として活動を続けていたTFは、2024年6月に解散となりました(大林委員は同年3月27日に委員辞任)。
◆ 危うい中国依存
河野氏が防衛相を務めていた時(2019.9〜2020.9)、「可能な限り再生可能エネルギー比率100%を目指す」と指針に明記し、全ての防衛省・自衛隊施設の電力調達について、太陽光や風力などの再生可能エネルギーの比率を大幅に引き上げるよう指示していました。
今では多くの自衛隊施設で再エネ電力が購入されているそうですが、太陽光発電をはじめとした再エネ発電はバイオマス以外、発電量は天候に左右され、供給が不安定になる場合があります。日本の防衛施設には、いざ必要なときに電気が足りないということが起らないように、安定的な電力が必要です。
しかし、現在の日本の再エネ政策の結果、中国企業の多くが日本のメガソーラー事業に参入し、かつ、日本の太陽光発電に使われている太陽光パネル(太陽電池)の9割が中国製という状況下、日本が、太陽光発電市場において中国へ依存し続けることは、安全保障上、大きなリスクをともないます。
専門家によれば、中国企業の日本法人は、電力消費量を監視することで、自衛隊の活動状態を把握でき、さらに、有事には、本国の命令があれば、電力供給網を遮断・攪乱(かくらん)することも可能だと言われています。
実際、ノルウェーなど北欧で運行中の中国製電気バスについて、中国のメーカー側が遠隔でアクセスできることが判明し問題になり、ハッキングなどセキュリティに対する懸念が高まっています。
<日本がとるべき政策>
◆ 現行のFIT制度の停止と太陽光パネルの国産化
日本の国益を損ない、中国を利するだけになってしまいかねない、現在の太陽光偏重の再エネ政策、具体的には、FIT(固定価格買取)制度と再エネ課徴金を廃止し、日本の国民経済と安全保障を第一に考える再エネ政策を新たに構築されることが望まれます。
ただし、それは、太陽光発電の普及計画を停止して、再エネ優先策を見直せという意味ではありません。太陽光は再エネ推進の原動力であり、再エネ最優先は日本の国策であり続けるべきで、必要なのは、政策の運用方法の見直しです。
電力を安定供給する観点を土台にとして、再生可能エネルギーの導入(活用)には、国民負担とのバランスに配慮して進める必要があり、電気料金の高騰を招かない制度にせねばなりません。時間や季節、天候に左右されがちが太陽光、風力、水力を、天候の影響を受けない地熱やバイオマス発電が補填するなど、再エネ全体として、安定の電力供給を実現させるシステム作りが求められます。
その上で、太陽光発電に関しては、太陽光パネル(太陽電池)などの重要装備品は、安全保障の観点から、国産に限定することが求められます。いかに、再エネで太陽光を中心にエネルギー自給率を高めることができたとしても、太陽電池にシェアの9割を中国企業に握られたままの状態が続けば、元も子もないからです。
国産品が台頭できるまで、国内産業の育成や、次世代技術(ペロブスカイト太陽電池など)の開発・導入が今後の焦点となっています。
◆ 脱炭素利権
現在、永田町には「脱炭素利権」が跋扈していると言われています。かつては「脱炭素」という経済自滅的な政策には抵抗していた経産省が、いまでは巨大な予算と権限を持った最も強力な脱炭素利権と化したと、一部で批判されているのです。
「脱炭素利権」が国益を損ない、日本経済を破壊していると一部から批判されているのですが、ならば、再エネ最優先をやめて、原発回帰となるべきではありません。それは単に、同じ経産省内の「原発利権」が復活するだけだからです。
残念ながら、原発回帰は高市政権でも進みそうな流れがあります。そこで、次のテーマとして、原発について考察していきます。
<関連投稿>
太陽光発電を含む再エネについては、以下のサイトも参照下さい
<参照>
ソフトバンク参入、動くか電力市場 5000万顧客強み
(2014/2/2、日経)
3.11後、あれほど情熱を注いだ「再エネ」事業を孫正義が手放した本当の理由…
(2023.02.23, 現代ビジネス)
再生可能エネルギー発電事業が苦境 倒産・廃業が過去最多
(2025.05.12 、SDGs ACTION/朝日新聞)
再生エネ普及策 悪質業者の排除につなげたい
(読売新聞社説 2017年5月6日)
再エネFITは民主党政権の生んだ詐欺と腐敗の温床
(2023.23、JBPress)
いびつな真実! 現在、日本のメガソーラー事業の大半は“中国企業”が独占!
(2022/09/23 ワールドジェット・スポーツマガジン)
中国を利するエネ政策を止めよ
(産経新聞(正論)2024年4月10日付)
新規メガソーラー、電力買い取り価格上乗せ廃止へ…消費者が支払う再エネ賦課金が原資
(2025/12/14、読売新聞)
再エネ利権を一掃せよ(2)
(2024.08.19、夕刊フジ)
再エネ最優先、脱炭素という亡国
(2024.10.10、キャノン・グローバル戦略研究所)