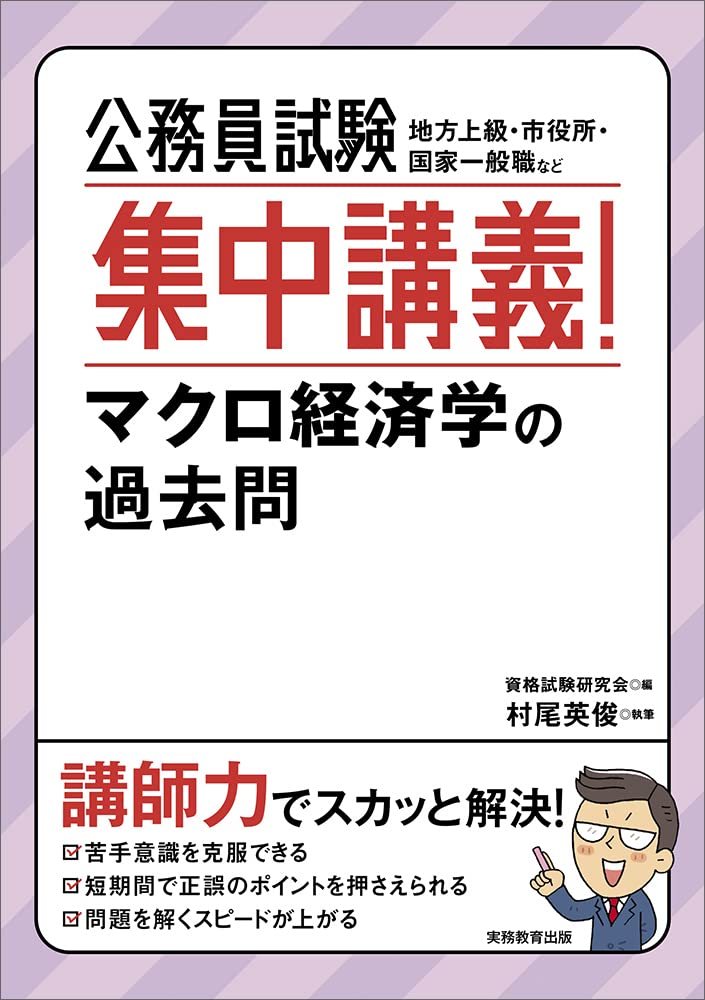東日本大震災から14年が経ちました。震災前まで日本は原発大国に地位にあり、震災後、原発ゼロの気運も高まりましたが、自民党・アメリカ・官僚・労働組合の圧力でかき消され、現在、原発はベースロード電源として、主要な電源とされています。日本の原発政策について改めて考えたいと思います。(人物名敬称略)
☆★☆★☆★☆★
日本に原発を導入し、わが国を原発大国にした人物といえば、元読売新聞社主の正力松太郎と、中曽根康弘元首相の名前が真っ先にあげられます。当時の二人の関係は、正力の意向を、中曽根が実現させるといったように密接過ぎる関係がありました。さらに正力松太郎を動かしたのがアメリカで、米政府―正力―中曽根の太いパイプが築かれていたのでした
◆ 中曽根康弘という政治家
中曽根の功績は、国家予算に初の原子力研究費を実現させたことです。1954年3月、中曽根康弘によって日本の国会に始めて原子力予算が上程されました。両院議員総会において、科学技術研究助成費のうち、原子力平和的利用研究費補助金2億3500万円、ウラニウム資源調査費1500万円、計2億500万円の予算案提出の合意に達し、予算の名称は「原子炉築造のための基礎研究費及び調査費」とすることで採択されました。翌月、予算案が可決され、以後、巨額の税金が利権として吸い上げられる構造が確立していくことになったのでした
◆ 正力松太郎という後ろ盾
当時の中曽根は、自民党内では、旧改進党系で、主流派の旧自由党系の代議士ではありませんでしたが、原子力予算の計上を一代議士で実現させることができたのはなぜでしょうか?中曽根を背後で支持(指示)していたのが読売新聞の社主・正力松太郎と言われています。原子力開発を訴え「原子力の父」と呼ばれた正力は、戦後、戦犯として訴追されましたが、戦犯訴追解除後、古巣の読売新聞社に復帰しました。その後、衆議院議員になり、日本テレビ放送網社長(1952~55)の地位を掴み、1956年1月には、初代の原子力委員会委員長に、また同年5月、科学技術庁長官にも就任しました。
この正力松太郎は、正力が戦犯不起訴で巣鴨刑務所出獄後に、アメリカの諜報機関CIA(中央情報局)の工作に「協力」していたことが、米国立公文書記録管理局が公開した外交文書によって明らかになっています。50年代から60年代にかけて、CIA(中央情報局)は、公職復帰した政治家、右翼、反社会勢力の人物などを含めた日本の保守層に、資金援助する形で囲い込みました。アメリカの目的は、冷戦下にあった当時、日本の保守政権を安定させる(日本を共産化させない)こと、情報を提供させ日本の実態を把握すること、かつアメリカの対日政策を推進させることなどがあげられます。
1955年の自由民主党(自民党)の結党においても、CIAの資金供与があったとされ、また、当時の岸信介、池田勇人両政権下の自民党有力政治家に数百万ドルを提供していたという事実も、米国務省などの公開資料から明らかにされています。自民党という政党は、その誕生から「親米」政党であることが運命づけられていたのです。そうした、CIAとのつながりを取り沙汰されていた人物としては、戦前の特務機関を仕切っていたとされた「右翼のドン」、児玉誉士夫が有名ですが、読売の正力松太郎や元首相の岸信介も、CIAと取引した人物と目されています。
◆ アメリカの原子力戦略
では、当時のアメリカの目論見とは何だったのでしょうか?アメリカは、1950年代に入り、原子力の発電利用に傾いていました。この背景には当時、核兵器はカネにならないことがわかったことがあげられます。核兵器は余りに残虐な兵器なので、戦争では使えない、輸出もできない、ソ連との軍拡競争で核兵器の数を増やしても「割に合わない」ことが明らかになったのです。そうなると、アメリカが先駆けた核の技術も不要になってしまう恐れがありました。また、大戦中に原爆開発に関わってきた何万人もの技術者の仕事を確保してあげなければなりませんでした。
そこで目につけたのが、原子力発電です。原発は「掘り尽くせぬ宝の山」と表現されるように、巨万の富を生み出すとされました。原子力エネルギーの原料であるウランは希少資源であることから高価で、また、取り扱いが極めて危険なため、新規の参入者も少なく独占化できるという特長があります。アメリカは、原子力という新しい産業を興し、外交においても強い地位を保ち続けようとしていたのです。
このために、アメリカは、「原子力の平和利用」の一大宣伝を始めます。1953年、アイゼンハワー大統領は、国連総会で「平和のための原子力」政策を打ち出し、「核が生む莫大なエネルギーの平和利用のために技術供与をしよう」と呼びかけたのでした。1954年3月に、中曽根康弘が主導した初の原子力予算を上程し、実現させたというのは、このアメリカの政策の延長線上にあったと考えられます。
◆ CIAと読売の情報操作
ただし、戦後、日本国民の核アレルギーは極めて強く、日本が原子力エネルギーを受け入れる見込みはないと見られていました。そこで、CIAは、日本に原子力を輸出することを可能にするために、日本国民の原子力に対する恐怖心を取り除くための心理戦を繰り広げます。そこで利用されたのが、正力の読売新聞です。1955年1月、読売新聞は、アメリカの「平和のための原子力」プログラムをトップ記事で大々的に紹介し、放送やイベントを含む半年に渡る一大PR活動を開始したのです。奇しくも、その2年前にテレビ放送が開始されメディア力が最大限利用されました。
これが奏功したのでしょう、翌1955年(昭和30年)には、原子力基本法が制定されました。日本の原子力の利用にむけて、国の諸政策の根拠となるこの法律には、原子力の研究・開発・利用を推進して将来に渡るエネルギー資源を確保すること、産業の振興に寄与すること、平和利用に徹することを、原子力利用の目的とすることなどが書き込まれました。
この基本法は自民党成立後、超党派の議員による議員立法で成立し、ほぼ全会一致で認められました。当時、自民党・社会党を問わず、「エネルギーは国家百年の計」で、原子力は、無資源国である日本の国力増進の重要な手段と認識されていました。革新派は、「無資源国の日本が資源を止められたことが無謀な戦争の一因になった」ことへの反省、保守派は、かつての米ソ冷戦構造下において「自衛のためなら核兵器を持てる」との発想で「日本の核武装化」への布石、または少なくとも「核兵器を持てる技術を維持する」という意図があったとされます。
1956年1月に、初代の原子力委員会委員長に就任した正力松太郎は、日本に原子力発電所を5年後に建設する構想を発表するなど、原発推進政策を推し進めようとします。ただし、当時、科学者たちから核兵器への転用や技術的な不透明さを懸念する声が上がりました。
ある時、原子力委員会の委員だったノーベル物理学賞受賞者の湯川秀樹博士は、「動力協定や動力炉導入に関して何等かの決断をするということは、わが国の原子力開発の将来に対して長期に亘って重大な影響を及ぼすに違いないのであるから、慎重な上にも慎重でなければならない」、「研究者が本当の基礎の基礎から積み上げていこう」と主張しました。これに対し、正力委員長は「つくる技術がなかったら買ってくればいい」と反論し、米国からの技術導入を推進する委員会の方針を打ち出したのです。湯川博士は、これに反対して委員を辞任しました。
こうして、日本は、アメリカと正力、中曽根の目論見通りに、原発を各地に建設していくことになったのでした。正力と中曽根は、政界における原発推進の両輪となって動き、正力松太郎は「原子力の父」と呼ばれるようになり、中曽根康弘は、1959年に科学技術庁長官に就任、1982年には総理の座まで射止めました。
◆ 田中角栄と原発
一方、原子力発電所の誘致を、土建屋的な見地で利益誘導したのが田中角栄元首相と言われています。地元の新潟に柏崎刈羽原発を誘致する際、田中は土地取引で4億円の利益を上げたと言われています。1974年に制定された電源三法(電源開発促進税法、特別会計に関する法律、発電用施設周辺地域整備法)の仕組みを作ったのも、田中角栄でした。
これは、地域住民の福祉向上と称して、発電用施設周辺の公共施設整備を行い、原発立地の地元にカネを還元することで、発電用施設の立地を促進するもので、原発利権という言葉も生まれました。
原子力発電所1基あたりの建設費用は、5000億円以上とされ、政治家にとっては巨大な公共事業となり、原発を地元に誘致すれば、多額の交付金が入って来るし、ゼネコンや地元の土建業者など一部の人たちに大きな利益をもたらし、それがそのまま選挙における票田になるというわけです。
◆ 原発大国の虚像
こうして、’70年代、石油ショックを経て、「資源のない日本における原子力の平和利用』は、国是となり、政官民が一体となって原発を推進していくことになったのでした。東日本大震災前まで、日本国内で稼動している原子炉は、54基に及び、世界で第3位の「原発大国」となりました。自民党政府、官僚機構と電力会社は、一体となって「原子力は日本に必要不可欠だ」とのキャンペーンを数十年にわたって繰り返した結果です。安全性に関しても、「原子力発電は、絶対に必要である」、「だから原子力発電は、絶対に安全だということにしなければならない」というロジックが成り立っていました。
東日本大震災から14年、「原発の是非」「原発ゼロ」についての議論はもはや消えてしまった感がありますが、遺伝子組み換えやゲノム食品などの問題とともに国民の安全と健康の観点から改めて問われるべきではないでしょうか?
<参考>
原子力特集 原発マネーに群がった政治家・学者・マスコミ
(週刊現代、2011年5月16日)
1950年制定の原子力基本法、中曽根康弘演説を読み返す
(2013年10月28日GEPR)
戦後史の歩き方(2)核を求めた被爆国・日本
(2013年5月20日、日経)
日本の原発導入の歴史1 -事実が隠される構造
(週刊ポスト2017年2月10日号)
Wikipediaなど
(投稿日:2022.3.13、最終更新日: 2025.4.19)