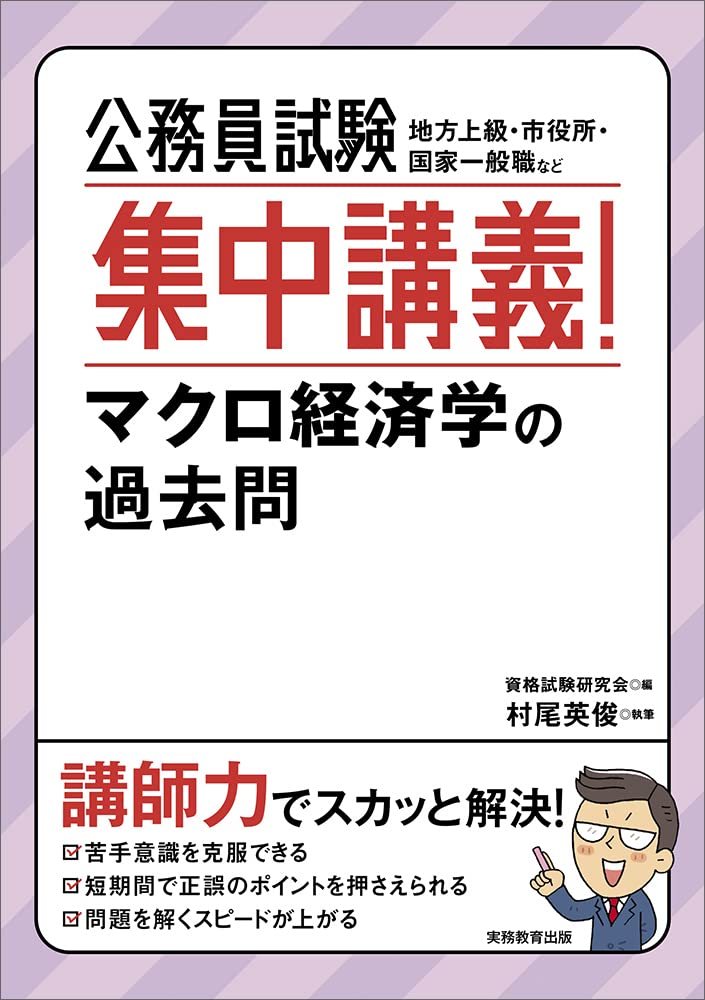マニ教は、その教えの普遍性から、発展を続けていれば、仏教、キリスト教、イスラム教と並ぶ、第四の「世界宗教」となりえたかもしれないとも言われています。今回は、あまり知られていないマニ教についてまとめました。
★☆★☆★☆★☆
<マニ教とは?>
マニ教は、3世紀頃、ササン朝ペルシアの時代、イラン人の預言者マニ(マーニー)を開祖とする宗教です。
現在のイランを中心に、西はヨーロッパやアフリカ北部、東はインド・西域を越えて中国にまで布教され、地域や民族を超えた世界的な宗教の一つに数えられるほど発展しました。さらに、その後のキリスト教・仏教の各派や、イスラム教にも影響を与えたとされています。しかし、11世紀ごろから衰退し、現在は、中国にマニ教の寺院がわずかに残っているほかは、ほぼ消滅したと考えられています。
マニ教は、ペルシア固有のゾロアスター教や、キリスト教のグノーシス派をもとに、ユダヤ教、ミトラ教から、仏教、道教、さらには、種々の神話や伝統的土着信仰を取り入れた折衷宗教(混淆宗教)(シュンクレティズム)です。
マニ教の神話や教義には、ゾロアスター教の神々の名も出てくれば、ユダヤ教の神や神話的人物、キリスト教の天使・使徒なども登場します。更にギリシア神話の神々や英雄、ペルシア神話、インド神話の神々、中国に入って後は、道教の神々やその宗教用語等、さまざまな宗教や神話、文化の価値観が取り入れられています。
もちろん、折衷宗教ですから、マニ教は単に、ゾロアスター教、ユダヤ教、キリスト教、仏教などの教義や神話などを接ぎ木して混成されたという印象を与えてしまいますが、それらは見事に融合・統合されて体系化されています。
では、様々な神話や宗教、伝統的信仰を取り入れた結果、マニ教は何を教えているのでしょうか?その教義をみてみましょう。
<マニ教の創世神話>
マニ教の神話には、とりわけキリスト教原罪思想やグノーシス主義の影響が見られます。
1)原初の対立
マニ教の世界創世の神話は、光と闇の戦いによって始まります。原初、「光の王国」と「闇の王国」がありました。「光の王国」には「光明の父」、「偉大な父(ズルワーン=時)」が存在した一方、「闇の王国」には、「闇の王子=アフリマン(アングラ・マインユ、アーリマン)」がいて、共存していました。
「光の王国」は光・風・火・水・エーテルからなり、「光明の父」は理性・心・知識・思考・理解の5つの精神作用を持っていました。闇の王子アフリマンは、光の王国を垣間見て、光を自分のものにしたいという欲望を抱き、光を手に入れるための戦いを開始しました。
しかし、「光明の父」はかねてこのことを予見しており、予め「生命の母」を生み出し(流出させ)、生命の母から、最初の人、「原人オフルミズド(アフラ・マズダー)」を誕生させました。しかし、原人オフルミズド(アフラ・マズダー)は、五つの「光の元素」を武器に、闇の王国にくだり、戦いを挑みましたが敗れ、光の元素ともども闇に飲み込まれてしまいました。
オフルミズドは「光明の父」に救いを求めると、「光明の父」は、「光の友」と「偉大な建設者(バームヤズド)」、さらに「生ける霊(ミフルヤズド)(太陽神・ミスラ)」を誕生させました。すると、「偉大な建設者(バームヤズド)」は「新しい天国」を作り、「生ける霊(ミフルヤズド)」は、闇に囚われていた原人オフルミズドを闇から救い出し、「新しい天国」へ連れて行きました。
2)世界の起源
しかし、原人オフルミズド(アフラ・マズダー)と共に闇に囚われた「光の元素」は、小さく砕け散って、闇に飲み込まれたままで、救われていませんでした。そこで、「生ける霊(ミフルヤズド)」とその五人の息子は、「光の元素」を救うため、闇の勢力に大戦争を仕掛け、多数の闇の神々(アルコーン)(闇の執政官)を倒すと同時に、多くの「光の元素」を救済しました。
そして、このとき倒された闇の悪魔(アルコーン)たちの死体から「現実の世界」が生まれました。その遺骸から剥ぎ取られた皮から、天が作られ、骨は山となり、排泄物・身体は大地となりました。救い出された「光の元素」のうち、浄化された「光の元素」から太陽と月が、十分に浄化されていなかった「光の元素」からは星がそれぞれ造られました。
しかしなお、多くの「光の元素」の粒子が闇に飲み込まれているため、「光明の父」は更に「第三の使者」を流出(誕生)させました。「第三の使者」は燦然(さんぜん)とした美に満ちあふれ、男のアルコーン(悪魔)の前には、素晴らしく美しい娘(「光の乙女」)として姿を現し、女のアルコーン(悪魔)の前には、輝く手足の美青年の姿で顕現し、闇のアルコーンたちを誘惑しました。
そのため、欲情した男のアルコーンは、美しい「光の乙女」を見て射精し、取り込んでいた「光の元素」を排出しました。その際、放出された精液(精子)の一部は、海の巨獣になりましたが、「光」の戦士によって倒され、残りは、地上に落ちて、五種類の植物となり、地上に広がりました。
他方、欲情した女のアルコーンは、美男に妊娠させられましたが、地獄で流産して、呑みこんでいた光の元素を放出しました。その時、水子は、大地(地上)に、二本足と四本足の動物、飛ぶ動物、泳ぐ動物、這う動物という五つの種類の動物たちを生み出しました。
3)人間の起源
一方、闇の世界では、男と女の悪魔(アルコーン)たちは、それぞれ合体して、男と女の大悪魔となると、光の勢力に、光の元素を取り戻されないように、光の元素を閉じこめた「物質で作った肉体」から、「第三の使者」を模して、最初の人間(人祖)となるアダムとヘーヴァ(エバ/イヴ)を創造しました。
二人は、自分たちの内部に「光の元素」が含まれていることに気づいていませんでした。そこで、「グノーシス(叡智)(隠された真の知識)」を教えて覚醒させるため、「第三の使者」の化身である「真実の開示者イエズス(輝くイエス)」が地上に送られました。
開示者イエズス(イエス)は、「アダムもイブも闇の創造物だが、大量の光の要素を持ち、その末裔たる人間は闇によって汚れていても智慧によって内部の光を認識できる」と説いて、アダムを覚醒させました。
グノーシスを得たアダムは、物質の生殖の連鎖を断ち切るため、ヘーヴァ(イヴ)との性的行為を避けるようになりました。しかし、ヘーヴァ(イヴ)には、グノーシス(智慧)を与えられなかったので、アダムが禁欲する理由が理解できず、アルコーンと交わり、カインとアベルを産みました。
嫉妬に駆られたアダムは、エバ(イヴ)と交わり、セトが生まれて人の営みが始まりました。こうして、カインとアベルの弟であるセトを先祖として、多数の人類が、この世に誕生していくことになりました。
<マニ教神話と救済論>
マニ教において、私たち人間は、闇の物質で造られた世界に生き、私たち自身の肉体もまた闇の物質で、闇に汚されている存在であると考えられています。その一方で、アダムとヘーヴァ(イヴ)を通じて、またセトを通じて、私たちの内部には「光の元素の破片」が潜み、また、光は地上に飛び散ったために、植物は光を有していると見なされています。
そこで、マニ教徒は、闇のアルコーンの策略で、「悪」を広める行為ともなる「生殖行為」を避けねばならないと教えられました。また、光の元素を少量とはいえ内に含む動物を無用に害したり殺したり、食物を採ることも止めることが求められました。
さらに、この闇の世界から救済されるために、私たちは、「グノーシス(隠された真の知識)」すなわちマニ教の啓示を知り、真実に覚醒し、人間や生物の内部に隠されている「光の元素」を純粋に抽出して、まず月に、それから太陽へと帰還させ、最終的に「光の王国」へと戻さ(帰還を促進さ)なければならないと説かれます。
やがて、光と闇のあいだで「最終戦争」が起こり、物質の世界は滅び、光と闇の二つの原理は、完全に分離され、再び混じり合うことがなくなるとされています。
このように、マニは、人間は、悪(闇)の物質でありつつ、アダムとエバ(イヴ)の子孫として大量の光の本質を有する矛盾した存在であると説き、人間は智慧(グノーシス)を得て、自らを救済しなければならないと主張したのです。
<マニ教の宇宙図>
マニ教は、布教に教典のほかに、絵図を使っていたと言われ(絵図は散逸)、とりわけ、マニ教の宇宙観を描いたとみられる「宇宙図」は極めて重要です。マニ教の宇宙観では、世界は「十層の天と八層の地上」で構成され、さらに、これら18層の世界から切り離されている天国と地獄があります。
「宇宙図」では、最上部が、楽園としての天国で、その下に太陽と月(右側の円が太陽、左側の円が月)が描かれています。さらにその下に、円弧で十層に分けられた「天」があり、天使や悪魔の姿のほか、さそり座やうお座など12星座(黄道十二宮)が描かれています。また、人間が住む「地」の八層の世界は、キノコ型にそびえる山が「須弥山」として描かれ、地の八層の下にあるのが、最下層の地獄です。
この宇宙図は、人の肉体に見立て、「天」の十の世界を肋骨、「地上」の人が住む場所を骨盤として見立てているような配置となっていると解されています。
何のためにそうしたかというと、人の肉体を宇宙全体と照らし合わせることで、「宇宙―世界(天)―現世(地上)」という存在が、人の肉体と同じ「悪」の属性であることを示すためだと推察されています。
マニ教の考えでは、人も世界も、物質である限り「悪」です。地上(現実の世界)は、基本的に悪魔の死骸からできており、人間も悪魔の子孫のような存在です。しかし、悪の存在である人の魂には、「光(善)」が受け継がれているので、魂が「悪(穢れた肉体)」から解き放たれると「善」になります。「悪」を捨てられれば、中身である魂は救われ、「宇宙図」で示されている、より高い「楽園(天国)」に近づけると解されています。
<宇宙の三際>
マニ教では、その創生神話にも示されていたように、宇宙は「三際(さんさい)」と呼ばれる三つの時期(初際、中際、後際)に区分されます。
1)初際
第一の時期には、明暗の違いがあるのみで、まだ天地は存在していません。「明」は光で、その性質は知恵であるのに対して、「暗」は闇で、その性質は愚とされています。ただし、両者には、まだ対立矛盾は起っていません。
2)中際
中期に入ると、すでに「暗(闇)」が「明(光)」を侵し始めると同時に、「明(光)」が「暗(闇)」に入り込み、両者は混合します。そのため、大いなる苦しみが生まれ、人は目に見える現実の世界(=「火宅」)から逃れようとします。しかし、この世(「火宅」)を逃れるには、真(光)と偽(闇)を見分け、自ら救われるためのきっかけを掴(つか)まなければならないとされます。
3)後際
第三の時期は、教育と回心を終える時とされ、光(明、真)と、闇(暗、偽)は、それぞれ由来の地である「根の国(極遠の地)」に戻り、光は大いなる光に、闇は闇の塊に回帰します。
<折衷宗教としてのマニ教>
では次に、マニ教が、ゾロアスター教、ミトラ教、ユダヤ教、仏教などの既存宗教をいかに折衷して、自己の教義に取り込んでいるのかを、比較宗教の観点から各宗教の教義にも触れつつみていきます。
- グノーシス主義とマニ教
マニ教は、様々な宗教や神話を取り入れているなかで、特に、キリスト教のグノーシス派の影響を強く受け、代表的なグノーシス主義宗教(グノーシス主義の一派)と言われるほどです。
グノーシス主義(グノーシス派)
そもそも、グノーシス派とは、1世紀に生まれ、3~4世紀にかけて地中海世界で勢力を持った宗教・思想で、キリスト教の異端の一つとされています。
「グノーシス」そのものの語源は、古代ギリシア語の「認識・知識」で、グノーシス主義(グノーシス派)は、「隠された真の知識」すなわち、自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想で、グノーシスを知ることで救済されると説かれています。
グノーシス派は、既存諸宗教、特にキリスト教の内部におこり、キリスト教の教義を、以下のグノーシス神話を基本に、自己に固有な「反宇宙的二元論」の立場から解釈し直して、グノーシス神話をつくりだし、キリスト教のなかで多くの分派を形成していきました。
グノーシス神話
原初には、真の至高神が創造した善の宇宙(神的存在によって満たされた超越的な光の世界=プレーローマ)があったと捉えます。しかし、至高神の神性(プレーローマの存在)の一つであるソフィア(知恵の女神)は、過失によって、ヤルダバオート(別名デミウルゴス)と呼ばれる不完全な(偽の)神を作って(産んで)しまいました。
ソフィアに捨てられた「偽の神」ヤルダバオートは、自らの精霊(サタン=悪)を産み、この宇宙や「物質」があふれる現実世界を作りだしました。
私たちが知る「物質」があふれる宇宙は、神が創造したものではなく、偽の神とサタン(悪魔)が創造したものだと捉え、「偽の神」が作ったこの世界は「悪の世界」で、地上の生の悲惨とされ、この世界が「悪」であるからだと解されます。前述したマニ教神話は、このグノーシス神話の影響を大きく受けていることがわかります。
グノーシス主義の反宇宙的二元論
グノーシス派の教えでは、その神話から、世界は本来的に悪となるので、他の諸宗教・思想の伝える神や神々も、「悪の神」、「偽の神」となります。現実の世界は「物質」で構成されているので、物質も悪であり、物質で造られた肉体も悪であると捉えられます。これに対して、肉体の対極にあるのが、「霊」(理想の世界「イデア」)で、これが真の存在であり世界であると考えられました。
ここから、「善と悪」、「真の神と偽の神」、「霊と肉体(物質)」(=「光・霊・善」と「闇・物質=肉・悪」)の霊的世界と現実世界を分ける「二元論」の考え方が生まれました(これら二つの原理は、世界の原初のときより並列して存在していたとされる)。
こうして、グノーシス主義の反宇宙的二元論(グノーシス主義の世界観)が確立され、マニ教においても、様々な宗教の神の名や神話を、内部に取り入れて独自の解釈と意味づけを行いながらマニ教神話に取り込み、「マニ教グノーシス主義神話」が構成されました。
グノーシス主義的宗教としてのマニ教
このグノーシス主義の影響を受けて、マニ教も万物が、善で光の要素(精神)と、悪で闇の要素(物質)からなるという、(善悪)二元論の立場を取りました。物質や肉体とは「悪」であり、「善」なるものとはそれらと対極にある霊的なモノ、「魂」などに限られるとしました。
既にその創生神話でみたように、マニ教では、これら二つの原理(「光・霊=魂・善」と「闇・物質=肉・悪」)が、世界には原初のときより、並列して存在していたと教えています。その後、宇宙は、光と闇の結合によって生まれました。その創成は、究極的には悪の力の作用であるととらえ、やがて、光と闇が闘争によって、全宇宙は崩壊すると考えます。悪に属するとされた現実の物質世界の未来をきわめて悲観的に考えました。
しかし、このとき初めて光による救済が起こり、闇からの解放がなされると説かれます。この光と闇の闘争は、最終的に救世主(キリスト)が登場して終焉を迎え、「光・善・精神」と「闇・悪・肉体」の2つの世界が、それぞれ明確に分けられていた始原の宇宙へ回帰すると、マニ教は教えています。
- マニ教とゾロアスター教
ゾロアスター教は、世界を善の神アフラ・マズダと悪の神アンラ・マンユ(アーリマン)の2神の対立ととらえ、この地上はこの2神の戦いにおける主戦場となっているとしています。その戦いでは、善の神アフラ・マズダ側の勝利が期待され、われわれ人間は、アフラ・マズダ側に味方することが求められています。
マニ教においても、ゾロアスター教の光と闇の二元論の世界観が一部、踏襲され、マニ教の宇宙観の基礎になっています。しかし、マニ教の創生神話には、ゾロアスター教(マズダー教)の神話と同様に、オフルミズド(アフラ=マズダー)とアーリマンの戦いというエピソードがありますが、マニ教神話では、アフラ=マズダは敗れているように、神話全体の枠組み、神々の構成・位置付け、戦いの結末は、現代に伝わる二元論的ゾロアスター教の場合と異なっています。
また、ゾロアスター教の教義は、善神アフラ・マズダーと悪神アンラ・マンユの2神はそれぞれ精神と物質との両面を兼ね備えていますが、マニ教では、物質と精神(魂)を対立させている点も異なっていいます。この点については、マニ教が、世界を精神(霊)と物質の対立ととられるギリャ哲学の理論を取り入れた解釈されています。
一方、ゾロアスター教の成立そのものは、紀元前に遡りますが、教義が成熟して、二元論的ゾロアスター教が確立したのは5~6世紀頃とされていることから、マニ教がゾロアスター教の影響を受けたのではなく、逆に、ゾロアスター教の方が、マニ教の二元論的な考え方の影響を受けたと見る向きもあります。
- マニ教とズルワーン教・ミトラ教
マニ教は、その宇宙論と神話において、ゾロアスター教の分派とされるズルワーン教や、ゾロアスター教と関係の深いミトラ教の影響を受けたという見方もあります。
ズルワーン教
ズルワーン教は、ゾロアスター教の分派で、すでに消滅したとされる教団です。信仰の対象となるズルワーンは、創造神(最高神)であり、時間の神(ズルワーンが時間を意味する)とされています。3~5世紀にかけてササン朝ペルシアで盛んであったと言われています。
ミトラ教
ミトラ教は、太陽神であるミトラ神(ミスラ神)を崇拝する密儀宗教です(「密儀」なのでその教義についてはあまり明らかになっていない)。ゾロアスター教が成立する前からイランで信仰されており、ゾロアスター教の教義にも大きな影響を与えました。
ミトラ神は、契約・約束・友情の神としても知られ、古代インド・イランのアーリア人が共通の地域に住んでいた時代から信仰されてきた太古の神です。最古の宗教文献とされる「リグ・ヴェーダ」において、ミトラ神(ミスラ神)は、アーディティヤ神群と呼ばれる神々の中の一柱で、魔術的なヴァルナ神と対をなす神として描かれており、二元論的な神観に基づいています。
ゾロアスター教が普及してくると、両者の神々は互いに習合しながら信仰されていきました。例えば、ゾロアスター教では、善の光神アフラ・マズダのみを崇拝すべきと考えて、ミトラ(ミスラ)をはじめとする多くの神々を排除しましたが、後に、ゾロアスター教は、ミトラ神を中級神ヤザタとして取り入れています。
ゾロアスター教からは、低く位置づけられたミトラ神ですが、ミトラ教がローマ帝国へ伝わると、戦いの神(英雄神)となり、ローマ帝国の庇護者である「不敗太陽神ミトラス」として崇拝されました。また、ミトラ(ミトラス)神は、牡牛を屠り、大地に豊穣をもたらす神として信仰の対象となったことでも知られています。
では、ズルワーン教とミトラ教がマニ教にどういう影響を与えたかについて、マニ教の神話をみると、原初、「光の王国」に存在した「光明の父」、別名「偉大な父」は、最高神で時間の神・ズルワーンからきていると解されています。
また、アフラ=マズダとアーリマンの戦いの結果、アフラ=マズダが負けてしまいますが、アフラ=マズダ(オフルミズド)から救いを求められた「光明の父」は、すでにマニ教の創生神話で学んだように、「生ける霊」を誕生させ、「生ける霊」は、闇に囚われていたアフラ=マズダを闇から救い出しました。この「生ける霊」が別名ミフルヤズド、すなわち太陽神・ミトラ(ミスラ)のことだとされています。
ミトラ神が現れ、アフラ=マズダを救済するという展開は、太陽神ミトラ(ミスラ)が、戦いの神として、アフラ・マズダを凌ぐ活躍しているところは、ゾロアスター教と決定的に異なる点です。さらに、マニ教において、ミトラ神は、最高神ズルワーンの化身という見方もあるようです。
一方、マニによれば、ミトラ(ミスラ)神は、少年神、童子神(どうじしん)または、綺羅の霊(きらのれい)、光の乙女となってこの世に現れるとされています。なお、少年神(童子神)と綺羅の霊(光の乙女)の総称をミール(世界教師)とする説もあります(後述)。
- マニ教と仏教・キリスト教・イスラム教
マニ教の物質や肉体を「悪」と見なす価値観は、グノーシス主義の観点だけでなく、仏教的な観点も加味されているという見方があります。一般的に、仏教の最終目標は、現実(肉体)の世界に何度も生まれ変わる輪廻という仕組みから解脱することであると言えます。マニ教も、世俗を否定し、肉体や物質的な世界に存在しつづけることを肯定しないという点で、仏教の禁欲的な面を取り入れていると解されています。また、前述したマニ教の宇宙図は、後の密教の曼陀羅にも通じる共通性があると言えるかもしれません。
一方、アダムとイブも登場するマニ教神話には、キリスト教の終末観や人間の原罪思想が根底に流れています。また、ユダヤ教からは、預言者の概念を取り込み、信徒に対して、モーセの十戒に相当する生活規範の遵守を求めています。
なお、マニ教の後に誕生したイスラム教は、その五行(信仰告白、礼拝、喜捨、断食、巡礼)や「預言者の印璽などの教義の面で、マニ教の影響を受けていると言われています(後述)。
このように、マニ教は、世界の諸宗教の教義や神話、神の名を内部に取り入れながら、独自の創作神話や教義を構成させてきたため、ゾロアスター教からキリスト教、仏教、ヒンズー教に至るまで「異端」と迫害されました。マニ教の後にでたイスラム教においても同様です。それでも、マニ教は、ユーラシア大陸の世界宗教として、マニの時代から千年以上存続しました。
<「預言者」の普遍化>
マニは、ユダヤ教の預言者の概念を取り入れ、民族・宗派の枠組みを超えた預言者の系譜を世界で最初に示したとされています。マニ教では、彼らをミール(世界教師)と呼びました。その系譜は、エジプト神話の戦争の神セト、ギリシャ神話のエノク(ヘルメス)、旧約聖書のノアから、ゾロアスター(ザラスシュトラ)、釈迦、イエスとつながります。マニの時代、ムハンマドはまだ出ていないのでこの系譜には含まれていませんが、後に拡大整備され、孔子、老子、ムハンマド、アリーらが加えられました。
ミールは、いずれも神の使いで、マニ教では、イエスをこの場合、神ではなく、次々と現れる使徒の一人と捉えています。このイエスに対する考え方はイスラム教でも採用されています。
マニ自身も、自らを天使から啓示を受けた者として自任しつつ、歴代の預言者の天啓を最終的に総合する最後の預言者(これを「預言者の印璽」という)と位置づけています。イスラム教でも「預言者の印璽」の概念を導入し、ムハンマドを最後の預言者としています。
<マニ教の経典と翻訳>
マニは、世界宗教の教祖としては、珍しく自らたくさんの経典を書きましたが、その大部分は散逸し、今日では断片的にしか残されていません。
マニの教典(聖典)として知られているものには、「シャープーラカン」、「生命の宝(いのちの書)」、「大福音書」、「伝承集(プラグマティア)」、「秘儀の書(ラーザーン)」、「巨人の書」、「マニ書簡(エピスル)」などがあげられます。このなかで、最初の教典である「シャープーラカーン」が有名で、マニ教の教義綱要が著され、宇宙創世の書とも呼ばれました。この書は、サザン朝第2代の王シャープール1世に献上されました。
また、マニの没後に弟子たちによってまとめられた教義解説書、「ケファライア」もよく知れられています。これは、マニと弟子たちとの対話集(講話集)という形をとり、マニが綺羅の霊からの啓示を受けたことや、クルドの地(メディア地方とパルティア地方)での布教が大成功を収めたことなどが記されています。
マニは、教義を万人対象とするという意図から、これらの教典を、当時の中東世界の共通語であるアラム語を用いて書いたとされています。さらに、みずから書き著した教典を、速やかに、ギリシャ語をはじめ各地の言語に翻訳させました。しかも、異民族や遠隔地の布教を促進させるため、教義の厳密な訳出にこだわるのではなく、各地に伝わる在来の信仰や文化・慣習に合わせて自由に翻訳させたと言われています。
例えば、ゾロアスター教の盛んな地域への伝道のためには、ゾロアスター教の神々の名や神話を用い、また、キリスト教や仏教が優勢な地域への伝道のためには、イエス・キリストの福音や仏陀の悟りを強調して宣教するなど、それぞれの教義や用語を適合させて、わかりやすく伝えたそうです。
しかし、逆に、教典の翻訳が重なるにつれ、本来のマニ教教義が、錯綜してしまい、混同や誤解を招き、教義の一貫性は保持されなかったとの指摘もあります。しかし、それでも、マニ教は、聖典の整備という点では、他の宗教に対して優位に立っていました。ゾロアスター教の教典「アヴェスタ」が書籍化されるのは6世紀のことで、それまでは口伝伝承しかありませんでした。またキリスト教・ユダヤ教でも、聖書が聖典として明確に区分されたのは3~4世紀とされています。ですから、知的水準の高い人々ほどマニ教に傾注していき、世界宗教への発展につながったと言われています。
<教団と戒律>
宗祖マニは、増大する信徒の数に対応して、生存中に、自ら教団を組織し、悪と否定された現世を生きていくための「戒律」を定めました。マニ教は、「選良者」信徒のクラスと、「聴講者」信徒のクラスの二つの集団で教団を構成され、それぞれ守るべき戒律も異なりました。
- 「選良者」信徒のクラス
選良者とは、仏教における出家信者・僧侶、キリスト教における修道士に相当し、専らマニ教の宇宙観・救済論に従い、霊的生活に専念しました。選良者は、選ばれた者、義者、エレクトゥス、またはマニ教修道士とも呼ばれました。
肉体を悪のすみかとする教えに従い、生殖行為を行なわず、かつ物質的生産活動には一切従事しないという極端な禁欲生活の原則で律せられていました。霊的な修行に励み霊的慰めを、聴講者やその他この世の人々・生命にもたらすことを使命としていました。
マニ教選良者には、「真実、非殺生・非暴力、貞潔、食物、清貧」の五つの戒律がありました。
真実の戒律
開祖マニの福音は真理であり、マニ教の教えに敬虔に真摯に従順でなければならない。
非殺生・非暴力の戒律
動物や植物を傷つけ殺してはならない。
この戒律によって、マニ教修道士は生産活動を禁じられました。例えば、麦を収穫すれば、それは麦を傷つけることになるからで、植物の根を抜くこともできませんでした。この戒律の神学的根拠は、物質の微妙な混合体の内部に閉じこめられた「光の元素(光の破片)」が、収穫の際に必要となる作業がもたらす「暴力」によって傷つけられることにあります。
貞潔の戒律」
肉体的快楽(性的行為)は回避しなければならない。
マニ教では、結婚・性交は子孫を宿すことで、悪である肉体の創造に繋がる忌避すべき行為と考えらました。また、物質である肉体の快楽は、光の霊の解放を妨害するためのアルコーン(闇の執政官=悪魔)の策略であると解されました。マニ教の選良者は、男女共に独身です。
食物の戒律
肉、醸造物(ワイン・ビール)、乳製品を食してはならない。
肉食は心と言葉の清浄さを保つために禁止され、飲酒も禁じられました。これらの食品を製造するには、原料に含まれる「光の破片(光の元素)」を損なう過程が含まれるからです。
マニ教徒(選良者も聴講者も)は、「菜食」を基本とします。とりわけ、メロン・キュウリなどの透き通った野菜やブドウなどの果物は、光の要素を多く含んでいるとされ、選良者はこれらをできるだけ多く食べ、光の要素を開放しなければならないとされました。
清貧の戒律
「無所有」を原則としなければならない。
「所有物」とは物質の「この世」のものであるので、それは不要であるとされました。この戒律は、イエスの説いた「清貧」と共通します。
マニ教の選良者は。男女共に、五感を抑制するため「白い衣服」をまといました。そのためマニ教の聖職者は「白装束」とも呼称されました。
選良者の義務は、宗祖マニに倣って、世界中を放浪し真理の福音を伝道して行くことでした。従って、修道士は定住者ではなく、神または上長の命令があれば、ただちにどこへでも伝道の旅に赴くことが求められました。
- 「聴聞者」信徒のクラス
「聴聞者」信徒とは、在家信徒、一般信徒のことで、平信徒、聴講者、アウディトゥス とも呼ばれました。「聴聞者」は、「選良者」に比べれば緩やかな戒律の下で世俗生活を送ることができました。通常は定住者であり、結婚して子をもうけることが許され、家族と共に生産活動に従事して暮らしました。ただし、その分、「布施」によって、選良者たちの生活を支えることが求められました。
マニ教の一般信徒(聴講者)には、五つの義務(戒律、,祈祷、布施、断食、懺悔)が課されていました。これは、イスラム教の五行(信迎告白・礼拝・断食・喜捨・巡礼)に影響を与えたとされています。
戒律
偶像崇拝の禁止など「モーセの十戒」に似た戒律で、選良者の五戒(「真実」「非殺生・非暴力」「貞潔」「菜食」「清貧」)とほぼ同等の内容ですが、選良者に対するほど厳格ではありません。
例えば、「貞潔」の戒律では、聴講者は、「妻は一人で、心より愛さねばならず、断食のとき等、重要な場合には、性的行為は避けること」とされています。また、「清貧の戒律」では、聴講者は家族と生活する以上、無所有では生活が成り立たないので、土地や家屋を「所有」して、世俗の生活をすることが認められています。
祈祷
一日に4度の祈祷が義務づけられました。日中は「太陽」に向かい、夜間は「月」に向かい平伏して祈り、太陽も月も見えない場合は、光の王国のある北の方向、あるいは北極星に向かい祈祷するという手順が定められていました。
布施
「聴聞者」は、結婚して家族を持ち、生産活動ができる代わりに、収入の十分の一または七分の一を、選良者やその共同体に贈与することが義務づけられました。在家信徒の布施によって、選良者(修道士)は生活することができ、マニ教の教会組織も、布施によって運営できました。
断食
聴聞者も選良者も、断食を義務としていました。断食には、毎週、太陽の日(日曜)に行われる週ごとの断食と、マニの地上での最後の日を記念する「ベーマ祭」前の30日間実施される年間の断食がありました(これはイスラム教におけるラマダーン月の先駆となったと考えられている)。
マニ教は、物質を悪とみなし、物質から離れ、魂に帰ること是としていることから、断食は極めて妥当な宗教義務とされました。
懺悔
聴講者も選良者も、週ごとの懺悔と年間の懺悔を義務としていました。聴講者は週ごとに、選良者の前で、戒律を守らなかったこと、罪などを誠実に告白した。また、ベーマ祭前の三十日間の断食の終わりの懺悔は集団で行われ、この儀礼によって、過ぎ去る一年間の罪が赦されました。
ベーマ祭
マニ教の祭礼や祭日は、キリスト教より導入されたものを含め複数がありましたが、マニ教最大で最も重要な祭りが「ベーマ祭」でした。ペーマ祭は、マニの殉教を偲ぶ祭祀で、マニの魂がこの世界から離れ、光の国へと昇天して行った日に行われます(その日が春分の頃であった)。
ベーマとはマニが降臨すると信じられた玉座のことで(ベーマそのものの意味はギリシア語で「座」を意味する)、ベーマ祭礼のときには、(マニ以外)誰も座ることのない椅子の座が準備されます。祭礼の最後の日は、準備された空のベーマ(座)には、マニが降臨すると信じられました。
このように、宗主マニが、信徒を「選良者」と「聴聞者(聴講者)」に二分したことは、若きマニが属したユダヤ教のエルカサル教団を参考にしているという見方もあれば、仏教の出家信徒集団と在家信徒集団の二分構造から着想を得たとする見方もあります。一方、キリスト教の「修道士」と「平信徒」の関係に似ているとも言えますが、キリスト教の修道士は、自らの修道共同体のなかで、生産活動を行い自給自足し、生産のための施設、また例えば食料貯蔵庫などを備えていた点に違いがあります。
いずれにしても、この二つの信徒の区別は、相互補完的であり、一方が他方に対し絶対的に優越するというような関係ではなかったとされています。互いに補完的な二極構造を造ることで、世代に渡り持続する宗教共同体と厳格な信徒集団を作ることに成功しました。
<マニ教会の階層>
マニ教のヒエラルキー(階層)は、マニの後継者と見做される「教長」を頂点に、三段階(教師、司教、管理者)の聖職者階層と、一般修道士階層からが構築されていました。
教長は、法王(デーン・サーラール)とも呼ばれ、クテシフォンの本部に1名いました。三段階の最上位には、キリストの十二使徒に倣った12人の「教師」がおり、その下に72人の「司教」、さらにその下に360人の「管理者(長老)」が、「選良者」の中から選ばれ、マニ教教団の組織運営や布教に当たっていました。
「選良者」(聖職者)
教長(法王)(1人)
教師(12人)
司教(72人)
管理者(長老)(360人)
「聴講者」(一般修道士)
なお、聖職者の人数については、マニの出身地バビロニアの伝統に従って、12に倍数が用いられています。これ以下の一般修道士は、男女共になれましたが、定員の定まっている聖職者職は、教長も含めて男性だけがなれました。
以上のように、マニ教の教団において、マニが「人間には自分のなかの救われるべき本質を自ら救わなければならないという使命がある」として、悪から逃れることを説いた教えを守り、信徒は、壮大な宇宙の戦いに参画しているという意識に支えられながら、清浄で道徳的な生活を送っています。
<関連投稿>
マニ教②:「第4の世界宗教」の発展と衰退
マズダク教:共産主義の生みの親!?
<参照>
マニ教とは?ゾロアスター教との関係や宇宙図まで解説 (雑学サークル)
マニ教概説・序説(KHOORA SOPHIAAS)
グノーシス主義/ヤルダバオト (幻想動物の事典)
「国内にマニ教「宇宙図」 世界初、京大教授ら確認」(日本経済新聞)
マニ教とは(コトバンク)
マニ教(Wikipedia)
(2022年7月19日)