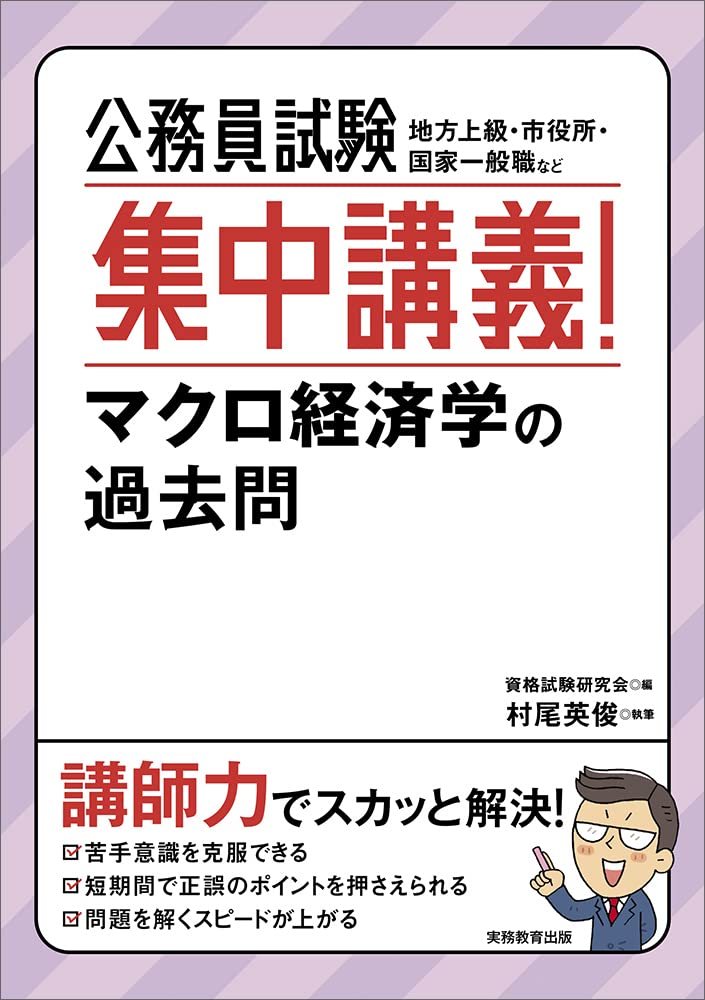「ヒンズー教を学ぶ」と題して、シリーズでお届けしています。ここまで、バラモン教、聖典ヴェーダについて解説しました。今回は、いよいよ、バラモン教から発展したヒンズー教そのものについて学びましょう。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
<概観>
ヒンズー教とは
ヒンドゥー教は、インド最古の宗教であるバラモン教を土台とした、インド発祥の多神教の民族宗教です。土着の神や民間信仰、仏教の教義を取り入れながら、変容・発展しました。地域や所属する集団が保持していた多様な要素を包括していることから、ヒンドゥー教に体系的な定義を与えることは困難ですが、逆いえば、ヒンドゥー教は、その多様性と寛容性を特徴としています。
語源・名称
「ヒンドゥーHindu」 の語源は、サンスクリット語(梵語)でインダス川の意味ですが、インドが植民地化された時代に、イギリス領インド帝国を支配した大英帝国が、インド土着の民族宗教を包括的に示す名称として採用したことから、「ヒンドゥー」の呼称が広まりました。ヒンドゥー教という名称もヨーロッパ人によって付けられた名前で、インドに逆輸入され定着し、「インド人の宗教」という意味です。正式にはヒンドゥー教で、慣用表記でヒンズー教と書かれる場合もあります。
宗教人口
ヒンドゥー教徒の数はインド国内で10億人を超え、その他の国の信者を合わせると約12億人とされキリスト教(25.1億人)、イスラム教(20.7億人)に次いで、世界で第3位です(ただし、世界の三大宗教には含まれない。ヒンズー教は特定の地域や民族に信仰される民族宗教であるから)。
アジア地域で信仰が広がっており、ヒンズー教徒が人口に占める割合は、インドでは80%以上、ネパールでは50%、バングラデシュでは14%、スリランカは15%とされ、マレーシア、シンガポールにも相当数の信者が住んでいます。インドネシアではバリ島に限れば人口の約9割を占めています。さらに、インド洋のモーリシャスや南太平洋のフィジー、南米のガイアナのように、インド系移民と在外インド人が多い国でも信者が多数います。
開祖・教義・組織
ヒンズー教には、キリスト教やイスラム教のような、明確な開祖をもたず、特定の体系的な教義もありません。また、キリスト教に見られるような教会制度や宗教的権威は存在せず、また預言者も居なければ、纏(まと)まった形の共通の聖典も存在しません。
<ヒンズー教の成り立ち>
紀元前1500年頃、イランからインド北西部に侵入したアーリア人は、ヴェーダ聖典を成立させ、これに基づいてバラモン教を興しました。紀元前5世紀頃に、ウパニシャッド哲学や仏教の隆盛をうけ、祭式中心の形式主義を批判された伝統的なバラモン教は、インダス文明の時代からインドやその周辺に居住する民衆に近い土着の神や思想、風習、民間信仰、さらには仏教の思想や制度を取り入れながら、ヒンドゥー教へと変容していきました。
ヒンズー教とバラモン教の境界線はあまり明確ではありません。というのも、インドは伝統的に歴史を記録する文化がないため、ヒンドゥー教の具体的な形成過程もいまなおあまりよくわかっていないからです。
ヒンズー教は、仏教誕生後の紀元前5 ~前4世紀に顕在化し始め、前2世紀〜後3世紀ごろに成立したとされています。その間、1世紀頃までには、旧来のバラモン教の勢力は失われたとされ、地域の民族宗教・民間信仰を取り込んで行く形で、ヒンズー教のシヴァ神やヴィシュヌ神の地位が高まっていったとされています。それも、異教徒をヒンズー教徒に改宗させるために、ヴェーダの時代に地位が低かったヴィシュヌ神を主神に祭り上げたとも言われています。こういう形で、ヒンズー教は、多くの神々や教派を取り込んで発展していったのでした。
その後、4世紀までに、カースト制度と結びついて社会に定着し、さらに、当時の支配王朝のグプタ朝(320~550年)は、ヒンズー教を国教としました。これが、インドからやがて仏教が消えていく一因とされ、ヒンズー教は4~5世紀には、当時優勢であった仏教を凌ぐようになりました。(14世紀になると、ヒンズー教は仏教を包含し始め、インドの仏教は、ヒンズー教の1派ともみなされた)。
こうして、ヒンドゥー教は、完全に確立され、インドの民族宗教として民衆に信仰され続けました。10世紀になると、北インドにイスラム勢力が侵攻してきましたが、北部(現在のパキススタン)だけで留まりました。
<ヒンズー教の神々>
ヒンドゥー教は、その成立の過程で、バラモン教や民間信仰の神々を吸収してきたので、多神教であり、数千もの神々が信仰されています。バラモン教では、聖典「ヴェーダ」を基本とし、軍神インドラ、天空神ヴァルナ、火の神アグニの三大神に加えて、後期には創造の神ブラフマーがとくに崇拝されていました。その後、バラモン教の神の名の下、インド各地で信仰されていた土着の神々(シヴァやその妻ドゥルガーなど)や、人気のある英雄たち(クリシュナ、ラーマなど)の物語を取り込み、さらにバクティやタントラなどの思想が加わることで、ヒンドゥー教はインドの民族宗教として次第に形を整えていったのでした。
また、ヒンズー教は寛容性のある宗教で、その間、人々は好みや傾向によって、崇拝対象を決めた一方で、自分が信仰しない神々も、決して排除されず、劣位ではあるが敬うべき神とされたことから、大きな宗教間の対立も起きませんでした。
- ヒンドゥー教の3大神たち
多神教のヒンドゥー教のなかでも重要な神は、三大神とされるブラフマー、ヴィシュヌ、シヴァで、それぞれ創造・維持・破壊の三つの機能を司っています(ただし、現在では、ヴィシュヌとシヴァが二大神として並び称されている)。また、3大神の妻や化身、共に活躍する神、さらに3大神の子神も信仰され、多くの物語や伝説に登場します。
ブラフマー(創造神)
ブラフマーは、宇宙創造の神、世界に実在の場を与える神で、ウパニシャッド哲学の最高原理ブラフマンの神格化、擬人化された存在(仏教では梵天)で、バラモン教の時代には大いに崇拝されました。しかし、ヒンズー教の時代、その抽象的な性格もあって、庶民の間では幅広い信仰の対象となることはありませんでした。
サラスヴァティ(サラスワティー)は、ブラフマー神の神妃(妻)で、芸術と学問、智慧、弁説、音楽の神として崇敬されています。(北伝)仏教では、弁才天です。
ヴィシュヌ(維持神)
ヴィシュヌは、世界(宇宙)を維持する神、慈愛の神、平安を司る神で、10大化身と呼ばれる多数の分身を有することで知られています。その中で最も有名なヴィシュヌの化身が、叙事詩「マハーバーラタ」の英雄・クリシュナや、叙事詩「ラーマーヤナ」で大活躍するラーマです。また、釈迦(ブッダ)も、ヴィシュヌの9番目の化身とされています。なお、ヒンドゥー教でのブッダは、「神々の敵を迷わせ破壊するために、異教を説く者」として登場します。なお、仏教はヒンズー教の一派とされています。
元来、ヴィシュヌ神(和名は毘紐天、盧遮那(毘盧遮那)は,バラモン教にあっては,数多くある太陽神の一つにすぎませんでしたが,やがて,各地の土着のさまざまな最高神(およびその神妃)との習合を重ね、シバ神と並んで,ヒンドゥー教最大の神へと転身していきました。
ラクシュミーは、ヴィシュヌの妻(神妃)で、ヴィシュヌ神の富と幸運を司る、富と幸運の女神、美の神として崇敬されています。仏教においては吉祥天と呼ばれています。
シヴァ(破壊神)
シヴァ(シバ)は、破壊と死、創造と再生を同時に司る神で、宇宙(世界)を創造し、その寿命が尽きた時に、宇宙を再創造するために破壊、破滅させます。また、性愛の神として、生殖や豊穣を司る神でもあり、シヴァの象徴はリンガ (男根像)でした。この結果、シバはリンガ、その神妃は性力(シャクティ)として崇拝の対象となりました。シヴァ派の寺院では、リンガ(男性器)とヨーニ(女性器)の交合像をかたどった、性交した状態の御神体が安置されています。
さらに、シヴァは、「ヨガを創始した神」、「最初のヨギー(ヨガをする人)」と言われ、「第 1 の修行者」を意味する「アーディヨーギー・シヴァ」とも呼ばれています。シヴァの別称であるナタラージャは、「踊りの神」、「舞踏神」で、アーサナ(ヨガの体位)につながる振付(ポーズ)を108種考えたとされています。加えて、シヴァ神の化身であるマハーカーラは、(北伝)仏教において大黒天として信仰されています(和名は自在天)。チベット仏教でも信仰対象となっています。
(シヴァ神の変遷)
シヴァは、アーリア人が西北インドに侵入する前から、崇拝されていたとみられていたことから、バラモン達は、非アーリア人の神であるシヴァの礼拝に、最初は反対していたとされています。
このため、ヴェーダ時代(前1500〜前500年)には、シバは個性の弱い神でしたが、やがて、諸地方の土着の宗教と習合を重ねるにしたがい、「イーシュヴァラ」(最高神/自在天)、「マヘーシュヴァラ」(大自在天)等の伝統的な絶対者概念が異名として取り込まれると、世界を主宰する神、世界を破壊する恐るべき神(破壊神)とされるようになりました。
また、各地の地母神もシバ神妃として習合されるに至り、サティー、パールヴァティー、ドゥルガー等のシヴァ神の妃も併せて崇拝されるようになりました。パールヴァティーは、ヒマラヤ神の娘で、シヴァの神妃(妻)です。穏やかで心優しい愛と美の神とされています。その化身には、美しい戦いの女神「ドゥルガー」、荒々しい殺戮の神「カーリー」などがいます。
ガネーシャは、シヴァの長男で、富、智慧、幸福(繁栄)の神とされますが、鼠に乗った象の頭を持つユニークな姿から、最も有名なヒンドゥー教の神の一柱となりました。(北伝)仏教では歓喜天(聖天(しょうてん))の名で知られています。
スカンダは、シヴァの次男で、ヒンズー教の軍神です(別名クマーラ)。ベーダ文献にその名がみられていましたが、ヒンズー教の叙事詩時代に入ると重要視されるようになりました。一方、火神アグニの子との説もあり、幼児の病魔を生み出す疫病神という側面もあります。仏教に入っては、仏法守護の神、韋駄天(いだてん)となったとされています。
トリムールティ
ヒンズー教では近世において、宇宙の創造神ブラフマー 、宇宙の維持神ヴィシュヌ 、宇宙の破壊神シヴァを「三神一体(トリムールティ)」の最高神として崇拝する立場があります。これは、宇宙の創造、維持、破壊という三つの機能を3人組という形で神格化した考え方です。
- ヒンズー教の他の神々
カーマ(カーマデーヴァ)
カーマとは、ヒンドゥー文献において、欲求(欲望)、意欲、愛欲を意味する言葉ですが、「リグ‐ベーダ」では宇宙(世界)創造の原動力としてうたわれ、のちに、インド神話で愛の神、愛欲の神とされました。快楽の女神ラティを妻(妃)とし、人間の愛欲、恋愛、性愛、和合をつかさどります。
インドラ・ヴァルナ・アグニ
バラモン教時代、三大神とされ、神々の中心であった雷神インドラ、天空神ヴァルナ、火神アグニは、ヒンドゥー教が成立した時代になれば影が薄くなり、神々の中心の座はシヴァやヴィシュヌなどに譲ってしまいました。
ヒンズー教においては、代わって、世界を守護するために、四方八方にそれぞれ神が配置されるローカパーラ(世界守護神)の中の一柱の神の地位に落ち着くと同時に、仏教には仏法擁護の神(天部)として、同じ方角神の役割をもって取り入れられました。
インドラ 東方守護の帝釈天
ヴァルナ 西方守護の水天
アグニ 南西守護の火天(かてん)
ローカパーラは、インド神話の神の名称ですが、「世界を守るもの(世界守護神)」の意味で、4方位(8方位)のそれぞれにある神の総称として、活用されています。また、仏教における十二天の原型とされています。
<ヒンズー教の教典>
ヒンドゥー教の代表的な教典・聖典(文献)は、バラモン教から引き継いだ聖典「ヴェーダ」と、百科全書的な「プラーナ文献」、それに英雄たちが活躍する二大叙事詩「マハーバーラタ」「ラーマーヤナ」です。
古代インドにおいて、聖典はシュルティとスムリティに分類されました。シュルティとは、サンスクリット語で「天啓聖典」を意味する、神より啓示された聖典のことをいい、スムリティは、「記憶されたもの」の意で、聖仙や偉人の著作による聖伝書をさします。ヒンズー教の聖典である「ヴェーダ」はシュルティで、「プラーナ文献」と2つの叙事詩はスムリティに属します。これらの聖典は、何世紀にもわたり口承にて記憶、編纂され、世代を超えて伝承され、後に一部文字に起こされました。
- ヴェーダ
ヴェーダは、紀元前15世紀頃から紀元前5世紀頃にかけてまとめられたバラモン教とヒンドゥー教の聖典で次の4部門で構成されています。
サンヒター(本集)
ブラーフマナ(祭儀書)
アーラニヤカ(森林書)
ウパニシャッド(奥義書)
最初の2つ(サンヒターとブラーフマナ)はカルマカーンダ、残りの2つをジュニャーナカーンダと呼びます。カルマカーンダ(行いの部・施祭部門)は生活においての規則や規律が、また、ニャーナカーンダ(知識の部・哲学的、宗教的思索部門)には自分自身の本質についての知識が書かれています。
また、厳密に言えば、4部門は、さらに各々「リグ・ヴェーダ(賛歌)」、「サーマ・ヴェーダ(歌詠)」、「ヤジュル・ヴェーダ(祭詞)」、「アタルヴァ・ヴェーダ(呪詞)」の四ヴェーダに分割され、ヴェーダは4×4の16種類からなります。
さて、ヴェーダ4部門のうち、ウパニシャッドは、ヒンドゥー哲学の基礎であり、シュルティ(天啓聖典)の中でも特に優れた書であるとされ、その基本理念はヒンドゥー教哲学や信仰にも継続的に影響を与え続けて言われています。ウパニシャッドは、1冊の書物の名前ではなく、約200以上ある書物の総称をいい、ヒンドゥー教では、108のウパニシャッドが列記されているムクティカー・ウパニシャッドを伝統的に認めてきました。そのうち最初の10から13が最も古く、最も重要なものとして、主要という意味で、ムキャ・ウパニシャッドと呼ばれています。
- プラーナ文献
プラーナ文献とは、サンスクリットのプラーナム・アーキヤーナム(「古き物語」「古伝説」の意)の略称で呼称される一群のヒンドゥー聖典の総称で、「第5のヴェーダ」とも呼ばれます。
内容は、ヒンドゥー教諸神の神話・伝説、賛歌、祭式、また祖霊祭、神殿・神像の建立法、カースト制度、さらには哲学思想、医学、音楽など、ヒンドゥー教のあらゆる様相を示す百科全書とも言われるほどあらゆる分野を含みます。なかでも、ヒンドゥー教の主神ビシュヌ神やシバ神を賛美する内容が際立っています。これらはヒンドゥー教の教えを、物語を通して人々に伝えるという役割を担い、布教の中心となっています。
プラーナ文献はおよそ西暦300年あたりから編纂され始めたとされていますが、その多くの著述は、天の啓示を受けて、伝説上のリシ(聖仙)、ヴィヤーサ が伝えたされています。歴史的にみれば、当初、紀元前5〜3世紀ごろのバラモン教時代に伝えられた神々やリシ(聖仙)、太古の諸王に関する神話・伝説・説話が中心だったと考えられ、ヴェーダの伝承者とは別に存在したとされるスータと呼ばれる吟遊詩人などの語り部集団によって伝承されました。
やがて、バラモン教からヒンドゥー教へ変わっていく歴史の流れの中で、台頭してきた巡礼地などに集まる身分の低い僧職らが、ヒンドゥー教のあらゆる要素を取り入れ、挿入、改編を繰り返し、およそ4世紀から14世紀にかけて現在のプラーナを大成、定着させたとみられています。
- ヒンドゥー叙事詩
ヒンドゥー教の代表的な二大叙事詩とは、英雄たちが活躍する「マハーバーラタ」と「ラーマーヤナ」で、。ギリシャの叙事詩「イーリアス」と「オデュッセイア」としばし較される秀作です。マウリヤ朝(前322年頃 ~前185年頃)の時代から形を整え始め、数百年かけて付加や変更が加えられた後、グプタ朝(320~550年頃)の時、現在の形態が完成したと考えられています。
マハーバーラタ
「マハーバーラタ」は、18編約10万詩節よりなるサンスクリット語の世界で最も長い叙事詩で、紀元前2世紀中葉〜紀元後1世紀末頃に原形ができたとみられています。伝説によると、リシ(聖仙・仙人)のビヤーサ(ヴィヤーサ)が書き、これを5人の弟子に伝えたとされていますが、実際は前10世紀ころから語り伝えられている間に整理され、現存の形になったのは4世紀ごろだと考えられています。
主筋であるバラタ人の2王族の不和から大戦争に至る話しは全体の5分の1ほどにすぎず、その間におびただしい神話・伝説が挿話として説かれ、ヒンドゥー教徒の信仰生活を実質的に規定してきと言われています。なかでも、「バガヴァッド・ギーター」(「神の歌」の意)は最も一般的なヒンドゥー教の聖典の一つとされ、時にウパニシャッド(奥義書)とみなされるため、シュルティ(天啓聖典)に数えられることもあります。
ラーマーヤナ
「ラーマーヤナ」は7編2万4000詩節よりなり、ラーマ王子の冒険を主題とする、一貫した文学作品ですが、「マハーバーラタ」と同様、その間に多くの重要な神話・伝説を含んでいます。成立は紀元3~4世紀頃で(実際は紀元前のはるか昔から伝えられていたとみられる)、詩人ヴァールミーキが、ヒンドゥー教の神話と古代英雄コーサラ国のラーマ王子の伝説を編纂したものです。この叙事詩は、ラーマ王子が、誘拐された妻シーターを救い出すべく大軍を率いて、ラークシャサの王(魔神)ラーヴァナに挑む姿を描いています。この戦いにおいて、ハヌマーンという猿の半神は、シーターを助けるために大活躍し、ラーマとともに人気を集めました。
<ヒンズー教の教義>
ヒンドゥー教の教義や宗教観、儀式の多くは、バラモン教以来の伝統を継承しています。たとえば、ヒンズー教は、神々への信仰と同時に、カルマと輪廻(輪廻転生)(サンサーラ)、その解脱という概念、そこから、身分(ヴァルナ)や職業(ジャーティ)までを含んだカースト制等を特徴(土台)としています。さらに、ウパニシャッド哲学の、人間の本質(我)と、宇宙の本質が一致するという梵我一如の思想も含まれます。
- カルマ・輪廻・解脱
カルマ(業)とは、人間の行為が善行・悪行に応じた、前世の報いとされる法則です。例えば、今世で苦しい思いをしているのは、前世の悪行が影響していると考えます。輪廻とは、人間の魂が死後に別の肉体に生まれ変わるというサイクルです。ヒンドゥー教でも、「カルマによってどのような人生を送るのかが決まる」と信じられてきました。
現世でのよい行いが、よりよい来世を招くとされ、生き物、行為を超越する段階に達しないかぎり、永遠に生まれ変わり、来世は前世の業(行為)によって決定されます。信心と業(カルマ)によって、次の輪廻(来世)の宿命が定まるのです。具体的には、カースト(ヴァルナ)の位階が定まります。これが、因果応報の法則(善因楽果・悪因苦果・自業自得)であり、輪廻の思想と結びついて高度に理論化され、インド人の死生観・世界観が形成されました。
- カースト制度
ヒンドゥー教の下でも、バラモン教以来のカースト制度は存続し、司祭階級バラモンを最上位として、クシャトリヤ(王族・戦士階級)、ヴァイシャ(農工商人・庶民階級)、最下層のシュードラ(被征服民の奴隷階級)に分けられ、4つの身分の分類(ヴァルナ)毎に、さらに細分化された世襲の職業別の集団(ジャーティ)(生まれ・出生)が形成されています。このカースト制をヒンズー教の中に確立させたのが、マヌ法典です。
マヌ法典
マヌ法典は、インド古来の生活習慣から生まれた、インドの古代法典(百科全書的な宗教聖典)で、ヒンドゥー教の規範の書(法典)となりました。マヌはヴェーダ神話では人類の始祖とされていますが、そのマヌが受けた神の啓示により成立したとされ,前200年―後200年ころ(2世紀ころが有力)に現在の形になったと推計されています。
マヌ法典は、12章2684条(2685詩句)からなりますが、インドで「法」は宗教、道徳、習慣などをも意味することから、単なる法律だけでありません(現代的な意味合いのある法律的規定は全体の4分の1でしかない)。
宇宙の開闢(かいびゃく)、万物の創造から説き始め、祖先祭祀、カースト制の厳守規則(カースト義務)や贖罪の方法、カースト制における各種の通過儀礼や日々の行事などが書かれ、最後に輪廻(りんね)と業(カルマ)および解脱について詳細に論じられています。法律的な項目としては、国王の義務など国家や国王の行政に関する事項、カースト制度に関する婚姻の規則や、財産の相続、裁判手続なども含んでいますが、バラモン階級を擁護する立場が全編を貫いており、バラモン中心の四種姓(カースト制度)の維持に貢献したとされています。
また、マヌ法典は、詩歌体をとり(韻文体で書かれ),その内容が理念的で文学的かつ教訓的な要素が多いために、インド人の生活のみならず、精神部分にまで深く根ざしているとされています。結果として、バラモン教徒(ヒンドゥー教徒)にとって、長く生活規範、人生の指針とされ、ヒンドゥー教の時代、その伝播とともに東南アジアの諸法典にも影響を与えました。一般のヒンドゥー教徒は、輪廻などの宗教観念を共有しつつ、長い歴史を経て生活に深く根付いた習慣や身分(カースト)に従って多様な生活を送っています。カーストによる差別は1950年にインド憲法で禁止されていますが、それでもまだ根強く残っています。
- 解脱(モクシャ)
バラモン教同様、ヒンドゥー教では、最終的には輪廻から脱する解脱(サンスクリット語で「モクシャ」)を人間にとって最大(人生最高)の目標とします。解脱とは、「輪廻の繰り返しから離脱すること」、カルマや輪廻から解放された状態がモクシャ(解脱)です。これらの考え方は仏教でも同じで、人間は無知や欲望によって、自分の本当の姿を見失ってしまいます。そのため、魂は輪廻のなかで苦しみ続けますが、解脱(モクシャ)を達成することで、永遠の平和を得ると信じられています。
輪廻の繰り返しから逃れる解脱の方法として、バラモン教では、そのための苦行が説かれました。また、そのために開拓されたのが、心身の鍛錬によって肉体を制御し、精神を統一する「ヨーガ(ヨガ)」の技法であり、ヒンドゥー教にも、修行法として引き継がれました。さらに、ヒンドゥー教では、解脱を実現する方法として、知識(ジャニャーナ)の道、行為(カルマ)の道、信愛(バクティ)の道という、神にいたる三つの道が強調されました。
知識(ジャニャーナ)とは、真理を学び知ること
行為(カルマ)とは、宗教的義務を怠らず遂行すること
信愛(バクティ)とは、神への献身
知識、行為、信愛の実践によって、真理と自己が一体であること(梵我一如)を認識し、輪廻からの解脱が目指されました。3つの道は、もともと、ウパニシャッド哲学で説かれましたが、ヒンズー教の時代に、民衆の日常的な信仰として、自覚されるようになったとされています。
バクティ運動
これらの神に至る3つの道のうち、とくに、神への信愛(バクティ)は、万人に実践可能であり,7~8世紀ころから大きな宗教運動となって、ヒンドゥー教全体の信仰の質を大きく変えたとされています。
バクティとは、もともと夫と妻のような、契約や約束によらない人間同士の信愛を示した言葉でした。それが、6~7世紀の南インドに始まり、中世以降に活発となったバクティ運動では、これを神との関係にまで拡大し「至高の神への絶対的帰依」、「神から恩恵を得るために要求されることは,他心なく一切を神にゆだね尽す信仰」と解され、最高神に帰依すれば最高神の恩寵によって救われると説かれました。
その振興には、イスラム教がインド各地に広がり、イスラームの平等主義的な一神教の考え方、さらには、スーフィズム(神秘主義)の影響があったとされ、12世紀の初めから15世紀にかけて、北インドを中心に拡大しました。加えて、ジャイナ教や仏教を排除し、インド古来の神々への信仰を復興させようという民衆による宗教運動とも相まって、バクティ運動は、16世紀までに全インドに浸透していきました。
こうして、バクティ運動は、ヒンドゥー教の主流となり、その主たる担い手になったのが、ヴィシュヌ神を至高の神とするヴィシュヌ派(後述)の信徒達で、文芸などを通じて,ビシュヌを叙事詩の英雄クリシュナと一体化する,熱烈な信仰が起こり、多くの大衆に受け入れられたのでした。また、バクティ運動を通じて、ヒンドゥー教はヴェーダ信仰から離れ、より現実的な民間信仰という面が強くなっていったと言われています。
<人生の3大目的>
ヒンズー教では、現世において、アルタ(富・実利)、ダルマ(法)、カーマ(性愛)を求めることが人生の三大目的(トリヴァルガ)とされています。
アルタ(富・実利)は、名誉、富、権力だけでなく、学問、土地、黄金、家畜、穀物、家財道具、友人を獲得し、獲得したものを増大させることを意味し、現世において追求されるものです。アルタは、役人の処世から、また、職業上の慣行をよく知る商人たちから会得すべきであるとされました。
カーマ(性愛)は、「カーマ・スートラ」によれば、「アートマンと結びついて、心に統御された耳・皮膚・目・舌・鼻の感覚器官が、それぞれの対象に生み出す心地よい活動」で「愛欲の快楽にあふれた実りゆたかな目的の感受」と定義つけられています。カーマはまた、単なる性欲の充足を目的とするものではなく、美的で文化的な要素を多く含むものであるので、文化的に洗練された粋人(すいじん)(ナーガリカ)やカーマを説く論書から学ぶべき事柄とされています。
ダルマ(法)とは、「祭式のように聖典の定めに従って行う」べきものであるとされ、私たちが考える「法律」よりはるかに幅が広く、宗教的、道徳的な義務も含むため、ダルマの追求には、現世だけでなく、来世も重要な意味を持ちます。また、ダルマは、ヴェーダを通じて、またダルマをよく知る者から学ぶべきであるとされています。
ダルマ、アルタ、カーマの三つをトリヴァルガ(trivarga)と呼び、それぞれ詳細に論じられ、以下のような代表的な論書(シャーストラ)が書かれました。
アルタ⇒「アルタ・シャーストラ」
カーマ⇒「カーマ・シャーストラ」
ダルマ⇒「ダルマ・シャーストラ」(⇒「マヌの法典」)
「トリヴァルガ」は、「カーマ・スートラ」の中で次のようにまとめて説明されています。
―――――
人は百歳の寿命をもつが、時期を分けて、それぞれ関連をつけて、互いに損なうことなく、人生の三目的(トリヴァルガ)を追求すべきである。少年時代には学問の習得など実利(アルタ)を、青年時代には性愛(カーマ)を、老年にはダルマと解脱を追求すべきである。寿命は移ろいやすいので、あるいは臨機応変に追求してもよい。ただし、学問の修得までは、禁欲を実行すべきである。
―――――
ただし、教義の面からみれば、アルタ(富・実利)、ダルマ(法)、カーマ(性愛)を実現は、人生の最高の結果を得られるとはされませんでした。トリヴァルガによって、来世で、天界に生まれることが最高の果報であり,結局,輪廻の中にとどまっているにすぎないと解されたのです。そこでウパニシャッドの思想家たちはさらに進んで,業・輪廻からの自由である解脱(モークシャ)を追求することが人生の最高の目的と考えました。したがって、アルタ(富・実利)、ダルマ(法)、カーマ(性愛)に、モークシャ(解脱)を加えて、四大目的とする場合もあります。
三大性典
一方、このトリヴァルガのなかで、特筆されるのが、カーマ(性愛)です。インドは、愛と性技巧の国という異名をもつ国で、古代インド人はこの方面をかなり熱心に探究しており、ヒンドゥー教においても、「生は性に通じるもの」でタブー視するものではありませんでした。そのため、性愛に関して、三大性典と呼ばれる「カーマ・スートラ」、「アナンガ・ランガ」、「ラティラハスヤ」のような性典も生まれました。
カーマ・スートラ
「カーマ・スートラ(愛欲の経典)」は、4~5世紀ごろに成立した古代インドの愛の経典で、全編男女の性愛に関する事項をサンスクリット語の韻文で記されています。「最高の禁欲と精神統一により,世人の生活に役立てるべく作られたもので,情欲を目的として編まれたものでない」と理(こと)わっていますが、、男女の性愛を通して、人生における「愛の研究」の重要性が説かれています。その内容は、接吻・抱擁・体位など性愛の技巧、処女との交渉と結婚、妻女、他人の妻、娼婦(遊女)について、求愛と結婚から強精剤,その他性欲を衰えさせる薬などのあらゆる事項を網羅しています。
ラティラハスヤ
「ラティラハスヤ(性愛秘義)」は、13世紀以前に書かれたとみられますが、成立年代は不詳で、精力を増大する薬,,女性の性感を高める薬などが示されています。また、女性を4タイプに分けて、その性的志向まで記しています。
アナンガ・ランガ
「アナンガランガ(愛擅)」は、夫婦の別離を防ぐことを目的として、16世紀頃に書かれたものですが、女性の性感を促し男性のそれを遅らせる薬や,強精剤の処方、乳房を大きくする薬など多彩な内容が含まれています。
<四住期制度>
ヒンドゥー教の独特の概念に、四住期(アーシュラマ)があります。これは、最終目標の解脱に向かって人生を4つの住期に分け、それぞれの段階ごとに異なる目標と義務を設定したものです。四住期は、学生期、家住期、林住期、遊行期に分かれています。なお、受胎から学生期までは、四住期に入らず、この間は一人前の人間とは見なされません。ただし、「マヌ法典」は、ヒンドゥー教のバラモン・クシャトリヤ・バイシャの上位三ヴァルナに属する男性の人生に四つの段階があると説いており、シュードラ及び女性には適用されません。
学生期
年齢は、ヴァルナによって異なりますが、ヴァイシャであれば12歳から23歳までの間にバラモンのもとで入門式を挙げ、学生期に入ります。入門式は第二の誕生といわれる重要な通過儀礼で、学生期(原則として12年)は、特定のグル(師匠)に弟子入りしてヴェーダを学習します。現在でいう就学期間に相当します。
グル(師)とは、インドではベーダ時代以来,精神的指導者として最上級の尊敬を受けました。また、グルはヨーガの修行を成就するためにも必要不可欠な存在として信仰の対象にすらなることもあります(グル信仰)。なお、この期間は、グルの下で聖典ヴェーダを学習する時期ですが、クシャトリアは武人としての技能の鍛錬や行政統治の実務の勉強も行い、ヴァイシャも世襲の職業に関する勉強も行うそうです。
家住期
学生期が終わると家に帰り、家業に務め結婚して家族を養う家住期に入ります。「カーマ・スートラ」は家住期を充実させるための経典で、家住期において家長は家業を繁栄させて大いに儲け、その金を喜捨することも重要と考えられています。この間はカーストの職業に専念し、神々と祖先の霊を供養します。男子をもうけて先祖の祭祀を絶やさないことが重要視されます。
林住期
家住期を終えると、家長としての義務を終えて隠居したのが林住期で、解脱に向けた人生段階に入ります。孫の誕生を見届けた家長は家を離れて、荒野や林に住み、質素で禁欲的、清浄な生活を営みことが求められます。
遊行期
人生の完成を求めるものは最後の遊行期に入ります。林住期を終えると住まいを捨てて、遍歴行者となって放浪し、解脱を目指します。これは行者となって一人旅立ち托鉢しつつ放浪しながら解脱を得るのです。
過去においても現在でも、全てのヒンドゥー教徒が四住期を全うするわけではありませんが、四住期は、理想的な男性の一生とされ、現在でも高級官僚や会社の重役だった人が、退職後行者となって放浪している姿は意外に多いと言われています。ちなみに仏教の開祖釈迦も当時のバラモン教の教えに従い、四住期に則った人生を送っています。釈迦は、男子をもうけた後、29歳で釈迦族の王族の地位を捨て、林間で修行をし、その後悟りを開いて布教の旅に出ています。
マヌ法典によれば、ヒンドゥー教のバラモン・クシャトリヤ・バイシャの上位三ヴァルナに属する男子は、入門式を受けると、「再生」するドヴィジャ(再生族)(二度生まれる者)とされました。これに対して、シュードラ(隷属民)と女性は、入門式を受けられず一度生まれるだけのエーカージャ(一生族)となります。女性は再生族である夫と食事を共にすることはなく、祭祀を主催したり、マントラを唱えることも禁止されていました。解脱を目指して修行するヨーガ行者も男性です。
<ヒンズー教の風習・慣例>
- 河川崇拝(ガンジス崇拝)
ヒンズー教では河川崇拝が顕著であり、水を使った沐浴の儀式が重要視されています。特にガンジス河(恒河)は水そのものがシヴァ神の身体を伝って流れ出て来た聖水とされ、川自体も女神であるため「母なる河ガンジス」として河川崇拝の中心となっています。ガンジス河には沐浴場(ガート)が設けられた聖地があり、ヒンズー教徒は、ガンジス河の水に頭までつかって罪を清め、あるいは水をお供えします。ネパールとインドのヒンドゥー教徒の住む地域には 、墓地は無く、火葬後に聖なるナルマダ川(インダス川上流の支流)に流す事が人々にとっては当たり前の葬儀となっています。
- 聖牛崇拝
多神教であるインド・ヒンドゥー教では、生き物も神であり、とりわけ、牛は神聖な動物(聖なる牛)として、また神の使者として、崇拝の対象です。牛は、神話にも度々登場し、たとえばシヴァ神の乗り物はナンディンという牡牛で、「ナンディン(乳白色の牡牛)神」となり、神聖化が進みました。牛は神聖であるがゆえに、ヒンズー教では牛を食べません(牛肉の禁食)。牛肉を食べることは宗教的な冒涜とみなされます。そのためインドでは、多くの地域で牛肉の販売や消費が法的に禁止されています。
ただし、古い時代のインドでは、牛を食べていました。それが、紀元前6世紀ころ、不殺生を説く仏教などの新しい宗教が台頭するなかで、動物を殺して食べないという考え方が広がり、牛が神聖視されるようになったと言われています。実社会でも牡牛(おうし)は移動、運搬、農耕に用いられ、牝牛(めうし)は(牛)乳を供し、乾燥させた牛糞は貴重な燃料(牛糞ケーキ)となっています。ただし聖別されているのは、主として瘤牛(コブ牛)で、瘤牛は神話にも出てくる聖獣であるので絶対に食べません。一方、同じ牛でも水牛は、崇拝の対象とはなっていません。水牛は、次々と姿を変える悪魔マヒシャの化身の一つであると信じられており、家畜として使役され、その肉は輸出品にされています。
また、ヒンドゥー神学では、牛の神聖性は輪廻と結びついています。ヒンドゥー教の輪廻の考え方は上下87段の階梯構造となっているそうですが、最上段の人間に輪廻する1つ前の段階が牛であり、牛を殺した者は輪廻の階梯の最下段からやり直さなくてはならなくなると言われています。さらに、ヒンドゥー神学者は牛には3億3千万の神々が宿るとし、牛に仕え、牛に祈ることはその後21世代に渡ってニルヴァーナ(涅槃)をもたらすとされています。
<ヒンズー教の主な宗派>
現在のヒンドゥー教には、ヴィシュヌ派とシヴァ派を中心に、シャクティ派やスマールタ派などいくつかの宗派があります。ヴィシュヌ派が最大で、シヴァ派と2派で信者の半数を占めています。両派は、互いの神を自分の神より下に見ることはあっても、排除しようとはしないので、両派間の宗教的争いといったものは起きませんでした。
- ヴィシュヌ派
ヴィシュヌと、その妃クリシュナなど多様な化身(アヴァターラ)を至高の神として崇拝する一派で、「マハーバーラタ」「バガヴァッド・ギーター」などを主たる典拠としています。ヴィシュヌ派の信徒達は、6〜7世紀に南インドで始まったヒンドゥー教のバクティ運動の担い手となり、ヒンズー教の拡大に貢献しました。
- シヴァ派
シヴァ神を最高神として崇拝する一派で、苦行、呪術、祭礼、踊り等を特色とし、比較的社会の下層階級に浸透していきました。シヴァ派、2世紀のクシャーナ朝時代には、既に大きな勢力となっていたとされ、5世紀ころに宗派として、明確な形をなし、6,7世紀以降,シバ派には独自の聖典,神学をもったさまざまな派が生じていきました。シヴァ派による「一者」概念の普及・探求は、ヨーガ学派や不二一元論などの哲学的発達にも寄与したとされています。
- シャクティ派
シャクティ派は、シヴァ派から派生した宗派で、シヴァの妃ドゥルガーまたはカーリーとその性力(せいりき)(シャクティ)の崇拝を特徴とします。シャクティとは「エネルギー、力」とりわけ「性力」を意味します。性力派と訳されることもあります。シバ神の妃(女神)たちを宇宙開展の根本的活動力(シャクティ)とみなして崇拝し、その女神とシバ神の合一を自らの身体において実現し、神通力と解脱を得ることをめざしています。シャクティ派の聖典はタントラとよばれ、7世紀ころから多数編纂されました。
- ヴィーラ・シヴァ派(リンガーヤト派)
12世紀には、同じくシヴァ派から新たに分派として、バサバを開祖とするヴィーラ・シヴァ派が登場しました。シバ神の象徴であるリンガを常に携帯し,身に着けたことから、リンガーヤト派とも呼ばれました。同派は、神の恩寵を重視し,カースト制度を否定し,偶像崇拝や巡礼など,外的な儀礼を廃止しました。
- ラセーシュバラ派
ラセーシュバラ(水銀)派は、水銀を服用し、身体を水銀所成にし,ヨーガを修することで,人は生前解脱に達することをめざす宗派です。水銀は、シバ神とその妃との結合から生じた不老不死の霊薬とされ、水銀を使用することによってシバ神と合一できるとされています。
- スマールタ派
スマールタ派は、他の宗派と異なり、特定の神のみを奉じることはせず、代表的な5神、ヴィシュヌ、シヴァ、シャクティ、ガネーシャ、スーリヤ(あるいは、ここにスカンダを加えた6神)を、不可分一体的な最高神として平等に奉じる宗派で、7世紀の初め頃に興ったとみられています。
スマールタは、スムリティ (伝承文献) 、特に「グリヒヤ・スートラ」に規定された祭式を行う者をさします。「グリヒヤ・スートラ」とは、マウリヤ朝の時代、ヴェーダ聖典の補助文献としてつくられたバラモン教経典の一つで、古くからあった家庭内の祭祀,儀礼が要約して述べられています。複雑な祭式が次第にすたれ,これに対して土俗的な神々が信仰の対象となったことから「グリヒヤ・スートラ」に規定された簡単な祭式によって尊崇されるようになりました。したがって、正統派のヒンドゥー諸学派はすべてスマールタ派に含まれます。
<関連投稿・サイト>
<参照>
What’s ヒンドゥー教? 3分でわかる! 世界五大宗教④
(2021.12.24、TRANSIT)
インド思想史概説
(野沢正信 、沼津高専 教養科 哲学)
シヴァ:ヨガと相互に影響を与え合ったヒンドゥー教における神
(Studio Lotus8)
仏教とヒンドゥー教の違いとは?
(Divership)
ミトラ教の歴史1
(東條真人)
ヒンドゥーの神々の物語③/ヴィシュヌ神と「桃太郎」の遠いつながり
(2022/03/18、ARTNEアルトネ)
ヴィシュヌの化身⑦仏陀とカルキ ヒンドゥー教の終末思想
(西遊旅行HP)
ヒンドゥー教の世界観が現われた天地創造の物語
(Peace in tour アジアの学び旅HP)
ヒンドゥー教
(ニッポニカ/世界大百科事典)
世界史の窓
Wikipedia
(2024年6月29日)