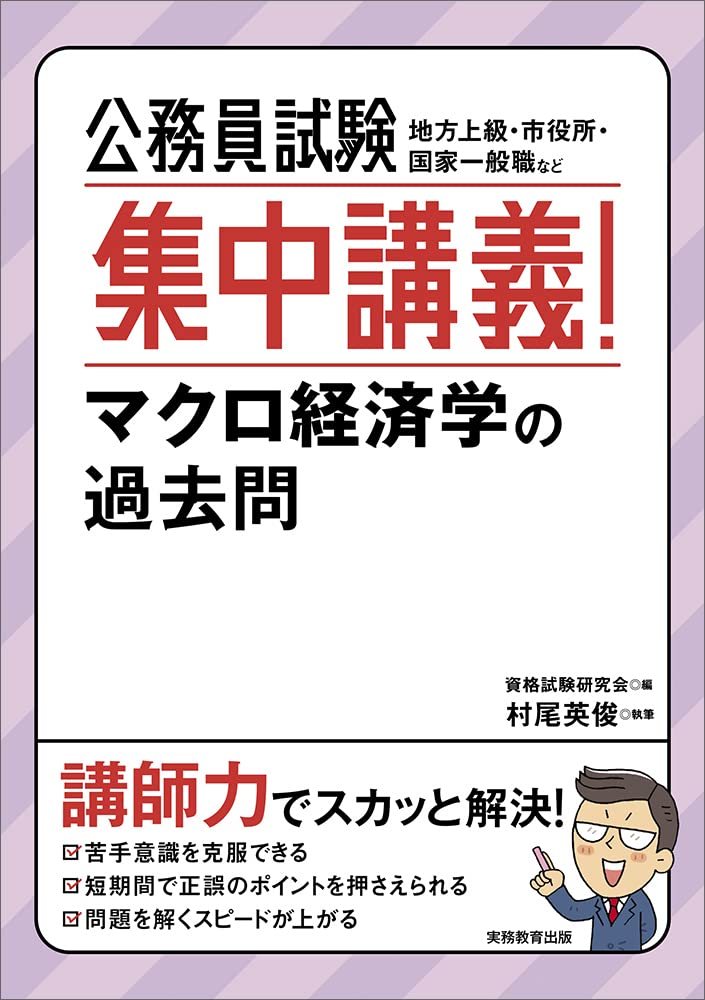私たちが学校で教えられてきた「明治憲法(悪)・日本国憲法(善)」の固定観念に疑いの目を向けた「明治憲法への冤罪をほどく!」を連載でお届けしています。今回は、第1章「天皇」の第11条から13条まで規定された天皇大権について考えます。天皇大権の規定は、天皇に絶対的(独裁的)な権力を与えたと一般的には批判されますが、実際はどうだったのでしょうか?とりわけ、天皇の統帥大権を規定した11条は、一般的に、軍部の独走を許し、明治憲法と当時の日本を「滅ぼす」原因となったとして批判される議論の多い条文です。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★
第11条(天皇の統帥大権)
天皇ハ陸海軍ヲ統帥(とうすい)ス
天皇は陸海軍を統帥(指揮・命令)する
<既存の解釈>
明治憲法下では立法権(議会)と統帥権(軍)は区別されていた。陸海軍は天皇直轄の機関として設計され、統帥権は、議会の統制が及ばないと解釈されていた(これを統帥権の独立という)。また、陸海軍は内閣を通さずに直接に天皇に帷幄(いあく)上奏(総理大臣に諮らず単独で天皇に意見などを申し上げること)し、指示を受ける立場でもあった。
1930年代に入ると、この「統帥権の独立」をたてに軍部による政治介入が強まり、政党政治も崩壊、やがて軍部独裁の政治体制に変質していった。
―――――――
この見解に対する<善意の解釈>をみる前に、当時の歴史的背景をみてみましょう。
<当時の政治の現場>
軍部独裁のきっかけをつくったとされるのが、陸海軍大臣の現役武官制と統帥権干犯問題でした。
◆ 陸海軍大臣の現役武官制
陸海軍大臣の現役武官制とは、行政を行う内閣の一員である軍部大臣つまり陸海軍大臣とその次官を、現役の軍人(武官、具体的には大将か中将)に限るとする制度です。
これは、軍とは無関係の政党出身の政治家(政党政治家)が、軍の行政上の責任者として、軍の方針や戦略、組織的な編成などに関して口を挟んでくるというように、軍部への政治介入を避けるために考案された制度です。
では、陸軍大臣と海軍大臣を現役の軍人に限るという制度がどうして軍部の暴走を許すのかというと、陸海軍大臣の現役武官制では、軍が人事権を実質的に掌握できるからです。
例えば、陸軍が軍備拡張要求を出して認められなければ、陸軍大臣が辞職し、陸軍はその後任を推薦しないと主張します。そうすると、陸軍が大臣を出さなければ、組閣(内閣を作ること)できないので、内閣は総辞職せざるを得ない事態にまで発展してしまうのです。
しかし、もし現役の将官でなくても陸海軍大臣になれるということであれば、予備役や退役した大将や中将は大勢存在するので、たとえ軍部の反対があっても首相は人選に困ることはありません。
軍部大臣現役武官制は、一時廃止されていた時期もありましたが、1936(昭和11)年に復活してからは、軍部が後任をちらつかせては内閣を牛耳るようになったのです。現役の軍人一人の力でも倒閣できてしまうわけですから、政府が軍部の意向に左右される軍部独裁を許すこととなってしまいました。
◆ 統帥権干犯問題
当時の浜口雄幸内閣が1930年に調印したロンドン海軍軍縮条約(軍艦保有量を制限する日米英条約)に関して、陸軍は「統帥権の干犯である」と、次のように主張して政府を激しく批判しました。「軍備の削減は直ちに軍事作戦に関わること、すなわち統帥権に関わることであるから、軍縮条約を天皇の統帥権を輔弼(ほひつ)(補佐)する海軍軍令部の承認を得ずに内閣が結ぶのは、統帥権の独立を犯すものである。」
これが、統帥権干犯問題として一大政治事件に発展していったのです。条約は批准されたものの、浜口首相は右翼の青年に狙撃され(後に死亡)、翌1931年には満州事変が勃発し、以後、日本は戦時体制に入っていきました。
こうして、陸海軍大臣の現役武官制で政治的な地位を高めた陸軍は、統帥権干犯という憲法上の「欠陥」を利用して膨張し、日本を破滅的な戦争へ導いていったのです。まさに、明治憲法11条の「天皇は陸海軍を統帥(とうすい)す」という短い条文が、軍部に都合のいい解釈を許し、軍の台頭を招いてしまったと言えるでしょう。
では、帝国憲法を起草した伊藤博文と井上毅が、天皇の統帥大権(11条)を定めた際、何を考え、何を期待したのでしょうか?
<善意の解釈>
もともと、統帥権は、「軍は政府から独立した公共性を持つ国家の軍隊であるから、天皇が統帥する」と象徴的な規定でした。
明治憲法の起草者、伊藤博文もその憲法解説書「憲法義解」の中で、「太古において、歴代の天皇は内外に事が起これば、自ら兵を率い、あるいは皇子皇孫を代行に立て征討を行い、国家の安寧を保持してきた。維新の後、兵制を改革し、参謀本部(軍令部)を置き、天皇自ら陸海軍を統率されたことで、かつての威光を再び取り戻すことができた(要約)」と述懐しています。
この伊藤の言説から、「統帥ス」とは軍隊の指揮・命令権を持つという意味ですが、統帥権を実質的に行使するのは、天皇ではなく、陸海軍の現場のトップである陸軍参謀部長と海軍軍令部長であることがわかります。
また、この統帥大権は、戦略や作戦に関わる陸軍参謀本部と海軍軍令部の問題であり、内閣とは直接の関係ありませんでした。内閣が扱ってきたのは、予算が絡む陸海軍の軍備や兵員についてでした。
原内閣(1918~21)から浜口内閣(1929~31)まで、内閣(政府)は、この予算面を盾にして軍部に対する支配権を強め、軍縮を断行するなど、シビリアン・コントロール(文民統制)を実現してきました。浜口首相に至っては陸軍大臣も兼務した程です。
しかし、1936年に軍部大臣現役武官制が復活すると、軍部が政治的意思を持ち、統帥権干犯問題など軍の都合のよい解釈で、政治にまで圧力をかけ、内閣を倒壊させるまで力を持ってしまったのです。
さらに、天皇は「君臨すれども統治せず」を志向され、特に昭和天皇は陸海軍に直接的な指示を下すことはほとんどありませんでした。この点からも天皇は象徴的な役割を担われてきたことがわかりますが、結果として、軍部はなにものにも制御されることはなく暴走していきました。要するに、軍国主義は、帝国憲法そのものが招いたのではなく、憲法を運用する側が作り出したといえます
条文が極めて簡潔な帝国憲法
帝国憲法は、制定当時、諸外国から高く評価されました。その要因の一つが、条文の簡潔さにありました。伊藤博文ら帝国憲法の起草者は、大日本帝国憲法を時代を超えてものにするために、すなわち、時代の推移に応じて、柔軟に運用できるように、条文を可能な限り簡潔にするという手法をとったとされています。
ただし、その反面、「統帥権の独立」条項(第11条)のように軍部の政治介入を許してしまう原因ともなったり、1条や4条に見られる憲法学者の独特な解釈を招いてしまったりしたことも事実です。
<天皇の統帥大権の実際>
ここで、日清戦争と日露戦争において、明治天皇が、軍をどのように統帥(指揮・統率)されたかをみてみましょう。
◆ 日清戦争
日清戦争において、1894(明治27)年8月の宣戦布告時、天皇は、列強の介入を憂慮され、日清開戦に消極的であったと言われています。「今回の戦争は、自分としては不本意であり、閣臣が戦争は避けられないと奏上されたので 許しただけである」と述べられたとの記録が残されています。
しかし、戦局が進展するなか、9月からは大本営が進出した広島に常駐され、積極的に戦争指導に携わられました。日清戦争遂行上の最高国策は、天皇出席の御前会議(通算7回)で,軍事作戦については天皇が大元帥として出席する大本営御前会議(通算約90回)で 決定されました。
双方の御前会議に出席したのは、明治天皇、首相伊藤博文、陸相大山巌、海相西郷従道、それに参謀総長、参謀本部次長、海軍軍令部長,および山県有朋(第1軍司令官)でした。この8名あるいはこれに陸奥外相を加えた9名が、日清戦争の最高指導部でした。
これらの頻繁な御前会議,それに天皇との会談を通じて、当時の首相伊藤博文が全般的な戦争指導権を握りました。伊藤首相は、軍事事項にも介入して軍が独走しそうな場合はこれを阻止し,国務による統帥の制御を行ったとされます。例えば、1894年11月、大本営の命令に反して第1軍司令官山県有朋大将が独断で中国領土内での更なる進攻を指示した時、山県を召喚した事件はその代表例でした。
御前会議の間、天皇は、軍の指揮に口は挟まず,一度も戦争の作戦に干渉しませんでした。天皇の親臨、親裁の形をとりつつも、政府主導での政戦両略一致が貫かれたのでした。
◆ 日露戦争
日露戦争においても、明治天皇は開戦に反対であったと言われています。「今回の戦いは朕が志にあらず。しかれども事、すでにここに至る。之を如何ともすべからざる」という述べられたそうです。
1903(明治36)年6月、伊藤博文、山県有朋、松方正義、井上馨,大山巌の元老と、桂太郎首相,小村寿太郎外相,山本権兵衛海相,寺内正毅陸相が集まった御前会議で,対露交渉の基本方針が討議、決定されました。
同年12月に,元老・閣僚会議で戦争準備に着手され、直ぐ後の参謀本部,海軍司令部合同会議で作戦計画が決められました。その後も日露交渉が重ねられ,開戦必至となったなかで,1904年1月の御前会議でロシアへの最終提案が、2月の閣議と御前会議で国交断絶の最後通告案が決定され,6日後に宣戦布告に至りました。
ここでも,御前会議(通算4回)で最高方針が決定され,戦争指導は開戦から講和にいたるまで,元老の承認の下で桂首相・小村外相ラインが牽引して行われました。元老・閣僚が指導権を握って統帥部をも統制下におき,政略優先で政略と戦略の一致が保たれたのでした。
このように,明治の日本は、日清,日露の両戦争ともに、元老(長老)と内閣=政府が一貫して主導して、御前会議における最高方針は決定されていました。たとえ、政府と統帥部の対立が発生しても、内閣=政府の統率下にあって統帥権は運用されました。
発言力を強化した軍部が、政党政治の進展に対抗して、独自の結束をかため、内閣から独立した勢力として台頭してくるの日露戦争後、とりわけ1930年代になってからでした。
以上、天皇の統帥大権についてみてきました。帝国憲法では、続いて、天皇の軍編制大権(12条)、天皇の宣戦・外交大権(13条)を規定しています。これらはいわば統帥大権と密接に関連する権限といえます。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★
第12条(天皇の軍編制大権)
天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵(へい)額(がく)ヲ定ム
天皇は陸海軍の編成と常備軍の兵額(兵士の人数、兵力)を定める。
<既存の解釈>
天皇には、陸海軍の編成(軍隊や艦隊の編成及び管区・方面の設定等)と、常備兵員(給与、軍人の紀律、人数の規定等)など軍の編成大権があった。これらは、天皇の大権なので、議会の干渉を受けず、独断で行うことも可能であった。日本国憲法にはこのような規定はない。
―――――
これに対する帝国憲法の起草者、伊藤博文と井上毅の考えは真逆で、天皇は最終決定権者ですが、内閣や軍の意向を受けて大権を行使します。
<善意の解釈>
天皇は、軍編成大権を独断で行使することはなく、実際は、陸海軍の現場の長である陸軍参謀部長と海軍軍令部長などの輔翼(協力)の上で行使されました。
もともと、編制大権の行使については,公式には「責任大臣の輔翼による」とされていましたが、内閣制の発足以来,閣議決定の軍事勅令だけでなく、内閣から独立して帷幄上奏に基づく軍事勅令が出されていました。帷幄上奏者は、軍令機関の長(陸軍参謀部長と海軍軍令部長)や、陸・海軍大臣などでした。このことは、天皇が出す軍事勅令は、内閣や軍指導部の決定を受けて出されるということを意味しています。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★
第13条(天皇の宣戦・外交大権)
天皇ハ戦(たたかい)ヲ宣(せん)シ 和ヲ講(こう)シ 及諸般ノ条約ヲ締結ス
天皇は宣戦布告を行い、講和条約を結び、様々な条約を締結する
<既存の解釈>
明治憲法において、外国と交戦を宣告したり、講和や貿易や同盟に関する条約を締結したりする事は、全て天皇の大権に属していた。この天皇の宣戦大権と外交大権は、議会の賛同は得ることなく行使することができた。
―――――
本条に関しても、伊藤博文と井上毅は、議会のチェックを受けないという否定的な立場ではなく、天皇が独断で行うのではなく、担当大臣など実務者レベルの決定を尊重するという立憲主義的な観点を強調しています。
<善意の解釈>
君主は外国に対して国家を代表する立場にあり、君主自らが条文にある外交事務を直接行っていた時代もありました。しかし、立憲主義の進展により、実務は外務大臣など担当大臣の管轄に属するようになり、天皇は宣戦大権や外交大権を担当大臣の輔(ほ)翼(よく)(協力)により行使しました。これは、天皇は、戦争を始めるかどうか、または講和するかを直接判断することはなかったことを意味します。
<参照>
帝国憲法の他の条文などについては以下のサイトから参照下さい。
日本国憲法の条文ついては、以下のサイトから参照下さい。
<参考>
明治憲法の思想(八木秀次、PHP新書)
帝国憲法の真実(倉山満、扶桑社新書)
憲法義解(伊藤博文、岩波文庫)
憲法(伊藤真、弘文社)
Wikipediaなど
(2022年10月26日)