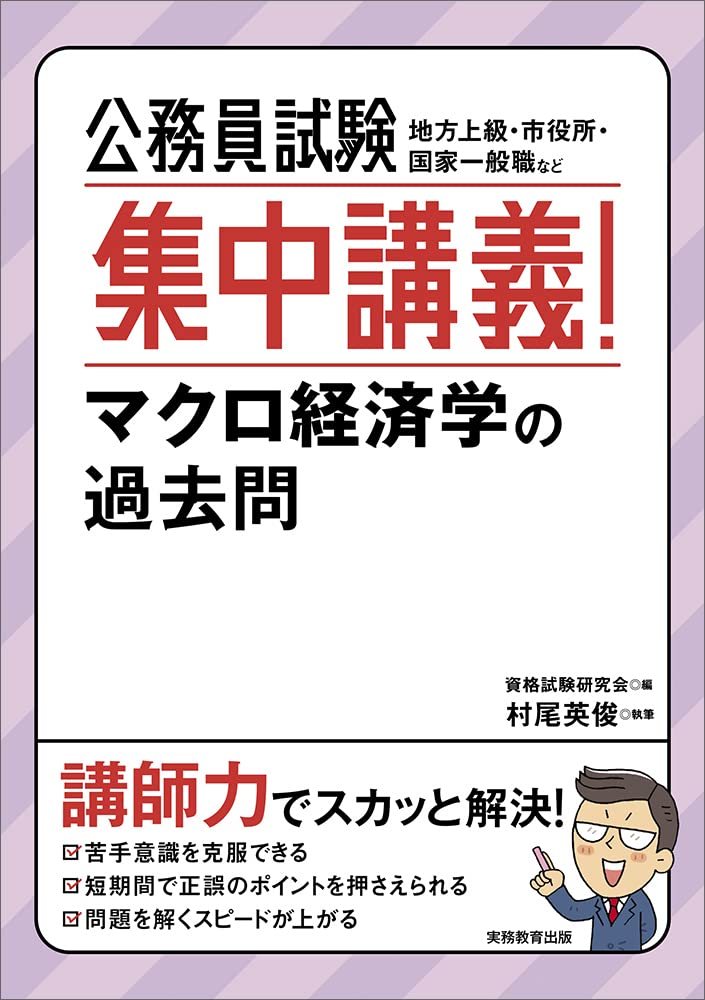自然を利用した再生エネルギーについて、連載でお届けしています。さまざまな種類がある再生可能エネルギーですが、再エネといえば、太陽光発電と言われるように、太陽光発電は、再生エネルギーのなかでも
もっとも知られています。今回は、そんな太陽光発電についてまとめました。
今回の再エネにおいては、初回に、総論としての再生可能エネルギーについて概説しているので、そちらも読み合わせ下さい。
○●
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
<太陽光発電の概要>
◆ 太陽光発電の可能性
地球が1年間に受け取る太陽エネルギーの総量は、現在の人類が1年間に消費するエネルギー総量の約3万倍にもなると言われています。 この膨大な太陽エネルギーは、人類のエネルギー需要を賄うのに十分な可能性を秘めており、太陽光発電は、カーボンニュートラルの実現につながる再生可能エネルギーの切り札として期待されています。
太陽光発電は、発電時に石油や石炭など有限の化石燃料を原料とせず、CO2(二酸化炭素)も発生させず、しかも、無尽蔵な太陽エネルギーを活用できることから、将来性の高い、今後の主力電源を担うエネルギーとして活用されています。家庭では屋根などで太陽光発電により電力を自家発電で賄い、企業の中には、大規模な太陽光発電施設で発電した電気を産業用に利用するなど普及が進んでいます。
◆ 太陽光発電とその仕組み
太陽光発電とは、太陽光がもたらす光エネルギーを、電力へに変換する発電方法です。太陽光を受けて電気エネルギーを発生する太陽電池を利用して発電します。
太陽電池は、太陽の光エネルギーを吸収して直接電気に変える、半導体で作られた装置で、プラスの電荷(電子の持っている電気の量)を多く含むp 型半導体とマイナスの電荷を多く含むn型半導体を張り合わせた(重ね合わせた)構造をしています。
この「太陽電池」を、複数、直列につないで、強化ガラスやフレームで覆った、一枚のパネル状の板が製品としての太陽光パネル(「太陽電池モジュール」)です。
半導体(太陽電池)に光が当たると、日射強度に比例して発電するわけですが、太陽光(光子)が太陽電池(シリコンなど半導体)に当たると、エネルギーによって束縛されていた電子が解放され、その抜けた穴として*正孔(ホール)が生じます(*光電効果)。
このとき、電子(-)はn型半導体に、正孔(+)はp型半導体にがペア(電荷の対)となって集まりますが、p型とn型の接合面では電位差(位置エネルギーの違い)が存在するため、発生した電子と正孔(ホール)が引き離され、電子はプラスに帯電している半導体へ、ホール(正孔)はマイナスに帯電している半導体へと流れます。この電子の流れ(電流)を利用して、電気を取り出す仕組みが太陽光発電です。
*正孔
正孔(ホール)は、半導体の結晶構造の中で、熱や光などによって、半導体の原子から電子が飛び出した後に残った「穴」のこと。
*光電効果
物質(特に金属)に光を当てると、物質から電子が飛び出す現象のこと(飛び出した電子を 光電子 という)。この現象は、光が粒子(光子)の性質も持つことによって説明され、アインシュタインが提唱した「光量子仮説」によって解明された。
太陽電池には種類がいくつかあり、材料によって、大きくシリコン系、化合物系、有機系の3つに分けられます。現在一番多く使われているのが、最も古くからある多結晶シリコン系の太陽電池です。この太陽電池では、電気的な性質の異なる2種類(p型、n型)の半導体を重ね合わせた構造をしています。その他、最近では有機系のペロブスカイト太陽電池の実用化も進んでいます(後述)。
なお、太陽電池には、「電池」という名前がついていますが、電気をためる機能はありません。
太陽電池の最小単位を「セル」、セルを複数組み合わせパネル状にしたものを「モジュール(太陽電池モジュール)」(=太陽光パネル)、モジュールを複数組み合わせたものを「アレイ」(ソーラーアレイ、太陽電池アレイとも呼ばれる)といいます。
電力の大きさ(出力)は「W=ワット」「kW=キロワット」(kW=1000W)という単位で表されます。
kW=瞬間的に流れる電気のエネルギー(電力)
たとえば、200Wのパネルを15枚使用した場合の総出力は、200×15=3000W=3kWとなります。
kWh=kWに時間をかけたもの(電力量)
kWh(キロワットアワー)は、1キロワットの電力を1時間使用したときの電力量を表す単位で、電気の使用量を示します。
発電「容量」と発電「出力」は一般的に同じものを指し、どちらもシステムの最大発電能力をkW(キロワット)単位で表したものです。また、総出力は、設置容量(容量)ともいいます。「発電量」は実際に発電された電力量をkWh(キロワットアワー)単位で表し、発電容量と発電する時間によって決まります。
◆ 太陽光発電の利用主体
太陽光発電は、一般家庭(住宅用)と産業用に大別され、家庭から発電所まで、幅広い用途で活用できる分散型電源です。
住宅用の太陽光発電とは、屋根やカーポート上に設置した太陽光パネルによって発電した電気を送るシステムです。
住宅の屋根に設置できる太陽光発電のシステム容量(太陽光パネルがどれだけ発電できるかを表す数値)は、1kWあたりの1日の発電量は2.7kWh(年間約1,000kWh)が目安とされています。
したがって、一般的な家庭の発電量が、家庭用システム容量(3〜5kW程度)の場合、1日あたりの発電量は約8.1〜13.5kWhになります。
そうすると、一般家庭モデルでの1日あたりの平均使用電力量(夜間の使用電力量も含む)は8.7kWhとされていることから、問題なく、太陽光発電で使用電力量をまかなうことができます。もちろん、実際の発電量は、地域、季節、設置角度、天候など、さまざまな要因によって変動します。
産業用太陽光発電とは、容量が10kW以上の発電システムを指します。ビルなどの屋上に設置された太陽光パネルによる発電や、広い土地を利用し多くの発電を行う大規模な太陽光発電施設など、さまざまなものがあります。
最近では、発電出力が1MW(メガワット) (=1000kW) 以上の大規模な太陽光発電設備(メガソーラー)の建設も増えています。
ただし、場所によってはさまざまな問題が発生しているため、2020年から大規模な太陽光発電事業に関しては「*環境影響評価法」の対象事業となりました。
*環境影響評価
その事業内容が環境にどのような影響を及ぼすかについて事業者が、事前に、調査、予測、評価を実施し、その結果を公表して住民や地方公共団体などから意見を聴き、環境保全の観点からよりよい事業計画を作ることを事業者に促す制度。
◆ 太陽光発電の利用形態
太陽光発電は、発電した電気の利用方法によって、自家消費型と売電型に大別できます。
「自家消費型」とは、自宅に設置した太陽光発電システムで発電した電力を、自分の家庭で消費することをいい、「全量自家消費型」と「余剰売電型」に分けられます。
「売電型」とは、発電した電力を、自分の家庭で消費するのではなく、電力会社に売ることを指し、仕組みとしては「全量売電型」です。
全量自家消費型
全量自家消費型は、発電した電気を、家庭、工場・店舗などでの自家消費にすべて使い切る方式です。太陽光パネルを個人宅や事業所の屋根や空きスペースに設置して、発電した電力をその場で直接利用します。発電した電気を直接使用することで、電力会社からの電気購入量が減り、電気代を削減できます。
余剰売電型
余剰売電型とは、発電した電気を自社で優先的に利用し、余った分を売電する方式です。自家消費型は、発電した電力を使い切ることを想定したシステムですが、自家消費しきれず、使い切れなかった電力会社へ売ることができます。もっとも、最近では、蓄電池と組み合わせることで全量自家消費を実現することも可能となっています。
全量売電型
全量売電型は発電した電気すべてを電力会社に売却する方式で、売電収入を得ることができます。家庭内(建物内)で電力を使うことは想定されておらず、自家消費する電気は、これまで通り電力会社から購入します。
自家消費型は、昼間も電気を多く使う工場や、オール電化住宅、日中在宅する家庭など、電力消費量が多い場合に特に向いており、家庭向けのシステムでは「自家消費型」が主流です。これに対して、売買型は、投資目的として利用される場合にみられます。
近年では、電気料金の高騰、売電単価の低下、非常用電力需要の増加、国際的な環境対策への貢献など、さまざまな要因から自家消費型の太陽光発電が注目されています。
<太陽光発電の普及>
◆ 太陽光の発電量と発電能力
エネルギー資源庁のデータによれば、2023年度の太陽光の発電電力量は、966億kWhで、総発電電力量(9854億kWh)のうち9.8%を占めています。
また、太陽光発電の潜在的な発電能力をみれば、日本国内における太陽光発電の賦存量は、79.8 億 kWと試算されています。賦存量とは、利用可能な総エネルギー量で、建築物や低・未利用地など物理的に設置可能な潜在量を合計したもので、理論上の最大潜在能力を示します。
さらに、理論的な賦存量に対して、導入した場合の発電能力を示す導入ポテンシャルと呼ばれる統計があります。これは、賦存量から、技術的・地理的(土地の傾斜や設置可能面積など自然条件)・社会的制約(土地利用などの制約)などの要因を差し引いた、現実的に導入可能な量を示します(技術的導入ポテンシャルと呼ぶこともある)。
太陽光発電の*導入ポテンシャルは、*発電設備容量で約27億4,595万kW、発電量換算で年間約3兆2,216億kWh(3,221.6 TWh)と、特に設備容量ベースでは膨大なポテンシャルが推計され、他の再エネを圧倒しています。
ただし、設置・運用コストや収益性など、経済的に見合うか(採算性)などを考慮すると(これを「経済性を考慮した導入ポテンシャル」と呼ぶ)、最大でも、設備容量で4億622万kW(406GW )、年間発電換算で5041億kWhとそれぞれ大きく縮小し、他の再エネと比較しても風力発電を下回るという特徴があります。
技術的導入ポテンシャル:27億4595万kW(3兆 2216億kWh)
経済的導入ポテンシャル:3832万kW〜4億 622万kW (473億kWh〜5041億kWh)
*導入ポテンシャルに関する数値は、環境省の2020年データに基づく。
*発電設備容量
現在、国内に実際に設置され稼働している発電設備の最大出力(kWやMW)の合計で、設備が最大限に稼働した場合の発電能力を示す(「現状」や「実績」を示す数値)。
◆ 太陽光発電の普及
2023年度、太陽光発電の総発電電力量に占める割合(電源構成比率)は9.8%でしかありませんでしたが、2012年の1%から、2019年6.7%、2020年7.9%、2021年8.3%と着実に増加しています。
また、太陽光発電は、再生可能エネルギーの中でもっとも普及しており、発電量に占める再生可能エネルギー比率22.9%(2023年度)のなかの約43%を占める主要なエネルギー源となっています。2020年度頃に太陽光発電量が水力発電量を追い越し、トップとなりました。
2012年から始まった固定価格買取制度(FIT)(後述)の認定容量の約75%を太陽光発電が占めており、再生可能エネルギー導入拡大の牽引役となっています。
政府が策定するエネルギー基本計画では、2030年までに、発電量のうち、再生可能エネルギーを36〜38%ととし、そのなかで太陽光発電の割合を、現在の9.8%から、14〜16%とする、また、2040年までに電源構成の40〜50%を再生可能エネルギーでまかなう目標が掲げられ、そのうち、太陽光発電は、23〜29%を占めると定められています。
今後、さらに太陽光発電を普及させるためには、産業用・事業用の大規模な導入も引き続き重要ですが、住宅用太陽光発電は、普及を加速させるための鍵となるとみられています。
国内の10kW未満の住宅用太陽光発電導入件数は、2019年に267万件に達し、戸建住宅総数(28,768万戸)の約9%を占める割合です。ただし、2012年7月のFIT制度開始直後は、年間平均で27.2万件と導入が大幅に増加しましたが、近年は、14.5万件と伸び悩みの状態で、今後、増加の余地はあります。
これに対して、国や自治体による支援体制が整備される見通しで、たとえば、2025年現在、一部地域で太陽光発電の設置義務化が施行されています。東京都では、2025年4月から、一定の条件を満たす場合に、新築住宅への太陽光発電設備設置が義務化されました。また、群馬県や京都府、川崎市でも、太陽光発電の設置義務化が進められています。
*設置義務対象者
東京都:年間都内供給延床面積が合計20,000㎡以上の住宅供給事業者
京都府:延床面積300~2,000㎡の建物を新築する施主
また、2025年現在、各地方自治体では住宅用太陽光発電の容量1kWあたり2~15万円の補助金を交付しています。初期費用を軽減できるため、利用者にとって導入の大きな後押しになります。
一方、政府も、太陽光発電の一般化に向けて2030年までに新築戸建住宅の6割に、太陽光発電設備の設置を促す方針を示しています。さらに、資源エネルギー庁では、発電設備の設置に対して固定資産税や所得税の軽減措置を実施しています。
◆ 太陽光発電の世界の潮流と日本の位置づけ
世界的にみても、太陽光発電は、世界各国で導入が進み、その発電電力量は、大きく増加しており、再生可能エネルギーの中心的な役割を担っています。2012年末の世界の太陽光発電の累積導入容量は、100GWを上回る水準でしたが、2022年に1.1TW、2024年には2.2TWに到達したと推計されています。
1テラワット (TW) = 1000 GW
1 ギガワット(GW) = 1000 MW
1 メガワット(MW) = 1000 kW(キロワット)
全エネルギーに占める再生可能エネルギーの比率は、2020年の約19.8%から2024年に32%に上昇し、同年末時点における再エネ設備の累計導入量の内訳は、太陽光が1865GWで42%を占めています。
日本は、かつて、ドイツとともに、太陽光発電の導入で、世界をリードしてきましたが、近年は、中国が、政府による強力な支援策と、大規模メガソーラープロジェクトの推進によって、圧倒的な存在感を示しています。
2024年の太陽光発電設備の*導入容量では、中国が突出して887.9GW、2位は米国の177.4GWで、日本91.6GWで、インド(97.3GW)に次ぐ4位となっています。
また、太陽光発電の*累積導入容量では、日本は、2023年度末時点で約7300万kW(73GW)と世界では、中国、アメリカに次ぐ第3位です。
*導入容量
実際に運転が開始された発電設備の総容量(実際に運転している容量)、制度上の導入計画や認定を受けた容量
*累積導入容量
実際に稼働している設備の合計、まだ稼働していないもの(今後運転される可能性のある設備)も含めて、これまでに導入されたと認定された設備の総容量。なお、稼働前の設備認定失効、未稼働案件の存在、古い設備の廃棄・交換により、累積導入容量が減少することもある。
もちろん、日本は、今も、世界でも有数の再エネ先進国として、温室効果ガスの削減に貢献しているとは言えますが、発電設備の適地不足などから、日本国内での導入ペースはやや鈍化傾向にあります。
<太陽光発電の特徴>
◆ 太陽光発電のメリット
環境に優しく、枯渇の恐れがない。
太陽光発電の最大の特長は、エネルギー源が無尽蔵で枯渇せず、クリーンである点です。太陽光発電は、発電時において、太陽光から直接電気を作り出すため、CO2の排出量はゼロです(ほとんど排出されません)。
もっとも、太陽光パネルの製造、運搬、設置、廃棄の過程で、CO2が発生しますが、化石燃料を使った発電(石油を燃焼させて電気を起こす火力発電)に比べて、CO2排出量を大幅に削減でき、かつ、SOX(硫黄酸化物)、NOX(窒素酸化物)などの大気汚染物質を発生させることがありません。
火力発電と太陽光発電で、1kWあたりの発電に対する温室効果ガス排出量を比較すると、化石燃料を使用する火力発電でのCO2の排出量は1kWhあたり約690g(519〜975g)、太陽光発電によるCO2の排出量は1kWhあたり17〜31(48)gと言われています。
具体的には、家庭での太陽光発電では、3kW〜5kWの太陽光発電システムの使用が一般的です。3kWの場合、その太陽光発電システムでの年間発電量は、3000kWhとされており、年間1950kgのCO2の排出量を減らすことができます。1950kgのCO2は、杉の木約140本分の吸収量に相当するそうです。
自家消費で電気代が安くなる。
家庭も企業も、太陽光発電で、自家消費(自家発電した電気を自宅で使用すること)すれば、電力会社からの購入電力量を減らせるため、電気代の負担を大幅に軽減できます。また、昨今の電力高騰対策にも有効です。
2025年現在の購入電力料金単価は、31円/kWhです。売電価格が15円/kWhであることを踏まえると、平均的な戸建て住宅の太陽光発電による自家消費では、年間5万7000円相当の電気代が安くなると試算されています。
電力市場価格の影響を受けにくい
家庭や企業の電気代も、太陽光発電の場合、電力市場価格の影響を受けにくい点もメリットです。たとえば、火力発電では、天然ガスや石油などの燃料価格の影響を受けます。近年、ロシアのウクライナ侵攻の発生により、燃料価格が高騰するなど、地政学的な影響を受けます。加えて、為替による燃料価格への影響も受けます。
これに対して、太陽光発電の原料は太陽からもたらされる光エネルギーなので、原料を輸入する必要はなく、自社の電源設備で発電できるため市場の影響をうけることはほとんどありません。
設置の規模や場所を選ばない
太陽光発電を導入しようとする場合、設置する場所の広さに合わせて自由に規模を決められるため、一般家庭から大規模施設まで、それぞれの施設に合ったシステムを設置できます(システムの規模に関係なく発電効率がほぼ一定)。
また、発電時に騒音を出さないので、日当たりの良い立地があれば、どこにでも設置できます。屋根や屋上などへの設置のほか、近年ではビルの壁に設置するケースや、駐車場のカーポート(屋根と柱のみで構成された簡易的な駐車スペース)を活用したソーラーカーポートの設置も増えてきています。
災害時の電源を確保できる
太陽光発電は、自家消費型であれば、地震や津波、台風や豪雨などの自然災害で、停電が起こっても、太陽光発電設備で発電している日中は、電気を使用することができます。
前述したように、一般家庭での平均電気使用量は約8.7kWhであり、家庭用の太陽光発電量が8.2〜13.7kWhであるため、災害時の電源として太陽光発電は有用です。さらに、蓄電池やエコキュート等の省エネ設備と組み合わせれば、夜間の自家消費や災害時の備えにもなります。
また、屋根や屋上に太陽光パネルを設置していない場合でも、停電などで電力会社からの電気供給が止まってしまった際、太陽光発電システムを備えた電力会社は、「自立運転機能」に切り替えることにより、太陽光発電システムで作った電気を供給できます。
売電収入を得ることができる(電気を売却できる)
太陽光発電で得られた電力は、*固定価格買取制度(FIT)等のもとで、電力会社への売却が可能です。この制度を利用すれば、太陽光発電で自家発電し、自家消費した後の余剰電力を電力会社に売却して、売電収入をえることができます。
*固定価格買取制度(FIT)
FIT制度は、太陽光をはじめ再生可能エネルギーで発電した電力を、資源エネルギー庁が設定した価格で電力会社が一定期間(10〜20年間)、固定価格で買い取ることを義務付ける(固定価格での買取が国により保証する)制度で、2012年7月から導入された。
ただし、太陽光発電における売電価格は、FIT制度が導入時の42円/k/Whから、年々下落傾向にあり、2025年現在15円/kWhに設定されています。FIT制度の導入当初は初期費用の回収を考慮した売電価格が設定されていましたが、初期費用が大幅に低下したことを受け、売電価格の段階的な引き下げが実施されているのです。
売電価格の引き下げによって、売電による収益性は低下してはいますが、自家消費による電気代の節約効果が高いことに変わりはありません。
◆ 太陽光発電のデメリットと課題
技術開発が進み、環境にも家計にも恩恵がある太陽光発電が100%普及しないのは、発電の際のデメリットや、普及に伴う課題(問題)を抱えているからです。
高い初期費用(高い設置コスト)
太陽光発電を導入するには初期コストがかかります。具体的には、太陽光パネルやパワーコンディショナ、接続機器を設置するための架台、その他の機器、工事費などが必要です。
住宅用太陽光発電の場合、設置費用の平均(2023年)は1kWあたり28.8万円です。家庭用の屋根には3〜5kWの容量の太陽光パネルが設置されることが多いため、初期費用は86〜144万円ほどかかると計算されます。
ただし、太陽光発電の導入平均費用は、製造技術の進歩や市場拡大に伴う製造コスト削減などによって、FIT制度導入当初の2012年と比較して、約6割まで低下しています。また、太陽光発電に対する行政からの補助金や、各種サービスを利用することで、初期費用を抑えることも可能になっています。
それでも、高い設置コストは、太陽光発電普及の大きな足かせになっているため、今では、電設備導入の初期費用を抑え、太陽光発電を低コストで導入できる、様々なモデルや制度が考案されています。
維持費がかかる
太陽光発電を設置した場合、初期費用のほかに、システムを維持するためには、メンテナンスや部品交換の費用(ランニングコスト)が発生します。メンテナンスなどの運転維持にかかる費用は1kWあたりで年間約5000円と試算されています。
ただし、太陽光発電のソーラーパネルは、長い保証期間があり約20年間は使用できると考えられます。パワーコンディショナは、15年程度での交換が目安となっています。
気候により発電量が変動する
太陽光発電は、天候や季節、日照時間など気候の影響を受ける変動制再生可能エネルギー(VRE)で、電力の供給に不安定さが伴います。
晴天の日は安定した太陽光の供給で発電効率が高まりますが、曇りや雨の日は発電できる電力量が落ちてしまうなど、毎日同じ発電量を得ることはできません。また、当然、太陽光のない夜間には発電することができません。季節によって発電量が変動します。日射量の多い夏に比べて、日射量が減少する冬は発電量も減少します。
太陽光発電そのものに蓄電機能はありません。太陽光発電で発電した電気は、通常、リアルタイムで消費しなければなりませんが、蓄電池など省エネ設備を併用して貯めておくことで、発電できない夜間や悪天候の日にも太陽光発電の電気を使えるようになります。
とりわけ、蓄電池を太陽光発電と組み合わせることで、通常は売電される余剰電力を貯めておいて、夜間や早朝に蓄電池から放電して自家消費する利用法が一般的です。また、停電が発生した場合でも、非常用電源として利用されます。
ここまでが、太陽光発電のシステム上のデメッリトですが、ほかにも運用上、いくつかの課題があります。
設置場所の適地不足
太陽光発電には、前述した「設置や場所を選ばない」という利点とは裏腹に、太陽光発電の普及に伴い、適切な設置場所の確保が大きな課題となっています。サイズや重量の制約により、発電設備が設置可能な場所には限りがあるからです。
とりわけ、太陽光発電で、火力発電などと同等の大きな電力を得るには、広大な面積が必要になりますが、日本は国土が狭く山間部が多いため、大規模な発電所を設置できる土地の確保がむずかしくなってきています。また、過剰な土地開発による土砂災害や景観破壊も問題視されています。
こうした、設置に適した場所が限られるため、国内の太陽光発電導入ペースは鈍化傾向にあります。今後は、新たな設置場所として、ビルの壁、水上やカーポート、荒廃農地といったスペースの転用も進められています。
電力系統の制約と出力抑制の必要性
大量の太陽光発電が導入された地域では、電力の安定供給を維持するための系統接続が制約されたり、出力抑制を強いられたりするという問題があります。
系統接続の制約とは、電力会社の送配電網(電力系統)が「満杯」の状態になってしまうことです。発電した電気を送るための送電線や変電所には、送れる電気の量に物理的な上限(容量)があります。特定の地域で太陽光発電が大量に導入されると、送電線が「満杯」になり、新しい発電所に接続できなくなったり、既存の発電所の電気も送れなくなったりする可能性がでてきます。
出力抑制の必要性は、余剰電力の発生から生じる問題です。電力は貯蔵が難しいため、常に需要(使う量)と供給(作る量)を一致させる必要があります。たとえば、太陽光発電で、晴れた日の昼間など、電気が多く作られすぎて、電気の供給が需要を大幅に上回ると、周波数や電圧が乱れ、最悪、大規模な停電につながりかねません。
そこで、これを防ぐため、電力会社は火力発電の出力を下げたり、他の電力会社管内に送電したりしますが、そうした措置をとっても供給が上回る場合、太陽光発電所に対し「発電量を抑えてください」「止めます」と、再エネの出力抑制(出力制御)の指示を出す場合があるのです。
実際、2014年に再エネ接続保留問題と、2018年と2022年に電力会社の出力制御問題が起きました。2014年9月、九州電力を皮切りに北海道、東北、四国、沖縄の電力4社が、自社の送電網に接続できる再エネの容量が限界に達したとして、FIT制度に基づく再エネ発電事業者からの新規接続申し込みの受け入れを一時停止しました。
また、2018年10月に九州電力が、また2022年4月には四国電力と東北電力が、好天で太陽光による発電が増える可能性がある一方、休日で企業の需要が少なくなる見通しのため、実際に稼働中の太陽光発電などに対して、再エネの受け入れを一時的に止める「出力制御」の指示を出しました。
これらは、固定価格買取制度(FIT制度)により再エネ導入が急速に進んだことが背景で、再エネの大量導入に対して電力系統の整備や運用ルールが追いついていないという構造的な課題です。
どちらの問題も、再生可能エネルギーの導入量が、既存の電力系統(送配電網)の受け入れ容量や需給バランス調整能力を超えつつある状況で発生しました。そこで、太陽光発電を大量に導入するためには、電気を効率よく運ぶための送電網の増強といったインフラ整備や、余った電気を貯めたり(蓄電池の導入)、他の時間帯や別の地域で使ったりする(地域間連系線の活用)ための新しい仕組み(運用ルール)が必要となってきます。
景観や生態系への影響
太陽光パネルによって、良好な景観が変わることや、景色が見えなくなる可能性があります。太陽光パネルからの反射光がまぶしいという苦情も出ています。また、重要な動植物が生息、生育する場所が消失や縮小することで、環境が変わり影響を与えてしまう可能性があります。
太陽光パネルの廃棄問題
太陽光発電の今後の課題として、2012年の固定価格買取制度(FIT制度)開始当初に導入された発電設備が寿命を迎え、事業が終了した後に発生している設備の放置や不法投棄があげられます。
日本での太陽光発電は、FIT制度が導入されたことで、加速度的に増加しましたが、太陽光パネルの寿命は約25〜30年とされているため、2040年頃には、太陽光発電設備から太陽光パネル等が一斉に廃棄されることが予想されています(2034~2036年の間に22~34万トンの発電設備が廃棄されるとの推計値も出されている)。
最終処分場の受入能力には限界があるため、大量廃棄による最終処分場のひっ迫が懸念されます。不法投棄されたパネルは、火災の発生や、太陽光パネルに含まれる鉛やカドミウムが、不適切な処分によって流出・拡散といった環境汚染のリスクがあるため非常に危険です。
太陽光発電パネルの大量廃棄問題は、主に2030年代に顕在化し、廃棄量のピークは2040年頃と予測されていることから、それぞれ「2030年問題」、「2040年問題」と呼ばれています。
廃棄処分量の減少に向けて、リサイクル技術の開発やリユース促進に向けた中古市場の拡大が求められています。行政側も、2022年から発電設備の修繕・撤去費用の積み立てを義務化しました。また、関係省庁による現地調査を実施し、設備管理が不十分な事業者に対する指導を強化しています。
<太陽光発電導入の経緯>
◆ 黎明期(~1990年代初頭)
太陽光発電は、1839年にフランスの学者が金属の板に太陽光を当てると電気が発生すると発見したことから始まったとされています。
日本では、1955年に初めて太陽電池が作られ、1958年には太陽光発電システムとして実用化がスタートしました。
その後、オイルショック後の1974年に現経済産業省が「新エネルギー技術開発計画(サンシャイン計画)」を打ち出し、愛媛県西条市に約1000kWの太陽光発電装置を設置し発電・配電の実証試験を開始するなどサンシャインプロジェクト等が立ち上げられました。
1980年代初頭には、香川県で世界初の本格的な太陽熱発電の試験が行われるなど、技術開発が進みました。
◆ 普及拡大と一時的衰退期
(1990年代半ば~2000年代)
太陽光発電は、発電コストが非常に高く、それまで一般家庭への普及は限定的でしたが、1992年から93年にかけて、日本初の住宅用太陽光発電システムが登場すると、国・地方公共団体等の助成や各電力会社の自主的な支援プログラム等などが導入され、徐々に普及が進みました。
とりわけ、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と、新エネルギー財団 (NEF)は、技術革新と市場拡大の両面で重要な役割を果たしました。
*新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
技術開発と産業化の推進を担った機関で、研究開発や大規模な実証プロジェクトを通じて、太陽光発電の産業競争力を強化させた。
*新エネルギー財団 (NEF)
NEFは主に普及促進と支援策の実施を担い、補助金制度の運営や啓発活動を通じて、一般市場への太陽光発電の普及・導入を促進に尽力している。
これらの結、設備価格は数十分の1になり、日本は生産量・導入量とも世界一となりました。2000年にかけての最盛期には、太陽電池出荷量は日本一国で欧州・米国・中国を足した数に匹敵していたほどでした。
しかし、2005年に新エネルギー財団 (NEF) の助成が終了すると、2007年まで国内市場は縮小し、世界一の座から転落しました。パネルの生産拡大は続きましたが、価格は下がらず、日本のパネル生産シェアは2010年には9%に低下した。2000年代後半には中国一強状態となっていきました。
◆ 飛躍的拡大期(2010年代~)
2011年3月の東日本大震災後、日本政府による自給エネルギーの確保と低炭素社会の実現という政策で、化石燃料や原子力に依存し過ぎないエネルギーミックス(さまざまな発電方法を組み合わせて電気を作ること)が推進されることとなりました。
2012年7月、太陽光を含めた再生可能エネルギーの固定買い取り制度(FIT制度)が導入され、普及の大きな転機となりました。
FIT制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定期間(10〜20年)固定価格で買い取ることを保証した制度で、事業としてのインセンティブが高まりました。
再生可能エネルギーで最も急速に普及が進んだのが太陽光で、太陽光発電事業への新規参入が飛躍的に増加しました。なかでも、事業用(産業用)の大規模太陽光発電所(メガソーラー)といった大規模な設備が急増し、商社や通信、建設など多様な業種や外国企業が売電市場へ参入しました。
ただし、強力な規制緩和で太陽光発電の流れは加速しましたが、その大量導入に対して、電力系統の整備や運用ルールが追いついていないという構造的な課題が浮き彫りになり、前述したように、2014年に再生可能エネルギー接続保留問題や、2018年、2022年には、電力会社の出力制御問題が発生しました。
また、政府の買い取り価格の段階的な引き下げで市場拡大のペースが鈍化すると、事業者の乱立の影響もあり、倒産業者数も増加、早くも淘汰の時代に入りました。
2022年4月には、FIP制度が新たに導入されました。これは、固定価格ではなく、売却した電気の価格(市場価格)に一定の補助金が支払われる制度で、市場価格に連動した、競争力のある電力源となることが目指されました。政府は、市場への統合を図るために、FITからFIPへの移行を促しています。
<太陽光発電の今後の展望>
前述したように、政府のエネルギー基本計画では、2040年までに電源構成のうち、太陽光発電は、現在の9.8%から、23〜29%を占めるとされ、また、2050年のカーボンニュートラルを見据えて、さまざまな取り組みがなされています。
◆ ゼロ・エネルギーな建物ZEH・ZEB
太陽光発電の具体的な取り組みとしては、「2030年度以降新築される住宅について、*ZEH(ゼッチ)基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指す」とともに、「2030年において新築戸建て住宅の6割に太陽光発電設備が設置されることを目指す」とする政策目標があげられます。
*ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)
家庭での消費エネルギーに対して、高断熱、省エネ設備機器での省エネと、太陽光発電などの創エネによって、エネルギー消費を実質ゼロにした住宅のこと。
ZEH の運用については、2016年度から、ハウスメーカーや工務店、リフォーム会社などの企業が受注する住宅のうち、ZEHの割合を2020年までに50%以上にする目標を宣言・公言した企業をZEHビルダーとして、公募、登録し屋号や目標値の公表を行ってきました(2022年3月のZEHビルダーは4,722社であった。)
そして、2021年度からは、目標水準を引き上げた新たなZEHホルダー制度の運用が始まっています。
ZEHだけでなく、ZEB(ゼブ)の取り組みもあります。ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)とは、建物で消費する年間のエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のことで、2021年10月の地球温暖化対策計画で、事務所ビルや商業施設などの建物における2030年度のエネルギー起源のCO2排出量を2013年度に比べ51%削減するという目標が設定されました。
◆ 進む技術開発
太陽光発電のさらなる普及を目指し、国内外で革新的な技術開発も進んでいます。これまで、太陽光発電に使われる既存の太陽電池は、壊れにくく、光から電力への変換率も高かったのですが、材料や製造コストが比較的高いという難点がありました。そこで、次世代の太陽電池材料(次世代型パネル)として期待されているのが、ペロブスカイト太陽電池です。
ペロブスカイト太陽電池とは、ペロブスカイトという結晶構造の新しい太陽電池で、軽量性・柔軟性に優れた次世代型太陽電池です。現在の太陽電池よりも低価格で軽量な太陽電池の実現が期待されています。
すでに、現在使用の太陽電池に匹敵する変換効率も達成しており、荷重制限のある屋根や壁面に設置できるため、今後設置スペースの拡大が見込まれます。2025年現在、実用化に向けた開発と実証実験が各地で進められ、政府は、2040年までに容量20GWのペロブスカイト太陽電池導入を目標としています。目下、課題とされる耐久性の問題に取り組み、さらなる変換効率の向上めざして、実用化が進められています。
変換効率に関しては、2023年には、シャープが変換効率約34%の太陽光パネル開発に成功し、世界記録を樹立しました。軽量・高効率パネルの実用化により、従来は設置が困難とされていた壁面や水上への導入も可能となります。
こうした、技術革新、蓄電池併設による電力安定化、新たなビジネスモデルの構築などにより、太陽光発電は今後、一般家庭から企業までより広範囲に普及していくことが期待されます。
(参照)
再生エネ普及への道、急拡大する太陽光発電、
2013年9月25日(日経)
太陽光発電のしくみ・特徴
(中国電力HP)
太陽光発電の今後に将来性はある?現状や課題・今後の展望について解説
(Daigasコラム/大阪ガス、2025年10月29日)
太陽光発電の仕組みや課題、世界の現状について解説
2023.09.29(最終更新日:2025.10.03)Earth &Note
太陽光発電 5割抑制も 再稼働前提 事業者「参入できない」
(2015年3月5日、東京新聞)
2026年度 新FIT制度について解説!
(ソーラーメイトブログ、2025年7月1日)
自家消費型太陽光発電システムとは?基礎知識や導入のメリットなど解説
(出光Sola Frontier)
再エネ受け入れ一時停止、東北電も 太陽光と風力の21発電所を制御
2022年4月10日、朝日新聞)
SMART ENERGY WEEK -スマートエネルギーWEEK
(サステナブル経営WEEK事務局)