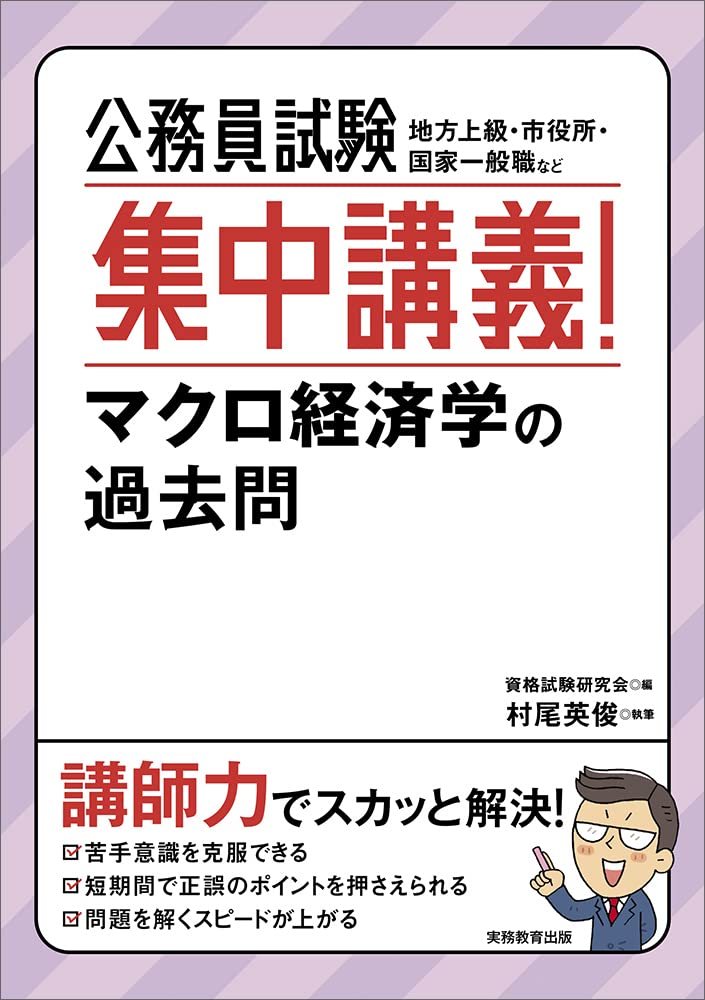日本のエネルギー政策について連載でお届けしています。今回から、自然を利用した再生エネルギーを取り上げます。再生エネルギー(再エネ)には、太陽光、水力、風力等がありますが、今回は、個々の内容を見る前に、再エネの全体像を概観します。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
<今、なぜ再エネか?>
地球温暖化が深刻化し、世界的に脱炭素に向けた取り組みが加速する中、再生可能エネルギーへの転換が世界規模で求められるようになっています。日本でも、化石燃料への依存を減らし、省エネの推進や再生可能エネルギーへの転換が進められています。とりわけ、石油や石炭などの化石燃料を持たない日本にとって、再生可能エネルギーは、社会の維持と発展にとっても不可欠なものです。
◆ 再生可能エネルギーとは?
再生可能エネルギーとは、太陽光や風力など、自然界のさまざまな場所に存在していて枯渇しない資源によって作ることができる持続可能な環境に優しいエネルギーをいいます。何度も繰り返しエネルギーを作り出すことができるため、再生可能エネルギーと呼ばれており、脱炭素化やエネルギーの安定供給に重要な役割を果たしています。
なお、「エネルギー供給構造高度化法」では、再生可能エネルギー(再エネ)を「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と定義しています。また、同法によって、日本では、太陽光・風力・水力・バイオマス・地熱の5つの電源を主要な再生可能エネルギーと定めています。
◆再エネの種類と分類
太陽光発電
太陽光発電とは、太陽光がもたらす光エネルギーを直接電気に変換する発電方法で、ソーラーパネルに複数まとめて組み込まれている太陽電池(太陽光を受けて電気エネルギーを発生する部品)を利用して発電します。
天候により発電量が左右されますが、住宅・工場・公共施設・未利用地などへ広く普及が進んでいます。2012年に経済産業省が実施した固定価格買取制度(FIT)により急激に導入件数が増加し、発電割合は再生可能エネルギーのなかで最大です。
水力発電
水力発電とは、河川にダム等を設置し、流水や落水といった水の力を利用することで、水車を回転させ、そこから得られた動力で発電機を動かし発電します。水力発電は安定した信頼性の高い電源である一方、大規模水力発電は国内に新たな適地がなくなってきていることから、中小規模の開発が進んでいます。
バイオマス発電
バイオマス発電は、林地残材や製材廃材、食品廃棄物などの生物資源を利用して発電する方法です。脱炭素につながるだけでなく、廃棄物の削減など資源の有効活用にも役立つ一方で、原料の安定供給確保、収集・運搬・管理コストなどの課題があります。
地熱発電
地熱発電は、地下深くにたまった「地熱」を利用して発電する方法で、地下のマグマ溜まりで熱せられた蒸気や熱水をくみ上げ、その蒸気でタービンを回して発電します。他の再エネと比較して、天候や風況に左右されず、昼夜を問わず安定的に発電可能ですが、開発に時間とコストがかかり、リスクも高いことが問題視されています。日本には大きな地熱のポテンシャルがあると指摘されています。
風力発電
風力発電は、風の力を利用して発電する方法で、風力エネルギーを風車によって動力に変換し、その動力を活用して発電します。変換効率が高いうえに夜間も稼働できますが、風 況(風の強さや風の方向)の影響で発電量が安定しません。
陸上力発電と洋上風力発電の2種類があり、海に囲まれた日本では洋上風力発電のポテンシャルが高いとされています。
ほかにも、雪が持つ低い温度や年中一定を保つ地中の熱、空気の温度でさえも再生可能エネルギーとして利用可能です。さらに、海面の温かい水と深海の冷たい水との温度差を利用して発電する海洋温度差発電や、海の波の上下動や潮の満ち引き、海流を利用した発電方法などの研究開発も行われています。
(参考)エネルギー変換効率でみた再エネ
エネルギー変換効率とは、エネルギーを変換して利用するときに、投入したエネルギーに対する、有効に利用できるエネルギーの割合(発電に使われたエネルギーが電気に変換された割合)を言います。
再生エネルギーのなかでは、水力発電のエネルギー変換効率は約80%と、他の発電方式と比べても効率の良さが際立っています。
再エネのエネルギー効率
水力発電 80%
風力発電 25%
太陽光発電 15〜20%
地熱発電 8%
海洋温度差 3%
バイオマス発電 1%
(関西電力HP)
ただし、再エネの発電は、水力発電を除き、化石燃料での発電と比べて面積割合での効率が低いというのが実態です。
火力・原子力発電の発電効率
天然ガス(LNG)火力:55%
石炭火力 42%
石油その他火力 36%
原子力発電 33%
たとえば、ある太陽光の発電所は、同じ所在地にある火力発電所と比べ、面積は約2倍ですが、発電量は0.1%にも満たないといった事例もあります。
<再エネの特徴>
◆ 再生可能エネルギーのメリット
今、再生可能エネルギーが注目され、求められる理由は、再エネが、➀脱炭素化に貢献し、②エネルギーの安定供給、③エネルギー自給率の向上にも役立つととも、④地域経済の発展につながる場合もあるからです。
➀ 再生可能エネルギーは脱炭素化に貢献
再生可能エネルギーは、発電時に地球温暖化の原因となる、温室効果ガスであるCO2の排出がゼロで、脱炭素化に貢献します(地球温暖化対策として有益)。
もちろん、設備の設置や運用に多少のCO2(二酸化炭素)の排出はありますが、石炭や石油といった化石燃料とは異なり、発電時や熱利用時に、CO2などの温室効果ガスを排出しません。
ちなみに、再エネ電源の中で、設備の設置や運用時に発生するCO2排出量において、水力発電と地熱発電が、他の再生可能エネルギーを下回っています。
② 枯渇せず安定供給に寄与
また、再生可能エネルギーは、枯渇しない太陽光や風力などをエネルギー源とし、永続的に利用することが可能であることから、資源の状況に左右されずにエネルギーの安定供給に寄与します。
これは、世界中で、再エネの割合を増やすことは、石油や石炭など資源が有限である化石燃料の枯渇を防ぐことにもつながります。
③ 国内のエネルギー源で発電可能
再生可能エネルギーは、太陽光や風力といった自然のエネルギーを利用するので、石油や石炭など化石燃料を輸入する必要がなく、国内でエネルギー源を確保できます。
日本のエネルギー自給率は、12.6%(2022年度)と先進国のなかでも低水準であるなか、再エネの導入が進めば、エネルギー自給率を高め、エネルギーの安全保障にも役立てることができます。
④ 地域経済の発展に寄与
再エネは、CO2(二酸化炭素)の排出抑制だけではなく、地域経済発展の有望な「資源」にもなりえます。
たとえば、太陽光発電を利用している地域では、近年、田畑等の農地の上部空間を活用して太陽光発電を設置する「ソーラーシェアリング」が行われており、単に、発電だけでなく、燃料などの利用にも共有され、電力費や燃料費の削減につなげているところがあります。さらにそこから、農業に限らず、他の地域の産業と結びつきを強めていくことも期待できます。
再エネは密度が薄いエネルギーであるため、再エネを回収するには広い面積を必要とします。都市部にはそれだけの土地の余裕がなく、地方は逆に有利となります。
なお、地域のエネルギー需要のすべてを当該地域の再エネのみで賄える地域を「エネルギー永続地帯」と呼ばれており、2019年度時点で、日本には1718市町村のうち、エネルギー永続地帯が138市町村あるとされています。
◆ 再生可能エネルギーのデメリット
一方で、再エネには、天候や風況といった自然環境に左右されるため、発電量が不安定であったり、設置場所が限定されたり、発電コストが割高といったような問題点が指摘されます。
発電コストが高い
再エネは、燃料費がかからないものの、発電するに当たり大きなコストが発生しており、火力発電(石油火力を除く)や原子力発電よりも高コストで生産しなければなりません。
電源別発電コスト(1 kWh当たり、2020年)
太陽光(事業用):12.9円
地熱:16.7円
陸上風力:19.8円
洋上風力:30.1円
天然ガス(LNG):10.7円
原子力 :11.5円
石炭火力: 12.5円
石油火力: 26.7円
電力の安定供給に課題
再エネの多くは自然現象の影響を受け、太陽光発電であれば天候や日照時間、風力発電であれば風力や風向きの影響により、発電量が変動し、安定供給に課題があります。そのため、電力需要に応じて発電量を調整することや、余剰に発電された電力を蓄電池に蓄えるなど、電力の需給調整機能が必要となります。
発電量のコントロールが困難
再エネが電力を安定的に供給できないという問題は、発電量の管理を、化石燃料以上に難しいものにします。
もともと、電気は大量に生産したものを貯めておくことが難しく、需要予測に合わせて発電する必要がありますが、化石燃料の場合、火力発電所は燃料の投入量を調整することで発電量を比較的容易かつ迅速に調整できます。
しかし、再エネは、太陽光や風力など自然現象に依存するため、天候や時間帯によって発電量が大きく変動するなど、火力発電以上に予測や制御が難しくなります(安定した発電が困難)。
これが、欧州のように国同士が地続きであれば、電気生産量によって受け渡しを行うなど周辺国との協力が可能ですが、島国の日本では、周辺国と協力して発電量をコントロールすることができません。
加えて、日本では、地域(エリア)ごとに電力の需要と供給のバランスを管理していることもこの問題を大きくしています。再エネの導入拡大には、蓄電池の活用や地域間連系線の強化など、発電量の変動を吸収するための対策が不可欠となっています。
系統制約の問題
発電量の管理が難しいという課題は、さらに、*系統制約の問題を誘発させます。
*系統(電力系統)
「発電⇒送電⇒変電⇒配電」という発電所から利用者へ電気を供給するためのシステム全体のことを言う。
再エネには、太陽光、風力、地熱などの自然エネルギー源が豊富に存在し、それらを利用して効率的に発電できるポテンシャルのある地域と、電力需要が高い地域が一致していない場合が多くあります(電力需給のミスマッチ)。
その場合、送電線には送れる電力量の上限がある(送電可能な電力量も決まっている)ので、再エネ事業者が「系統に繋げることができない」といった問題などが発生します。これは、電力系統全体に負荷がかかりすぎると、安定した供給を維持するために、一部の再生可能エネルギー発電所への接続が制限されることがあるからです(送電インフラの制約)。
日本では、地域(エリア)間の繋がりはあるものの、電気を他のエリアに大量に送ることが困難であるので、系統の制約問題の緩和や解消が必要になります。
(この問題については改め取り上げます)
大規模設備が必要(限定された設置場所)
再生可能エネルギーで日本の電力需要を賄うだけの発電設備を備えようとすれば、大規模な再エネ発電設備を備えることが望まれます。しかし、国土の狭い日本では、新たな発電設備を設置するためスペースは限定的です。
これは、発電効率の面からも言えることで、再エネの発電は、化石燃料での発電と比べて面積割合での効率が低く、火力発電なみにエネルギーを多く生産するためには、より大きな設備を設置できる広大な土地が必要となります。
設備導入地域での住民による反対運動
さらに、これに関連して、巨大な設備を必要とする再生可能エネルギーの発電所が設置された地域において、地域の活性化に繋がるなどのメリットはありますが、景観・環境破壊や騒音問題、生態系への悪影響などが指摘され、施工業者と地域住民との間でトラブルが生じるケースが増えています。
では、次に、再生可能エネルギーが電源別にどれくらい利用されているか、またその潜在能力はどうなっているかなどについて、みていきましょう。
<日本の再生可能エネルギーの実績と潜在力>
◆ 再エネ発電量の割合
資源エネルギー庁が発表した「2023年度エネルギー需給実績(速報)」によると、2023年度の発電電力量、9854億kWhのうち、石油・石炭・天然ガス(LNG)などの化石燃料(火力発電)の発電割合が68.6%、原子力発電8.5%に対して、再生可能エネルギーは22.9%(2257億kWh)でした。
また、再生可能エネルギーのなかで、太陽光発電の割合が最も多く、水力発電、バイオマス発電、風力発電、地熱発電の順でした。
太陽光発電 966億kWh(9.8%)
水力発電 749億kWh(7.6%)
バイオマス発電 404億kWh(4.1%)
風力発電 108億kWh(1.1%)
地熱発電 30億kWh(0.3%)
◆ 発電設備容量でみた再エネ
発電設備容量とは、現在、国内に実際に設置され稼働している発電設備の最大出力(kWやMW)の合計で、設備が最大限に稼働した場合の発電能力を示します(「現状」や「実績」を示す数値)。
資源エネルギー庁のデータによれば、全国発電設備容量(実績)は、2014年度の2億5201万kW(252GW)から、2024年度は3億2416万kW(324GW)に増加しています。
このうち、新エネルギー(再エネ)等の導入容量が94GW(大型水力を含めて142GW)でした。政府は、2030年度までに再エネを200GW程度に増やす目標を設定しています。今日の発電設備容量は1995年頃に主要であった石油による発電設備が減少(26%⇒5%)し、再エネの発電設備が著しく増加しています。
発電設備容量(2024年)の発電源別比率(2014年度からの変化)
新エネ: 2%⇒29%
水力:19%⇒15%
天然ガス:29%⇒25%
石炭:15%⇒16%
石油:17%⇒5%
原子力:18%⇒10%
◆ 潜在的な発電能力でみた再エネ
環境省は、再生エネの「潜在的な発電能力(潜在的ポテンシャル)」を調査し公表しています。これは、発電施設を可能な限り設置した場合の発電量を試算したもので、技術的に可能か(現実性)、経済的に可能かなどによっても数値は変動します。
一般的に、潜在的な発電能力は、賦存量と導入ポテンシャルの2つの観点から評価されます。
賦存量とは、対象地域に存在する利用可能な自然エネルギー源全体の量(日射量、風速、河川の流量など)から計算される資源の総量で、理論上の最大潜在能力を示します。
導入ポテンシャルは、「導入した場合の発電能力」の意味で、理論的な賦存量から、技術的・地理的(土地の傾斜や設置可能面積など自然条件)・社会的制約(土地利用などの制約)などの要因を差し引いた、現実的に導入可能な量のことです。
言わば、現在の技術水準では利用困難なものや法令・土地用途などによる制約などを除いた賦存量(技術的・法的な制約内で導入可能な量)で、技術的導入ポテンシャルとも言います。理論的な賦存量から技術的に可能かなどが判断された量です。
これによって、長期的な可能性(⇒賦存量)と短期・中期的な実現可能性(⇒導入ポテンシャル)の両方を把握できます。
「導入ポテンシャル」はさらに、「経済性を考慮した導入ポテンシャル」と「事業性を考慮した導入ポテンシャル」に分類することもできます。
「経済性を考慮した導入ポテンシャル」は、「導入ポテンシャル」からさらに、設置・運用コストや収益性など、経済的に見合うか(採算性)が考慮された上での導入可能な量のことです。
「事業性を考慮した導入ポテンシャル」は、経済的ポテンシャルに加え、さらに、環境影響評価や社会的受容性(住民合意、送電網の整備、電力の利用状況など)などを考慮して、現実的に事業として成立する、より実現可能性の高い量をさします。
これら一連の分類は、再生可能エネルギー導入の可能性を、理論的な発電能力から、技術的な限界、経済的・政策的・社会的な実現可能性まで、段階的に絞り込みながら評価する際に用いられます。
電源別でみた潜在的発電能力
この中で、再エネ種別ごとの「導入ポテンシャル」と「経済性を考慮した導入ポテンシャル」についてみてみると、設備容量でみた「(技術的)導入ポテンシャル」では太陽光発電が圧倒的に大きく、2番目が洋上風力、陸上風力発電と続きます(括弧の数字は、年間発電量で換算したもの)。
太陽光: 27億4595万kW(3兆 2216億kWh)
陸上風力: 2億8456万kW (6859億kWh)
洋上風力:11億2022万kW(3兆4607億kWh)
中小水力: 890万kW (537億kWh)
地熱: 1439万kW (1006億kWh)
(環境省「再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査」報告書/2020年度のデータ)
*ワット(W)
「電力の瞬間の大きさ(瞬間的に消費する電力の大きさ)」を表す単位で、最大出力の測定などに活用される。
*ワットアワー(Wh)
「電力量(電気がどれだけ使われたか)」、「ある時間内の総電力量(消費・蓄電されたエネルギーの総量)」を表す単位、バッテリー容量や電気代を計量するときに使われる。
しかし、「経済性を考慮した導入ポテンシャル」では、太陽光発電は大幅に縮小し、風力発電を下回ります。
経済性を考慮した導入ポテンシャル
(数字の幅は低位推計と高位推計)
太陽光: 3832万kW〜4億 622万kW (473億kWh〜5041億kWh)
陸上風力:1億1829万kW〜1億6259万kW (3509億kWh〜4539億kWh)
洋上風力:1億7785万kW〜4億6025万kW (6168 億kWh〜1兆5584億kWh)
中小水力: 321万kW〜 412 万kW (174〜226億kWh)
地熱: 900 万kW〜1137 万kW (630〜796億kWh)
この結果から、風力発電、特に洋上風力発電の潜在的な導入可能性が非常に大きいことがわかります。高位推計でみた場合、現在の国内の年間発電電力量(約1兆kWh)を、洋上風力だけでまかなえる計算になります。
全ての再エネ発電による発電量の合計(経済性導入ポテンシャル)は、低位推計で1兆954億kWh/年、高位推計で2兆618kWh/年と推計されています。
これは、国内の年間発電量の合計は約1兆kWh/年であることを考えると、導入可能な立地は必ずしも全国満遍なくとはなっていないとはいえ、統計上、再エネ発電は、低く見積もっても、現状の日本の全電力消費量と同等(再エネですべて賄える)です。高位ポテンシャル(高位推計)でみれば2倍となり、再エネには多くの未開発の潜在能力が存在し、導入余地も非常に大きいことを示しています。
なお、バイオマス発電は、他の自然エネルギーとは異なり、燃料を燃焼させるため、燃料供給や安定性など独自の評価が必要となり、太陽光、風力、中小水力、地熱発電と同じような単一の確定的な数値は、環境省から発表されていません。
<日本の再生可能エネルギーの現在地>
石油ショックと東日本大震災
1973年の第一次石油危機の後、環境省は、石油依存からの脱却を図るべく、天然ガスや原子力、再生可能エネルギーの導入を促し、エネルギー源の多様化を進めてきましたが、なかなか進みませんでした。
しかし、2011年3月の東日本大震災にともなう福島第一原子力発電所の事故は、日本のエネルギー政策の転換点となりました。
震災前、2010年度の電源別発電電力量の割合(電源構成)は次の通りでした。
化石燃料:67%(液化天然ガスLNG:29%、石炭:28%、石油等9%)
原子力:25%
再エネ:9%(水力が7%、その他新エネルギーが2%)
2011年3月の原発事故以降、全国の原子力発電所は順次停止され、一時は原発の発電量がゼロとなりました。そこで、原発の代替として、震災後は、停電を防ぎ、電力の安定供給のために、それまで老朽化により休止していた火力発電所を再稼働させたり、カタールなどから大量の天然ガスを輸入したりするなど、火力発電を増強して電力をまかなってきました。
これにより、火力発電の割合は、2010年度の67%から、2013年度は88.2%(天然ガス40.9%、石炭32.9%、石油14.4%)に上昇しました(原子力は0.9%)。
これに対して、再生可能エネルギーの発電比率の割合(電源構成)は、2010年に約9.5%と全体の1割未満でしたが、福島第一原発の事故を踏まえ、経済産業省は、2012年から本腰を入れ、原発に代わって再エネの普及を進めるために、固定価格買取制度(FIT制度)を導入しました。
震災後の普及
FIT制度により、事業としてのインセンティブが高まり、2013年から、再生可能エネルギーの新規参入が飛躍的に増加しました。その結果、再エネ等の比率は、2013年10.9%から2023年には22.9%へと上昇、10年間で2倍以上となっています。
逆に、化石燃料をエネルギー源とする火力発電は、88.2%(2013年)から68.6%(2023年)に低下し、その中でも石油等による発電が約半分に減少(14.4%から7.4%)、天然ガス(LNG)も40.9%から32.9%へ下がっています(原子力発電は8.5%)
このことは、東日本大震災直後に原子力発電の代替として、天然ガスと石油を軸に急増した火力発電が、その後の10年間で再生可能エネルギーに置き換わってきたことを示しています。
とりわけ、太陽光発電の伸びが顕著で、2013年の1.2%から2023年には9.8%の約8倍に急増しました。この背景には、太陽光設備の建設期間が短くてすむことや、後述する固定価格買取制度(FIT)で、太陽光の買取価格がかなり割高に設定されたことなどもあげられます。実際、2024年度末までにFIT制度で運転開始した設備容量の約9000万kWのうち7000万kW が太陽光でした。
再エネの電源別発電割合の変化(2013年⇒2023年)
太陽光:1.2%⇒9.8%
バイオマス:1.6%⇒4.1%
風力:0.5%⇒1.1%
水力:7.3%⇒7.6%
地熱:0.2%⇒0.3%
<固定価格買取制度(F I T制度)>
それでは、再エネ推進の原動力となったFIT制度についてみてみます。
◆ FIT制度の仕組み
FIT(フィード・イン・タリフ)(略称「フィット」)制度は、再生可能エネルギーで発電した電力の全量を固定価格で、電力会社に一定期間(10年〜最長20年間)、原則、買い取ることを義務付ける制度です。
再生可能エネルギー特別措置法(F I T法)に基づき、2012年7月に制定され、再エネの対象は、経産省が認定した、太陽光、風力、地熱、バイオマス、中小水力です(なお、大規模水力発電は、既に経済的にも確立していることから対象外)。
FIT制度によって、買取価格の見通しが立つことで事業計画が立てやすくなり、FIT法が施行された2012年7月以降、再生可能エネルギー発電事業に参入する事業者が増加し、太陽光発電を筆頭に、再エネの設備容量も増加しました。
FIT制度において、買取価格は、再生エネ事業者に利益が出る水準に設定されており、経産省が年度ごとに見直しています(経産省の有識者会議「調達価格等算定委員会」で価格案が示され、経産相が正式に決めるという手続きがとられる)。
買い取りに必要な費用(買取費用)は、電気料金に上乗せされ、「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)という形で、その費用の一部をすべての電力利用者が負担しています。
したがって、再生可能エネルギーの普及が進むにつれ、割高な固定価格での買い取りは電気料金における消費者の負担を重くする原因となっています。
出典:資源エネルギー庁「2020-日本が抱えているエネルギー問題(前編)」
このため、経産省は、再エネの導入コストが下がっていることもあって、年度ごとに毎年見直される再エネの買取価格を年々下げています。特に、再生エネが太陽光に偏っている現状を是正するため、重点的に太陽光の買取価格が大幅に引き下げられました。
再エネ買取/売電価格の変化
(導入時の2012年と2025年の調達価格ならびに買取期間)
太陽光発電
10KW未満(住居向け) 42円 ⇒ 16円 (買取期間10年)
10KW以上(企業向け) 40円 ⇒ 8.9円〜11.5円(20年間)
水力発電(発電規模別)
24円〜34円 ⇒ 9円〜34円 (20年間)
風力発電
陸上 22円 ⇒ 12円〜13円(20年間)
洋上 22円〜55円 ⇒ 36円(20年間)
地熱発電
1.5万KW未満: 40円 ⇒ 19円〜40円 (15年間)
1.5万KW以上: 26円 ⇒ 12円〜26円 (15年間)
バイオマス発電(燃料の種類別)
13円〜39円 ⇒ 13〜40円 (20年間)
(新電力ネット/資源エネルギー庁)
余剰電力買取制度
なお、FIT制度が2012年7月に制定される前に、太陽光発電のみ買取制度が、2009年11月から始まっていました。それは、「余剰電力買取制度」と呼ばれるシステムで、家庭などで太陽光発電によって発電された際に、使いきれなかった余剰電力を、電気事業者が一定期間(10年間)、固定された価格で買い取ることを国が義務付けました。
余剰電力買取制度と、FIT制度(固定価格買取制度)との違いは、FITが太陽光を含む全再エネを対象として、発電された電力を全量買い取る仕組みであるのに対して、前者は、買取り制度の対象が、太陽光のみで余剰電力を買い取るということです。
余剰電力買取制度は、2012年7月に後継の「固定価格買取制度(FIT)」に移行するまで実施されました(その後はFIT制度に吸収)。
◆ FIT制度の改革
再生可能エネルギーの買取期間が終了すると、その後は通称「卒FIT(そつフィット)」と呼ばれる状態となります。
買取期間が最も短いのは、出力10キロワット未満の家庭用の太陽光発電の10年です。余剰電力買取制度を含めると、2019年11月から、卒FIT(FIT期間の終了)を迎え、買取期間が満了する人(家庭)が増えています。
買取期間が終了した後は、FIT制度による固定価格での買い取りはなくなり、より安い市場価格での売電となります。
引き続き売電を希望する場合は、電力会社(主要電力会社や新電力会社)と新たに売電契約を結ぶ必要がありますが、通常、FIT制度の時よりも買取価格は下がります。 また、新規に導入する設備もFIT制度の対象となります。
FIT制度の課題
卒FITが増えていくなか、今後のFIT制度と再エネ市場の方向性を定めることが求められました。
FIT制度は、再エネを普及させることが目的で始まりましたが、将来的にはFIT制度がなくとも、再生可能エネルギーが普及し、再エネ市場が持続可能な成長を実現することが理想です。
しかし、再生可能エネルギーのさらなる導入拡大への取り組みが進みづらいという課題がいくつか指摘されていました。
それはまず、FIT制度により、これまでに再生可能エネルギーの導入が大幅に増加し、かつ「卒FIT」も増えていくという状況下、FIT制度も*電力市場と連動(統合)していくことが必要になったことです。
*電力市場
電力市場は、発電事業者と小売電気事業者との間の電力取引を行う卸電力市場のことを言い、取引方法は相対取引(売り手と買い手が一対一で価格を決定する販売方法)と取引所取引に大別される。後者には、JEPX(Japan Electric Power Exchange)(日本卸電力取引所)がある。
また、現行のままFIT制度が続けば、今後も、買取費用がすべて電気料金に上乗せされているので、割高な固定価格での買取りによって、国民(家計)の負担が大きくなっていくことも懸案となっていました。
加えて、再生エネ固定価格買い取り制度が、電力コスト増の原因と経済界からの批判も強まっています。経団連は「再生エネ比率が低いほど経済に好影響を与える」と、買い取り費用の抑制を訴えています。
そこで、FIT (固定価格買取制度)に 新たな仕組みが必要ということになり、入札制度と、FIP制度が導入されました。
FITの入札制度
FITにおける入札制度は、とりわけ、再エネ市場で価格競争を促進させることで、再エネの適正価格化を促しことが目標とされました(これまでは、固定での買取り価格が、実質的な「市場」での価格であった)。それが結果的に、国民の負担が軽減され、再生可能エネルギーの効率化とコスト削減によって、より安定した再エネ発電事業を実現することが可能となります。
(入札制度の概要)
FITの入札制度は、政府が指定した出力が一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備を持つ発電事業者を対象に、2017年4月の改正FIT法によって始まりました。
当初は、導入が際立った進んだ太陽光発電のみでしたが(入札参加条件は2000kW=2MW以上から現在250kW以上に変更)、後に、風力発電と一部のバイオマス発電など他の再エネも入札の対象となりました(地熱と水力発電は原則として入札の対象外)。入札対象の基準や条件は、各電源種別によって異なり、個別にまたは定期的に実施されます。
(入札方法)
入札制度では、まず政府が先に「これだけの電力容量を買い取りたい」と、事前に買い取り量を明示し、それに応じて各発電事業者が「この価格でこの容量を提供できる」と、希望価格(「1kWhあたりの価格」と「発電出力」)を提案(で応札)する形で入札が行われます。そして、最も安価な価格を提示した事業者から順に、募集容量に達するまで落札者が決定されるという仕組みです。このようにして買取価格を設定する方式は「ペイ・アズ・ビッド方式」と呼ばれます。
入札によって決定された価格は、FIT制度において、固定買取価格(調達価格)に反映されます。なお、入札価格には上限が設けられています。
FIP制度
FIP(フィード・イン・プレミアム)(略称「フィップ」)制度は、FIT(固定価格買取)制度のように再エネへの投資を促す仕組みは残しつつ、再生可能エネルギーを自立させ、電力市場へ統合させるためのステップ(段階)として、2022年4月から、大型の発電施設を中心に新しく導入されました。
(FIP制度は2020年6月の再生可能エネルギー特別措置法の改正によって導入が決定し、2022年4月から施行。)
FIT制度では、再エネで発電された電気を固定された価格で電力会社が買い取り、しかも、買取価格は最長20年間固定され、発電事業者にとっては需給量に関わらず一定の収益が発生します。
これに対して、FIP制度では、再エネは卸電力市場(電力の卸売市場)で、自由に取引(売買)され、売電(発電事業者が卸売市場で電気を売る)の際、市場価格に一定のプレミアム(補助額)が上乗せされます。
販売価格は、市場価格に連動し、市場価格変動リスクを負いますが、市場動向によっては高収益を得ることできます。たとえば、蓄電池などを活用することで、より高く売電できるタイミングを狙うことも可能です。
このように、FIP制度の導入によって、再生可能エネルギーの価格競争や自立化が実現し、再エネが競争力のある電力源となることが期待されています。
もっとも、これによってFIT制度は廃止された(完全に終了する)わけではありません。FIP制度は、FIT制度と並行して導入されたので、発電事業者は、FIT制度かFIP制度を選択することになります。
前述したように、買取期間満了まではFIT制度が継続され、すでにFIT認定を受けている設備は、FIT期間の終了まで売電価格も変わることはありません。また、FITの新規契約も認められています。
ただし、政府は、電力市場との統合を目指し、FIP制度は拡大、FITは縮小させていく方針で、現在では、FIT制度からFIP制度への移行が進んでいます。たとえば、大規模な産業用太陽光発電(250kW以上)の新規認定は、2024年度以降、段階的にFIP制度のみが対象で、FIT制度は適用されなくなります。
また、すでにFIT制度の認定を受けている大規模案件を持つFIT認定事業者は、希望すればFIP制度へ移行することも可能です。
加えて、FIP制度にも、FIT制度の入札制度が適用され、入札によって決定された価格は、FIP制度における基準価格に反映しています。しかも、今後、FIT入札の対象が徐々に縮小され、FIP入札の対象範囲が拡大していく方針です。
◆ FIT制度の構造的問題
固定価格買取制度(FIT制度)には、再エネの大量導入に対して、電力系統の整備や運用ルールが追いついていないという構造的な課題を抱えています。そうした地域では、電力の安定供給を維持するための系統接続が制約されたり(系統接続の制約)、出力抑制を強いられたりする(出力抑制の必要性)という問題が生じる可能性があるのです。
系統接続の制約
系統接続の制約とは、電力会社の送配電網(電力系統)が「満杯」の状態になってしまうことです。
発電した電気を送るための送電線や変電所には、送れる電気の量に物理的な上限(容量)があります。特定の地域で、たとえば太陽光発電が大量に導入されると、送電線が「満杯」になり、新しい発電所に接続できなくなったり、既存の発電所の電気も送れなくなったりする可能性がでてきます。
再エネ接続保留問題:
この問題が実際に顕在化したのが、2014年の再エネ接続保留問題です。同年9月、九州電力を皮切りに、北海道、東北、四国、沖縄の電力5社が、自社の送電網に接続できる再エネの容量が限界に達した(電気を安定的に供給する容量を超えそうだ)として、新たな再エネ発電事業者からの新規接続申し込みを一時的に保留・停止しました(その後、再開)。
これは、固定価格買取制度(FIT)の開始により再生可能エネルギー、特に、買い取り価格が比較的高く設定された太陽光発電に申請が殺到し、その導入が急速に進んだ結果、電力系統の安定供給に支障をきたす恐れが生じたためです。
出力抑制の必要性
出力抑制の必要性とは、余剰電力の発生から生じる問題です。そもそも、出力制御とは、電力の需要と供給のバランスを保つため、電力会社が、実際に稼働中の太陽光など再エネ発電事業者に対して、一時的に発電を抑制または停止するよう指示を出すことを言います。
電力は大量に貯蔵できないため、電力の安定供給には、常に需要量(使う量)と供給量(作る量)を一致させる必要があります。たとえば、太陽光発電の場合、晴れた日の昼間など、電気が多く作られすぎる(好天で発電が増える)一方、休日で企業の需要が少なくなるなど、需給バランスが崩れて、電気の供給が需要を大幅に上回ると、周波数や電圧が乱れ、最悪、大規模な停電につながりかねません。
そこで、これを防ぐため、電力会社は火力発電の出力を下げたり、他の電力会社管内に送電したりしますが、そうした措置をとっても供給が上回る場合、太陽光発電所に対し「発電量を抑えてください」「止めます」と、再エネの出力抑制(出力制御)の指示を出す場合があるのです。
実際、2018年10月に九州電力が、また2022年4月には四国電力と東北電力が、実際に稼働中の太陽光発電などに対して、自社の送電網に接続できる再エネの容量が限界に達したとして、FIT制度に基づく再エネ発電事業者からの新規接続申し込みの受け入れを一時停止しました(出力制御を実施)。
出力抑制は、電力の需要と供給を一致させ、電力系統の安定を維持させるための手段であり、再エネの出力が不安定で需要と供給のバランスが崩れる可能性がある場合に特に重要となります。
なお、出力抑制の優先順位は、まず火力発電の出力を調整・抑制し、次に、地域間連系線を活用して、余剰電力を電力需要のある他のエリアへ送電します。それでも供給が過剰な場合に、バイオマス発電、太陽光・風力発電の順で出力抑制が行われます。それでもなお解消できない場合、最後に、原子力・水力・地熱などの長期固定電源の出力が制御されるという順番になります。
この順番は「優先給電ルール」と呼ばれ、電力の安定供給と、出力調整の難しさ(原子力などはすぐに出力を元に戻せない)やCO2排出量などを考慮して定められています。
問題解決のために
こうした問題を解決し、再エネの導入を拡大するためには、➀電気を効率よく運ぶための送電網の増強といったインフラ整備や、新しい運用ルールの構築、②余った電気を貯めて(蓄電池の導入)、他の時間帯で使ったり、別の地域で使ったりする(地域間連系線の活用)技術開発などが必要となってきます。
➀に関して、現在、コネクト&マネージなど、既存の電力系統を最大限、効率的に利用する、新しい仕組みの導入も行なわれています。コネクト&マネージ(接続と管理)とは、電力系統の混雑緩和のための新しい電力系統の運用ルールのことを言います。
これまで送電線の容量はすべての電源がフル稼働することを前提に容量が確保されていましたが、特定の時期や需要に応じて、電源の利用状況を想定しながら、その際の空き容量を算定したうえで、新規容量を連系する手法(「想定潮流の合理化」)があります。
ほかにも、緊急時用に空けておいた容量の一部を、平常時にも活用できるようにする仕組み(「N-1電制」)や、「先着優先」(系統の空き容量の範囲内で先着順に受け入れる制度)ではなく、混雑時でも系統に空きがあるときに一定の条件下で、送電することができるという手法(「ノンファーム型接続」)などがあります。日本ではノンファーム型接続が導入されています。
②に関して、再エネ資源が十分にある地域では、時間的な需給のミスマッチを解消するための蓄電設備があれば、余剰となる再エネ電力を蓄えて、たとえば、太陽光発電が働かない夜間の電力負荷に供給することが可能になります。また、余剰電力を別の地域に供給できる場合があります。
蓄電機能は従来の揚水発電やリチウムイオン電池、電気分解によって水素に変換して蓄えるなど、様々な方法が想定されており、さらなる技術革新が求められています。
このような対策を組み合わせれば、再生エネの電力が大きくなっても受け入れ拡大は十分可能となります。
<今後の再生可能エネルギー政策>
◆ カーボンニュートラル
現在日本は、パリ協定を受けて、当時の菅首相が2020年10月の就任後初の所信表明演説の中で「2050年カーボンニュートラル」を表明しました。
カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出を全体として実質ゼロにすることです。具体的には、人間活動によって排出されるCO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスの排出量から、植林、森林管理などによる「吸収量」 を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを言います。なお、ここでの温室効果ガスの「排出量」「吸収量」とは、いずれも人間活動によってなされる人為的なものを指します。
また、日本はカーボンニュートラルの達成に向け、2030年度までに温室効果ガスを、2013年度比で46%削減する大きな目標を掲げています。2030年度の電力供給は約9300億~9400億kWhと見込まれていますが、エネルギー利用の効率化により2019年度の1兆240億kWhから10%近く減少させなければなりません。
今後、カーボンニュートラルに向けて、再生可能エネルギーの普及がどのように進むかについては、日本のエネルギー政策全体の方向性が決定されるエネルギー基本計画に反映されます。
◆ エネルギー基本計画
エネルギー基本計画とは、2002年のエネルギー政策基本法に基づいて、政府が策定する中長期的な日本のエネルギー政策の指針で、省エネ方針や電源構成(エネルギーミックス)の見通しなど、日本のエネルギー政策全体像が示されます。
2003年に第1次エネルギー基本計画が策定されて、おおむね3年ごとに見直され、2021年と2025年2月に、それぞれ、第6次と第7次のエネルギー基本計画がまとめられました。
第6次エネルギー基本計画
計画の中で、2030年の温室効果ガス排出量について、2013年比で26%削減することが謳われました。
そのためには、再エネの拡大が必要とされ、政府は、2030年度までの再生可能エネルギーの目標導入量を、3130億kWhとし、発電量に占める再エネの比率(電源構成)を22〜24%から、36~38%に引き上げることを目指すとされました。
なお、参考値として「2050年までの再エネ比率を50%~60%」も言及されています。
また、2030年に向けて、2021年現在のエネルギー自給率13.3%から2030年には30%程度とする、という目標なども掲げられました。
第7次エネルギー基本計画
計画のなかで、2040年度に向けた再生可能エネルギーの発電割合の見通しは、2050年カーボンニュートラル実現に向けた中間指標として、以下のように示されています。
・2040年までに温室効果ガスを、2013年度比で73%削減(2013年比)する。
・再エネを主力電源とし、電源構成を、2040年までに40%〜50%に引き上げる。
再生可能エネルギーの電源構成
(2013年→2023年⇒2040年目標)
再エネ(全体):10.9%→22.9%⇒40〜50%
太陽光: 1.2%→9.8%⇒23〜29%
風力: 0.5%→1.1%⇒4〜8%
水力: 7.5%→7.6%⇒8〜10%
地熱: 0.2%→0.3%⇒1〜2%
バイオマス: 1.6%→4.1%⇒5〜6%
・次世代エネルギーの利用拡大させる
次世代エネルギーは、二酸化炭素を排出しない、もしくは排出を大幅に削減できるため、カーボンニュートラル社会の実現に向けた有望な技術として、日本でも開発が進められ、水素、アンモニア、合成メタン、バイオ燃料などの次世代エネルギーの活用が不可欠とされています。
水素;運輸、工業など、多様な分野での利用が期待されています。
アンモニア:発電や船舶燃料、化学分野での活用が進んでいます。
バイオ燃料:原料の植物等がCO2を吸収しているため、低炭素な燃料です。
*合成メタン:既存の都市ガスインフラをそのまま利用できるため、脱炭素化の現実的な手段として期待されています(都市ガスの脱炭素化)。
*合成メタン
二酸化炭素(𝐶𝑂2)と水素(𝐻2)を化学反応させて作る人工的なメタンのことで、燃焼時に排出される𝐶𝑂2と合成時に回収した𝐶𝑂2が相殺されるため、大気中の𝐶𝑂2を増やさないカーボンニュートラルなエネルギーとされている。
――――
このように、政府は、火力発電依存からの脱却を図り、エネルギー政策を化石燃料から再生可能エネルギーへと大きく転換することを示しているようにも見えますが、日本の発電割合では、今なお、火力発電が最も大きな割合を占めているのが現状です。
しかし、地球温暖化による気候変動や資源の枯渇化を回避し、将来世代に暮らし良い環境を残すことは現世代の責務といえ、再生可能エネルギーは、カーボンニュートラルの達成とエネルギー自給率の向上を同時に実現できる潜在力をもっています。電力も熱も再生可能エネルギーにシフトしていくことは時代の大きな要請と言えるでしょう。
(参照)
日本における発電割合は?再生可能エネルギー発電の現状や今後とともに解説
(2025年04月28日、スマートエネルギーWEEK)-
日本の再生可能エネルギーの割合と今後の普及について
(プラス・ソーシャル・インベストメント)
環境問題について考えてみよう
(中国電力HP)
第7次エネルギー基本計画をわかりやすく解説
(Yanmar HP)
温室効果ガス:日本の削減目標26% 13年比 電源構成で21%
(毎日新聞 2015年04月30日)
電源構成案:「再生エネ活用」及び腰 政府、原発ありき
(毎日新聞 2015年04月29日)
再生エネ買い取り:太陽光偏重、見直し 経産省委が始動
(毎日新聞 2015年06月25日)
クローズアップ2014:再生可能エネルギー制度、抜本見直し
(毎日新聞 2014年10月16日)
特集ワイド:続報真相 再生エネ停滞の深謀遠慮
(毎日新聞 2014年11月07日)
図解でわかる!日本の発電割合(2025年公表データ)
(エナリスジャーナル › エネルギー)
エネルギーミックスの重要性
(一般財団法人 日本原子力文化財団)
再生可能エネルギーの導入ポテンシャルから、日本の地域毎の再エネ政策を考えてみる
(日立ハイテク)
再生可能エネルギーとは?その導入状況やメリット・デメリットを解説!
(三井物産Green&Circular)
再生可能エネルギーのメリット・デメリットは?エネルギーの種類別に解説
(SDGsコンパス)
2024の自然エネルギー電力の割合
(2025年6月30日 ISEP)
日本の再エネ導入ポテンシャルは、あとどれくらい残されているのか?
(2022/11/14、SOLAR Journal)
再生可能エネルギーの課題
(関西電力HP)