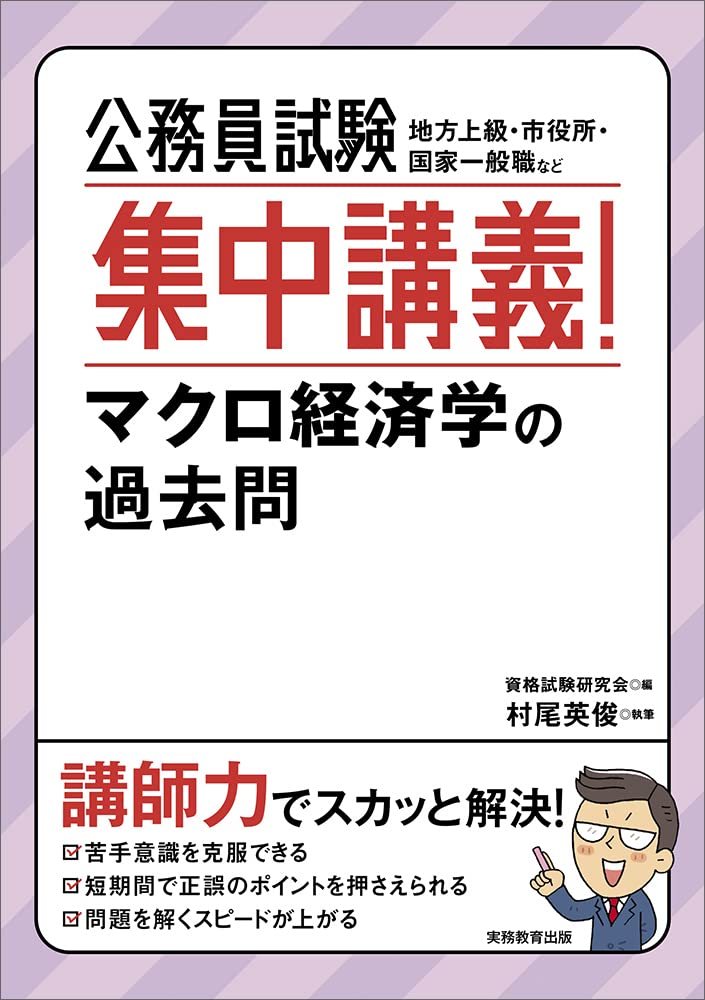火山大国、日本の切り札
太陽光や風力など自然を利用した再生エネルギーについて、連載でお届けしています。地球環境保護や電気代の高騰の観点からも、「再生可能エネルギー」が注目されています。そのなかでも最近、注目を集めているのが地熱発電です。
日本は資源小国(エネルギー資源が少ない)といわれ、約9割を輸入に頼っていますが、その足下には膨大な資源が眠っています。それが地熱で、日本は地熱発電で資源大国になる可能性を秘めています。今回は、こんな地熱発電についてまとめました。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
地熱発電は、クリーンな純国産エネルギーとして、今期待が高まっている、ポテンシャルが高いエネルギーのひとつです。
◆ 地熱発電の仕組み
地熱発電とは、地下にある地熱エネルギーを用いた発電のことで、地下1.5~3km程度まで井戸を掘り、そこから出る蒸気を利用して発電します。
主に火山活動のある地域では、地下深部の数百~数千メートルにあるマグマだまりによって周囲の岩石や地下水が加熱され、発電に適した熱水(高温高圧の地下水)や蒸気が生成されます。
これらが蓄えられる場所は、地熱の熱源(マグマ)である「地熱貯留層」と呼ばれ、一般的に地下1~3キロメートルの深さに存在し、200~300℃にもなっています。
地熱発電では、この地熱貯留層に井戸を掘り、生成された高温高圧の蒸気や熱水(地熱流体と呼ばれる)をパイプでくみ上げて取り出して、タービン(回転式の原動機)を高速回転させて発電します。蒸気でタービンを回すのは、火力発電や原子力発電と同じ手法です。
発電に使用した後の蒸気や熱水は、一定の温度まで冷却して、別の井戸から再び地下に戻され、資源の循環利用が可能となります。
このように、地熱発電は、「生産と還元」を繰り返すことで、安定した電力供給が可能です。水蒸気や熱水には、不純物が含まれる場合もありますが、設備に不純物などが付かない技術や、より効率的な発電設備が開発されています。
発電方法
地熱発電の発電方法には、主に、フラッシュ方式とバイナリー方式があります。
フラッシュ方式は、日本で最も一般的な方式で、地下から取り出した高温・高圧の蒸気や熱水を直接タービンに当てて発電します。
バイナリー方式による地熱発電は、低温熱水で豊富な未利用の地熱資源を活用する際に活用され、新エネルギーとして政策的に推進されており、長崎県の小浜温泉など、主に温泉地で導入が進んでいます。この方式では、地熱流体の温度が低い時に、水よりも沸点が低い媒体を加熱させることで蒸気を発生させ、タービンを回して発電させます。
日本の地熱発電所
日本の地熱発電所は、火山や地熱地域の分布から東北と九州に集中し、70か所以上存在します。このうち、1MW(1000kW)以上の大規模発電所は19基(2022年)で、20kWから250kWの小規模発電所が多数存在します。なお、国内最大の地熱発電所は大分県の八丁原発電所です(発電量11万kW)。
◆ 地熱発電のメリット
資源が枯渇しない
地熱発電は、地下に溜まっている地熱エネルギーを燃料として活用するため、石油や石炭などの化石燃料のように、資源が枯渇するリスクもありません。火山帯に位置している日本は、まさに、地熱発電に適した立地にあると言えます。
天候に左右されず安定供給でき割安
天候で発電量が変化する太陽光や風力と違い、地熱発電は地熱エネルギーを活用するため、天候、季節、時間に左右されることなく、国内で安定した供給を確保できます。実際、地熱の設備利用率は70%と、再生可能エネルギーの中で安定した出力が期待できます。
しかも、地熱発電は、他の再生エネルギーに比べ、発電コストが割安です。1キロワット時あたり10円前後で、太陽光や風力の2分の1から4分の1程度に抑えられ、石炭火力や液化天然ガス(LNG)火力とほぼ同水準です。
CO2排出ゼロ
地熱発電の場合、設備の建設から廃棄に至る発電プロセスにおいて、温暖化の原因となるCO2(二酸化炭素)排出量も化石発電燃料と比較すると大幅に削減できます。実質的に、発電時にCO2を排出しません。
◆ 地熱発電導入の現況
高い潜在的な発電能力
環境省のデータ(2020年度)によれば、世界有数の火山地帯として知られる(活火山が多い)日本の地熱発電の潜在的な発電能力(賦存量)は、2,300万〜2,347万kWと推定されています。
これは、地熱資源を、すべて開発した場合に、約2300万kW(23GW)の発電能力になるという意味で、原子力発電所約23基分に相当する膨大な量です。
国別の潜在的な資源量でみても、日本の地熱資源量は、アメリカ(約3000万kW)、インドネシア(約2800万kW)に次ぐ第3位です。
なお、理論上の賦存量に対して、技術的に可能な最大限の量を示す導入ポテンシャル(技術的導入ポテンシャル)は、設備容量で1439万kW、年間の発電量換算で1006億kWhとなっています。
さらに、これに採算など「経済性を考慮した導入ポテンシャル」では、設備容量で900〜1137万kW、年間の発電量換算で、630〜796億kWhと推計されています。
いずれにしても、日本は世界に冠たる火山大国のため、もともと地熱発電のポテンシャルは極めて高い国です。これらを活用できれば海外からの燃料に依存することもなく、自国でエネルギーを賄うことが可能です。
低い地熱の利用率
しかし、こうした地熱発電の潜在能力を十分に生かしきれておらず、地熱の活用は進んでいません。現在、実際に稼働している地熱発電の設備容量は、約52万kW(2025年4月時点)と、潜在的な発電能力のわずか2.2%程度(資源量に対する利用率2~3%)に留まり、国別では世界10位に後退します。たとえば、資源量こそ日本の4分の1ですが、約4倍の発電設備があるフィリピンとは対照的です。
また、日本の地熱発電所による年間の発電電力量は、約 30億kWh(2023年)で、日本の電力需要の0.3%程度でしかないのが現状です。
太陽光など他の再生エネルギーの電源構成比率は高まっていますが、地熱は、2013年も0.2%と、ほぼ横ばいの状態が続いています。しかも、再生エネルギーの中でも最低水準と振るいません。
*電力の単位
1000kW(キロワット)=1MW(メガワット)
1kW(キロワット)の1000倍が1MW(メガワット)、その1000倍が1GW(ギガワット)
1kWh(キロワットアワー):1kWの電力を1時間使用した場合の電力
◆ 地熱発電導入の経緯
火山帯に位置する(活火山の多い)日本では、戦後早くから地熱発電が注目されていました。1966年に、岩手県八幡平市松川温泉にある地熱を活用した松川地熱発電所が、国内で初めて商用運転を本格的に開始した(稼働させた)のをかわきりに、地熱発電所の建設が進められました。
また、1973年の第一次石油ショックを契機に、地熱発電の開発機運が高まり、国策として盛んに研究・開発が進められました。1996年には発電設備容量の合計が現在とほぼ同程度の50万kWを超え、日本の地熱発電技術は世界有数となったと評されるようになりました。
その後、石油価格が安定化し、国の支援も一巡したことから、地熱発電所の日本国内での新設のペースは鈍化し、地熱開発は「冬の時代」を迎えました。大規模な地熱発電所の新設は、1999年の八丈島の発電所を最後に20年近く途絶えました。
しかし、2011年の東日本大震災での原発事故をきっかけに、再生エネルギーへの注目が高まり、政府は再生エネルギーの普及を目指しました。2012年に固定価格買取制度(FIT)を導入しました。この制度は、再生エネルギーを電力会社が一定料金(通常価格より割高)で、すべて買い取ることを義務付けた制度です。
これをうけて、新たな地熱発電開発プロジェクトは増加傾向にあるものの、太陽光が大幅に発電設備の認定を増やしているのに対して、地熱はポテンシャルを生かしているとは言い難い状況です。
日本で地熱発電の普及が進まないのには、開発の過程に存在するさまざまな課題(デメリット)があるからです。
◆ 地熱発電のデメリット
高い開発コストと時間・開発リスク
地熱の発電コストは、他の再生エネルギーより割安ですが、太陽光と違って大きな設備が必要なため投資額も膨大になります。
資源調査をするだけでも数千万~1億5000万円程度かかるうえ、地下から熱水や蒸気をくみ上げる井戸の掘削にも1本あたり、数億円から10億円かかると試算されています。
しかも、地熱貯留層に向かってピンポイントで掘る必要があるのですが、蒸気が得られる場所を的確に見極めるのは難しく、掘削成功率は2~3割程度とされています。
さらに、地熱発電所の建設には、事前調査から発電所稼働まで(計画、初期調査から、発電・運用まで)の開発期間が10年を超える長期に渡ります。他の再生エネルギーに比べて開発期間が長いのです。
開発期間が長期に及ぶ理由の一つに、3~4年かかる環境への影響も調査しなくてはならないことがあげられます。普及の加速には環境評価の期間を短縮することが望まれています。
しかも、地熱の場合、太陽光や風力のように設置すれば必ず発電できるわけではないという開発リスクを伴います。地表から熱源の位置を正確に知るのは難しく、油田と同じように、発電に必要な水蒸気を確保できるかどうか、また、運用に値する熱源を有するかなど、実際に掘ってみないと地熱発電設備を設置できるか分かりません。
地熱資源が国立・国定公園の敷地内に!
また、日本で地熱発電の導入が伸び悩んできた要因として、地熱資源(地熱貯留層)のある場所はたいてい山地にあり、その8割が、開発制限がある国立公園・国定公園に指定され(に集中し)ていることがあげられます。
歴史的には、1973年の石油危機後、地熱発電が脚光を浴びましたが、当時の環境庁が国立・国定公園での開発に制限をかけたことから、新たな開発は難しくなり、地熱開発は下火になりました。
2011年の東日本大震災の際には、原発事故をきっかけに、地熱を含む再エネが注目されたことから、環境省は、2012年に環境への配慮を条件に、国立・国定公園内での開発を一部認める規制緩和に踏み切りました。具体的には、公園区域外から斜めに穴を掘り、公園内の熱源を回収する方式を認め、たとえば、秋田県では、出光興産などの企業連合が同県内の国定公園の一角で掘削調査に着手しました。しかし、開発の勢いは続きませんでした。
地域住民との合意形成
地熱資源の豊かな場所は、国立・国定園以外に、温泉地と重なることが多くあります。温泉施設で、近隣に地熱発電のための井戸を掘るとなると、温泉枯渇や、環境への影響(周辺の植生や生態系などへの影響、地下を掘る際に毒性のある流体が出てくる可能性など)を懸念した住民や温泉事業者からの反対を受け、地熱発電設備の設置が始められない事例もあります。
実際の温泉への影響については、地中の温泉が出る層(黄色部)と地熱の熱源(マグマ)がある地熱貯留層(オレンジ部)とは深度が異なるうえ、温泉用に掘る井戸と地熱貯留層の間には水を通さない岩(キャップロック)があるため、一般的には、温泉貯留層と地熱貯留層の水は接続していない(影響は少ない)というのが地質学上の常識となっています。
しかし、絶対にないとは言い切れないので、科学的な監視(モニタリング)システムの構築が必要との見方が一般的で、地熱貯留層や温泉の高度モニタリング技術の開発なども進められています。
また、自然豊かな場所に大きな音を出す発電施設ができることへの景観や、開発に関連した地震が起こる可能性なども否定できません。
適地が限られ、土地開発ができていない
このように、国立・国定公園や温泉地付近に地熱資源が存在していることから、大規模な地熱発電設備を設置するための土地の開発が行われていません。しかも、地熱発電に適した場所は主に東北と九州に集中していますが、そこは、道路さえもないような場所であることも多くあります。
こうした制約により、日本では1990年代半ば以降、新たな地熱発電所の開発が停滞し、設備容量は長らく横ばいの状態が続いているのです。
◆ 政府による地熱の開発目標
日本政府は*カーボンニュートラルの達成に向け、2030年度までに温室効果ガスを、2013年度比で46%削減する目標を掲げていることから、再生可能エネルギーの普及拡大が求められ、地熱発電に再び注目が集まっています。
*カーボンニュートラル
温室効果ガスの排出量と除去量を均衡させて温室効果ガスを全体としてゼロとする目標。
政府の開発シナリオでは、2020年3月末時点における地熱発電設備の導入量の合計量は59.3万kWでしたが、2030年度における導入目標として、2017年比で2~3倍の出力累計となる、140〜155万kW(約150万kW)を目指しています。
これにより、発電総電力量に占める地熱発電の割合(電源構成比率)は、2030年には1.0%と、2023年の0.3%の3倍以上に増加すると見込まれています。
また、2025年2月に発表された「第7次エネルギー基本計画」によれば、政府は、2040年までに電源構成に占める再生可能エネルギーの比率を、現在の22.9%から最大50%程度まで引き上げる目標を掲げ、地熱発電についても現状の0.3%から1~2%への拡大を示しました。
この目標を達成させるために、政府は、国立公園内の規制緩和、各種補助金などの手厚い支援、大学・研究機関との協働による高効率な発電技術・掘削技術の開発支援など、官民一体となって、様々な取り組みを実施しています。
とりわけ、効率的な発電設備の開発が注目されています。日本の地熱発電技術は世界トップクラスで、地熱発電用のタービンは、三菱重工業、東芝エネルギーシステムズ、富士電機の日本企業3社で世界シェアの7割を押さえています。近年においても、各社は「超臨界地熱発電」の分野に手を広げています。
超臨界地熱発電
新エネルギー・産業技術総合開発機構によれば、超臨界地熱発電は、地熱貯留層より、もっと深部(地下3~5km)にあるマグマの塊の上部に存在する、超臨界状態の水(「超臨界水」)を利用した発電方法です。
超臨界水とは、液体と気体の中間的な性質を持つ高温高圧の水で、海洋プレートによって引き込まれた海水を起源とし、400~500℃で、1本の井戸からより大きなエネルギーが利用可能だと考えられています(高い発電出力が得られる)。
実際、岩手県の葛根田地域に超臨界地熱システムが確認されており、100MWの発電が40年以上可能という調査結果も出ているそうです。ただし、超臨界水は腐食性が強く、設備へのダメージや安全性の確保に課題が指摘されています。
このように、地熱発電が今後、普及していくためには、こうした技術開発の成果が待たれます。また同時に、立地する地元との信頼醸成も不可欠です。
地域住民に対しては、温泉街と協業した地域密着型地熱発電所を建設するなど、地域の活性化につながるような工夫が必要となります。たとえば、地熱を地元で必要な電気に当てたり、地元農家のビニールハウスの熱源に活用したり、また、副産物であるお湯もプールや地域の暖房として利用するなどです。
(参照)
再生エネ普及への道、地熱、世界3位の資源量、
(時事解説、日経、2013年9月26日)
地熱発電のしくみ
日本の地熱発電の現状は?ポテンシャル・課題などを詳しく解説
(2024年07月11日、ふるさと熱電マガジン)
地熱発電とは?普及が進まない日本の現状を打破するためには?
(2022-10-07、(ASUENE MEDIA)
「地熱発電」の可能性
(月刊不動産、2024年10月)
地熱発電、なぜ注目?、火山国・日本、資源量世界3位
(2013/11/18付)
【動き出す地熱発電】次世代型開発と投資が本格化
(2025年7月8日 – Energy Tracker Japan)
地熱発電のメリットとは?仕組みや種類、展望や事例をわかりやすく解説
(2024.09.25、GX DiG)