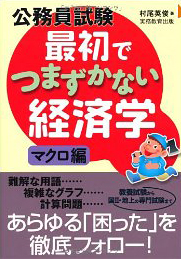御霊神社(ごりょうじんじゃ)
◆御霊神社とは?
御霊神社(ごりょうじんじゃ)は、下御霊神社に対応して、「上御霊神社(かみごりょうじんじゃ)」とも呼ばれ、平安遷都以来、京都御所の北側にある厄除けの神社、王城守護の神、皇室崇敬の神社として知られています。
当時の京都では、御霊信仰(ごりょうしんこう)が盛んでした。御霊信仰とは、その頃、頻発した天変地異や疫病が、時の政争により都を追われ非業の死を遂げた怨霊の祟りであると解され、その御霊を神として祀ることで、疫神・疫病を鎮めようとする信仰です。
御霊神社でも、794年、桓武天皇の弟で、非業の死を遂げた早良親王の神霊を祀った(早良親王は崇道天皇として祀られた)ことをきっかけに、以後、御霊神社は疫病除の霊社として有名になりました(これを御霊神社の始まりとする見方もある、その由来については後述)。
この御霊信仰を祭りにしたのが御霊会(ごりょうえ)で、鎮魂のための儀礼です。京都の夏祭りの多くは御霊会だと言われ、御霊神社の祭礼(御霊祭)が、御霊会発祥の一つと位置づけられています。また、京都の上京区にある御霊神社の一帯は、かつて「御霊の森」が広がっていたとされ、境内は、室町時代の応仁の乱の発端の地になりました。
◆祭神
御霊神社の祭神(祀られている神)は、前述した桓武天皇の弟・崇道天皇(早良親王)だけでなく、奈良・平安時代初期に不運のうちに亡くなった他の七柱の神霊も、八所御霊(はっしょごりょう)として、本殿八座に祀られています。
桓武天皇が794年5月に、崇道天皇の神霊を祀った後、仁明天皇、清和天皇の治世において、井上内親王、他戸親王、藤原大夫人、橘大夫、文大夫の神霊を合祀されました(6柱の神は六所御霊(ろくしよごりよう)と総称された)。さらに、この六所の荒魂として火雷神(菅原道真)と吉備大臣(吉備真備)が併祭されました。
崇道天皇(早良親王)
桓武天皇の弟だった早良親王は、785年、長岡京造営長官・藤原種継暗殺事件に関与したとされ、淡路島に左遷され、断食死してしまいました。
井上大皇后(いのえのおおきさき)
他戸親王(おさべしんのう)
井上大皇后(井上内親王)は、桓武天皇の異母で、(桓武天皇の父、光仁天皇の姉の)難波内親王を呪い殺した嫌疑により、子の他戸親王(桓武天皇の異母弟)とともに幽閉され、母子同時に死去しました。毒殺されたと言われています。
藤原大夫人(ふじわらのたいふじん)
生前の名前は、藤原吉子(よしこ)で、桓武天皇の夫人でしたが、謀反の嫌疑により、子の伊与親王(いよしんのう)とともに大和川原寺に幽閉され飲食を絶たれ没しました(死後、藤原大夫人として祀られた)。
橘大夫(きつだいぶ)
有力貴族であった橘逸勢(たちばなのはやなり)のこと。生前、橘逸勢は、842年の承和の変(伴健岑とともに皇太子恒貞親王を奉じて東国で謀反を企てたとされる)に連座したとして捕らえられ、伊豆へ流される途中で没しました(この事件は、藤原氏による最初の他氏排斥事件となった)。
文大夫(ぶんのたいぶ)
有力貴族であった文屋宮田麿命(ふんやのみやたまろ)のこと。生前の文屋宮田麿命は、843年に突然謀反の疑いありとの訴えにより、伊豆に配流されました。
火雷神(からいしん)
火雷神(火雷天神)とは、太宰府左遷後に悶死した菅原道真のことと解釈されがちですが、時代が合わないため、上記六神(六座)の御霊の「荒魂」と解釈されています。
吉備大臣(きびのおとと)
吉備大臣は、有力貴族の吉備真備(きびのまきび)のことという説もあります。確かに、吉備真備は、藤原仲麻呂に疎まれ、筑前守に一時左遷されたこともありますが、怨霊になったという話しはありません。従って、上記六座の御霊の「和魂」と解釈されています。
荒魂・和魂
神道には、神さまを祀るだけでなく、神さまの魂を祀るという考え方があり、「荒魂(あらたま)」は、神様の荒々しい力を示す神霊であるのに対して、「和魂(にぎたま)」は穏やかな働きのことをいいます。
これらの八神は、平安京鬼門に祀られ八所御霊大明神と称されました。現在、御霊神社には12柱の神霊が祀られ、分祀も30余社あるとされています。
◆御霊祭
前述したように、上御霊神社の祭礼である御霊祭は、御霊会(怨霊の退散を祈願した御霊信仰の祭り)の発祥で、京都で最も古い祭礼の一つとされています。863年、平安京で「咳逆病」が流行し、朝廷主催の御霊会が神泉苑で行われました。このとき、六座(崇道天皇、井上内親王、他戸親王、藤原大夫人、橘大夫、文大夫)の神座を設け、祀られたとされています。
かつて、御霊祭は、神幸祭(7月18日)から還幸祭(8月18日)まで一カ月に渡り行われ、江戸時代には、天皇、皇族も高覧されました(現在は、5月1日から5月18日まで催されている)。神輿(みこし)は、明治になって1871年以来途絶えていましたが、2009年に神輿の御所巡行が約140年ぶりに復活しています。
◆由緒と経緯
御霊神社の創建と変遷の詳細は不明とされています。かつて、この京都の一帯は山背国愛宕郡出雲郷と呼ばれ、794年の平安遷都以前から先住していた出雲一族の居住する地域でした。
飛鳥時代~奈良時代
延暦年間(728-806)にかけて、出雲一族の氏寺としての出雲寺(上出雲寺)が創建されました。一説に最澄が開創したとも言われています。このお寺は、「上出雲寺(かみついずもじ)」と「下出雲寺(しもついずもじ)」に分かれており、その後、上出雲寺に鎮守社(寺の鎮守のために建立された神社)として御霊社が建てられ、これが現在の御霊神社(上御霊神社)になったと言われています。
移住氏族である出雲氏は、天穂日命(あめのほひのみこと)を祖神とし、賀茂氏とともに北山城盆地の開拓に関わったとされています。飛鳥時代、672年の壬申の乱で大海人皇子(後の天武天皇)に付き戦功をあげ臣の姓を賜りましたが、その後、出雲氏の勢力は弱く、平安時代初期にはすでに衰微していました。これに伴い寺も衰退した半面、御霊神社が、中世(鎌倉時代-室町時代)まで上出雲寺御霊堂として知られていきました。
平安時代
794年、桓武天皇の勅願により、平安京の守神として、非業の死を遂げた桓武天皇の弟・早良親王(崇道天皇)の神霊が祀られました。
863年、悪疫退散の御霊会が勅命で催されました(御霊会の始まり)。
室町時代
1423年、足利義満が参詣し、太刀を奉納しました。
1427年、足利義持が社殿を寄進しました。
室町時代、御霊神社の「御霊の森」が応仁の乱(1467-1477)の発端となりました。応仁の乱とは、8代将軍・足利義政の時代、管領家の畠山、斯波家の跡目争いと、幕府管領の細川勝元と山名持豊(山名宗全)らの権力争いが絡んだ争乱です。1467年1月、御霊神社の森に布陣した畠山政長を、畠山義就の軍が攻めた「御霊合戦」を機に、戦乱は応仁の乱へと拡大していきました。
1478年12月:御霊神社、焼失。その後、足利氏により再建されました。
江戸時代
後陽成天皇(在1586年12月~1611年5月)が、神輿と牛車を寄進されました。
霊元天皇(上皇)の時、1723年9月、1729年2月に行幸されました。この時、願文(がんもん)が納められ、以後、天皇家の産土神(うぶすながみ)になりました(産土神とは、神道において、その人が生まれた土地の守護神を指す)。
光格天皇の時代、1788年の天明の大火により焼失しましたが、1790(1791)年に、内侍所(ないしどころ)が寄進され、1798年現在の拝殿が建立されました。
明治時代
1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈が行われ、1871年以降、御霊祭の御所巡行が途絶えましたが、1877年2月、明治天皇は勅使を参向させました。
現代
1952年12月、当時、皇太子・明仁親王の成年式、立太子礼奉告の幣帛(へいはく=お供え物)を献じられました。
1968年1月、本殿の再建復興に際し、昭和天皇、常陸宮、秩父宮、高松宮、三笠宮の四宮家よりの寄進があり、1970年に本殿が再建されました。
2002年、11月、当時の皇太子・徳仁親王が行啓されました。
2009年、御霊祭の御所巡行が復活しました。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆
下御霊神社
下御霊神社(しもごりょうじんじゃ)は、京都御所の南東(中京区)にあり、上御霊神社同様、御霊信仰に基づいて創建され、古くより京都御所の産土神(うぶすながみ)として知られています。社名は上御霊神社に呼応しています。
◆由緒
下御霊神社は、平安時代の839年、仁明天皇(在位833-850により、出雲一族の氏寺の一つ下出雲寺(しもいずもでら)の鎮守社(下出雲寺御霊堂)として創建されました。伊予親王(桓武天皇第3皇子)とその母・藤原吉子(桓武天皇夫人)を慰霊するためで、ほかにも、怨霊を慰めることが目的に政争に巻き込まれて憤死した人々を祀っています。
御霊神社(上御霊神社)の南に位置し、下出雲路の地に祀られたことから下御霊神社と呼ばれるようになりました。現在の下御霊神社は、1590年、豊臣秀吉の都市整備にともない、現在地である西園寺実氏の別荘・常盤井殿があった地に遷座しました。
◆祭神
八所御霊の御霊社に以下の6柱が祀られました。
伊予親王(いよしんのう):桓武天皇の皇子
藤原大夫人(ふじわらのたいふじん)(=藤原吉子よしこ):伊予親王の母
祟道天皇(すどうてんのう)(=早良親王):桓武天皇の皇太子
藤大夫(とうだいぶ) (=藤原広嗣)
橘大夫(きつだいふ)(=橘逸勢)
文大夫(ぶんのたいふ)(=文室宮田麻呂/ふみやのみやたまろ)
上御霊神社では祭神となっていた、井上大皇后(いのえのおおきさき) 、他戸親王(おさべしんのう) の親子に代わり、下御霊神社では、伊予親王(いよしんのう)と、藤大夫(とうだいぶ)が6座神霊に加わっています。
これらの6座の神霊に、吉備聖霊(きびのしょうりょう)と、火雷天神(からいてんじん)の二座が加えられ、祭神は八柱となり、「八所御霊」と称されています。
吉備聖霊(きびのしょうりょう)
吉備真備とされることも多いが、吉備真備は憤死した人ではないので、神社側は六座の神霊の和魂(にぎたま)と解されています。吉備真備と習合
火雷天神(からいてんじん)
菅原道真とされることも多いが、神社の創建は、道真が天神とされるよりも以前なので、神社側は六座の神霊の荒魂(あらたま)と解されています。菅原道真と習合
また、相殿(あいどの)として、天中柱皇神(あめのなかはしらのすめがみ)として、霊元天皇が祀られています。霊元天皇(在位1663-87)は、上皇の時代の1723年9月、1729年2月に行幸されました。この時、願文(がんもん)(神仏に願を立てる時、その趣旨を記した文)が納められたことを契機に、当時の神主である出雲路信直・直元父子は、天皇(上皇)と親交を深めたとされ、1732年の死後、霊元天皇の霊を配祀しました。
相殿:神社の主祭神に対して,1柱またはそれ以上の神を合祀すること。
さらに、境内にある猿田彦社、垂加社、柿本社には、それぞれ 神話の猿田彦、垂加神道を唱えた山崎闇斎、柿本人麻呂を祀られています。
このように、上御霊・下御霊の両社は、天皇家とのゆかりが深く、国家、皇室、都民守護の社として朝野の崇敬を集めてきた歴史があり、現在も、全国各地に散在する御霊神社の中でも代表的な存在です。
<参照>
御霊神社HP
下御霊神社HP
きょうとnavi
Kyoto design
京都風光(京都寺社案内)HP
Wikipediaなど